D 「僕はこれが知りたいので、○○の学会に行きたい」と自分で言ってくる人は、主体性があると思うし、「○○の講座に行ってみたいんだけど」って言ってきてくれると、「ちゃんと考えてんだね」と思います。(製造)
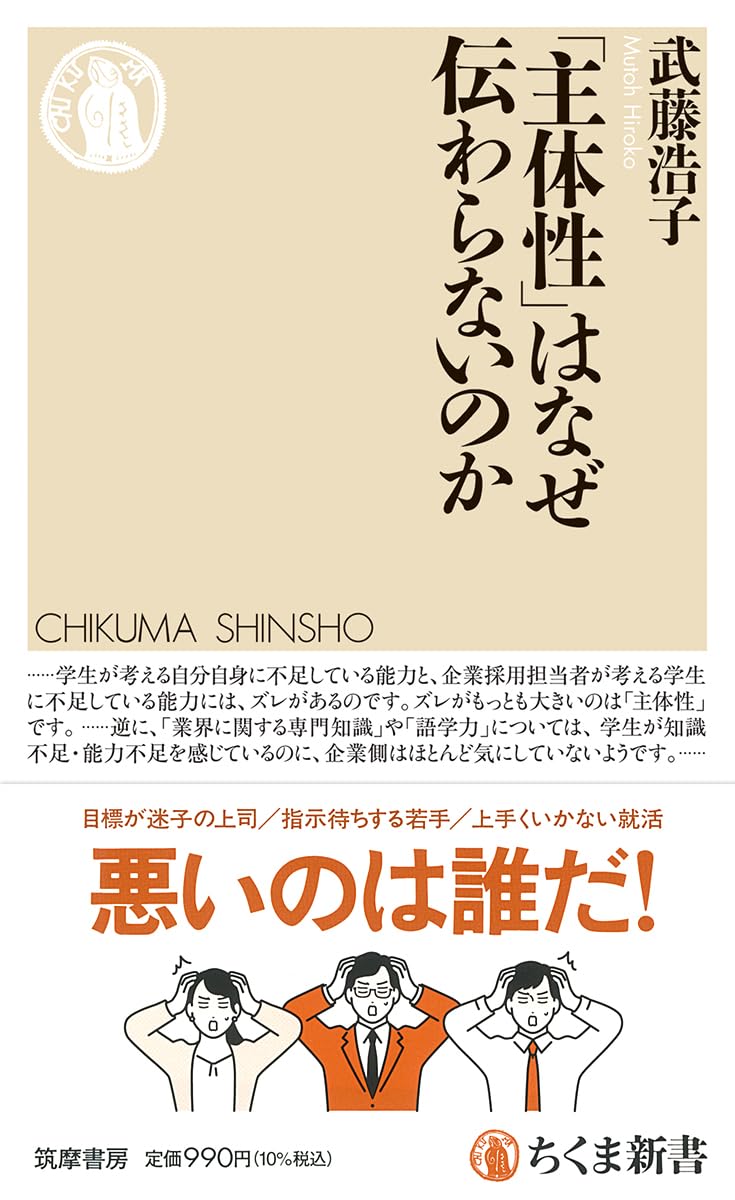 『「主体性」はなぜ伝わらないのか』(武藤浩子、筑摩書房)
『「主体性」はなぜ伝わらないのか』(武藤浩子、筑摩書房)
このように自分なりに先を考えていることが伝わると、「主体性がある」とされるようです。逆にいうと、自分なりに何か考えていても、発信しないならば、主体性があるとはみなされないのです。
では、発信さえすればよいのでしょうか。発信したとしても、それらしいものをコピー&ペーストするだけでは、「自分なりに考えていない」と判断されるようです。
A 逆に高学歴のほうがコピペで済ませちゃうみたいなところあるね。正しい答えっぽいのを言うけど、全然心が入ってないみたいな。(製造)
このように「高学歴のほうが」と大きくくくられると、すこしギョッとするかもしれませんね。Aさんの発言を続けてみてみましょう。
A 若手社員が「これが答えです」って言うけど、「で、お前どうしたいの」って聞いたら、「えっ」ていう顔をするから。「それはどういうことですか」って、「僕が何したいかって」。そんな質問をされたことがないから驚きなんです。でも僕もそうでしたけどね。(製造)
主体性を持って仕事をするには
正解を追い求めていてはダメ
もし、「で、お前どうしたいの」って上司に返されたら、「いや、そんなこと急にいわれても……と思うな」という方もいらっしゃるかもしれません(あと「お前っていわないで欲しい」と感じるかも)。仕事経験が浅い方であれば、「まだ仕事に関する知識も経験もそれほどないのに、自分が何をしたいかなんてわかるわけないよ」と言い返したくなるかもしれません。その考えはもっともだと思います。
このAさんは、高校や大学で求められたのは「教科書に書いてあること、答えがあることに、いかに早く到達するか」であったとも言いました。長年、正答を追う教育を受けたため、Aさん自身も含めて高学歴といわれる人(≒学校に適応してきた人)のほうが、「自分なりに考える」ことが難しいと考えていたようです。
Aさんは、自分自身の反省を踏まえて、若手社員には、コピー&ペーストするだけではなく、自分なりに考えてもらいたいと思っている。そこで“良かれ”と思って「で、どうしたいの」という声掛けをしているのかもしれません(これが私の見立てです)。







