KPIでは見えない「デザインの成果」
企業におけるデザイン賞の活用方法
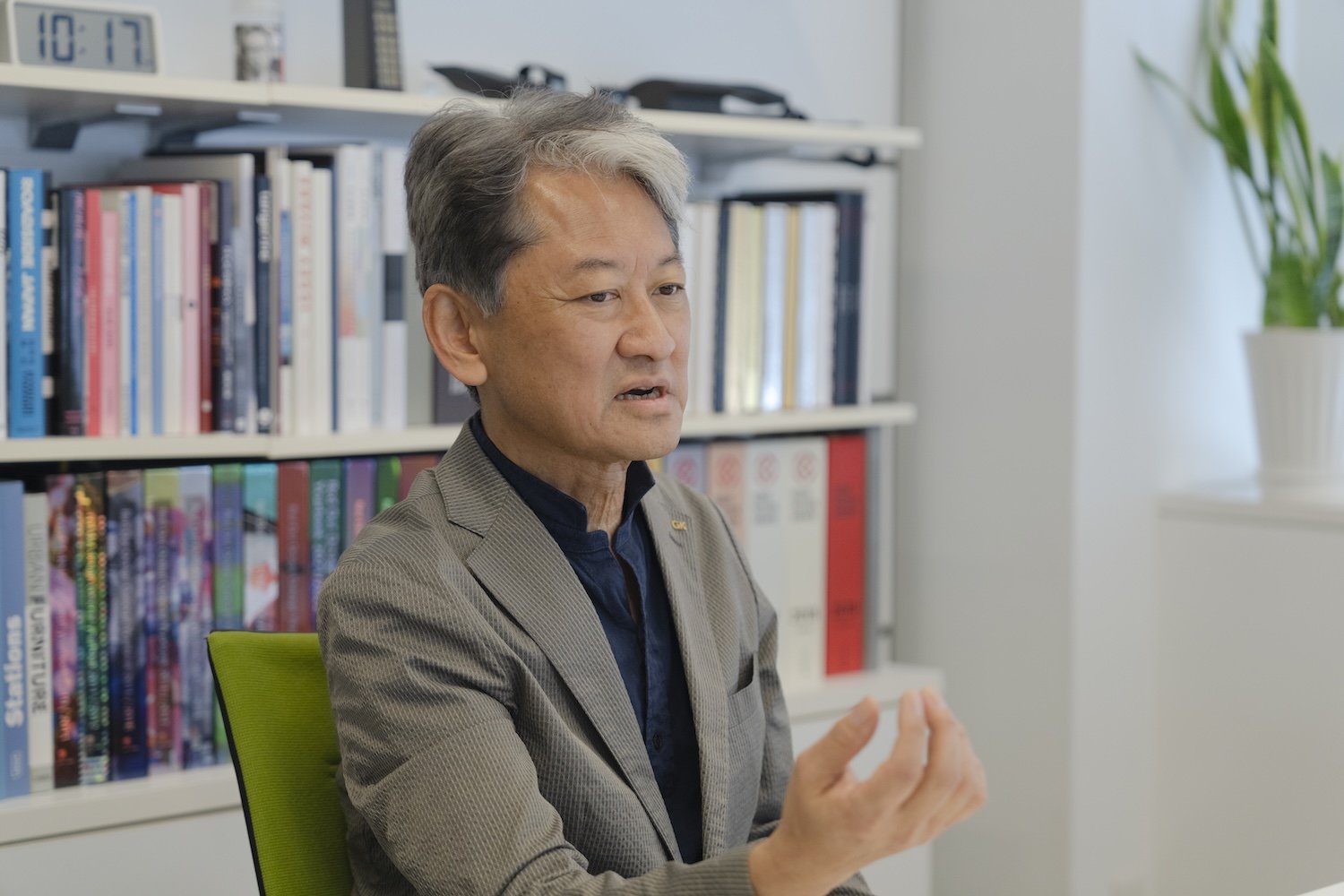
――この提携によって、応募する企業やデザイナー側にとっては、どんなメリットがあるのでしょうか。
最大のポイントは、レッドドット賞へのアクセスが格段にしやすくなることです。これまでは英語での応募や手続きの煩雑さがネックでしたが、今回の提携によって、日本語での情報取得やサポートが可能になります。
つまり、世界最高峰のデザイン賞に「挑戦しやすい環境」が整うということです。
――レッドドット賞としては、日本からの応募を増やしたいという意図があると聞いています。日本のデザインに対するどのような評価があるのでしょうか。
先ほど触れましたが、日本の中では「造形の質」がやや軽視されてきた面があります。けれども海外では、むしろその部分こそが日本のデザインの価値として高く評価されているんです。レッドドット賞のプレジデントであるピーター・ゼックも、「モダンデザインは日本の影響を受けている」と言っています。北欧などでも、そうした日本的な美意識を評価する展覧会が開かれていますし、国際的にも日本のデザインに対する尊敬の念は強いと思います。
また、レッドドット賞には、アジアでは中国からの応募が非常に多いのですが、かなりの割合で落選します。一方で、日本は応募件数こそ少ないけれど、受賞率はとても高い。だからレッドドット賞側としても、「もっと日本のデザインに参加してもらいたい」という意図があるわけです。今回の提携も、そうした思いが重なって実現したものといえます。
――デザイン賞は、企業がデザインの質を高める動機になると思われますか。
最近は、デザイナーをKPI(重要業績評価指標)で評価しようとする企業も増えています。経営の視点からすれば、デザインを数値で捉えようとする姿勢自体は健全だと思います。ただし、定量だけではどうしても限界がある。ビジネスの成果とデザインの関係を、明確な因果として証明するのは簡単ではありません。
そこで意味を持つのが「賞」の存在です。デザイン賞は、デザイナーの職能に対する客観的な評価の仕組みであり、同時に、モチベーションを高める装置でもあります。
さらに、受賞を通して経営者層がデザインの成果を実感することで、組織全体に「デザインをどう生かすか」という意識が浸透していく。
ちなみに、レッドドット賞では、毎年「ベストデザインチーム」を表彰しており、製品以上にデザイナーに光を当てています。ここが、グッドデザイン賞などとは大きく異なる点ですが、企業のデザイン組織において、デザインの質を高める動機付けに、非常に有効だと思います。







