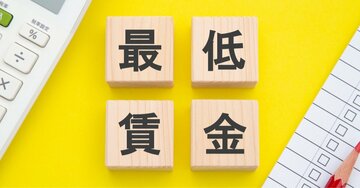今年9月までの1年間の女性非労働力人口(20~69歳)
の減少数
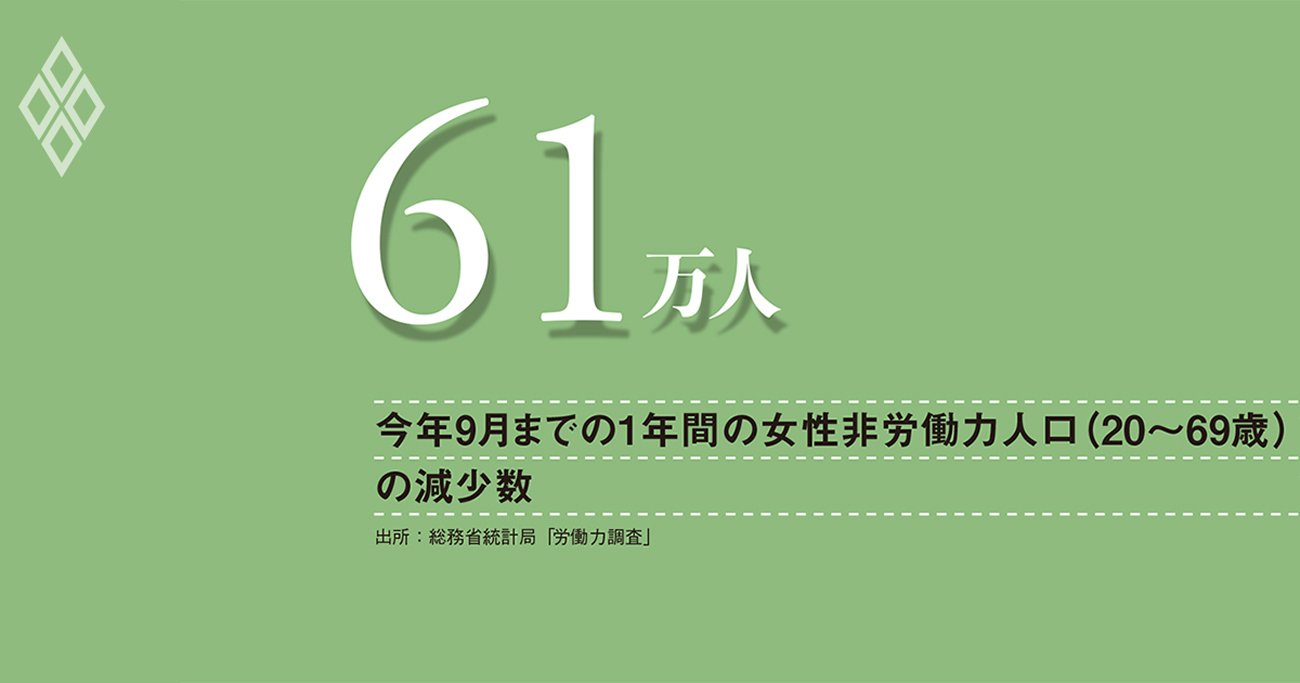
植田和男・日本銀行総裁はこの夏、金融政策の決定に当たり、需要面だけでなく供給面にも注目すべきだと述べた。労働市場が転換期にあるからだ。
労働投入量は労働時間と就業者数から構成されるが、労働時間は働き方改革などで顕著に減る一方、就業者数が高齢者や女性の労働参加で増え、人口減でも労働投入量の減少は抑制されてきた。
だが、今後は高齢化が進み、高齢就業者の退職が増える。また、低失業率下で女性の就業増加余力を探ると、20~69歳の女性非労働力人口はこの1年で61万人(7.2%)減少した。「日本の将来推計人口」(2023年)でも、同年齢層の女性人口は今後5年間で93万人程度減ると推計されている。近年、就業者数は横ばい圏にあるが、今後は外国人なしでは減少は避けられないだろう。
他方、労働時間は、非正規雇用や短時間就業の女性が多く、増加があり得る。週35時間未満で働く女性就業者のうち、追加就業希望者は今年1~9月平均で196万人に上る。「年収の壁」が緩和される中、正規雇用化やテレワーク、スポットワークなどの活用もあろう。
しかし、追加就業希望者は女性短時間労働者の12.2%にとどまる上に、「年収の壁」対策も労働時間の基準は据え置かれたままだ。
また、今後は介護問題が深刻化する。「就業構造基本調査」(2022年)によると、働きながら介護する者は既に365万人。介護人材はAIによる代替が限定的であるため、さらなる人材不足が見込まれ、特に女性の負担が重くなろう。こうした状況下、平均労働時間の増加は期待しにくい。
完全雇用や需給ギャップの解消がほぼ実現した現在、このような労働投入量の制約は成長や物価にとって大きなリスクであり、高圧経済論は適切でない。
需要拡張的な財政政策は人手不足を遍在化かつ深刻化させ、成長を阻害し、賃金・物価を過度に押し上げかねない。むしろ必要なのは需要刺激策ではなく、労働市場のミスマッチ解消など生産性を上げる供給面の政策だ。
10月の日銀「展望レポート」でも、労働の供給制約によって賃金・物価に上昇圧力がかかるとしている。物価高が続く中、日銀も早急に過度な緩和から脱却すべきだ。
(キヤノングローバル戦略研究所 特別顧問 須田美矢子)