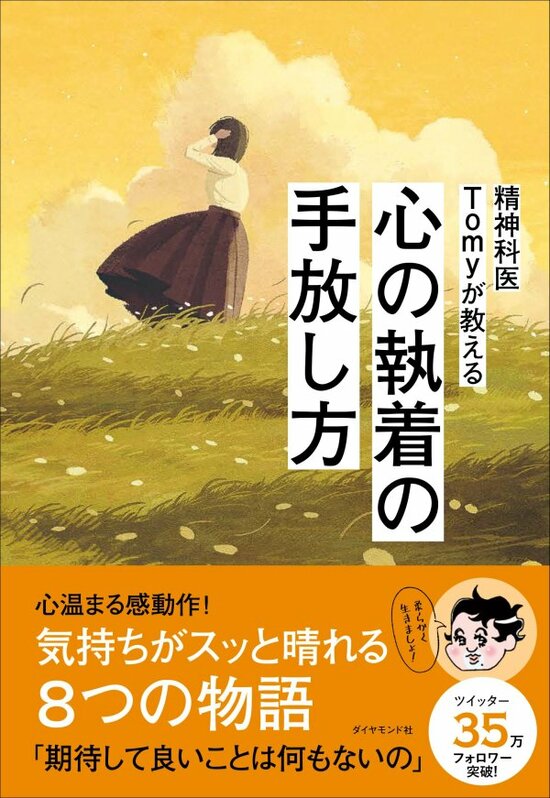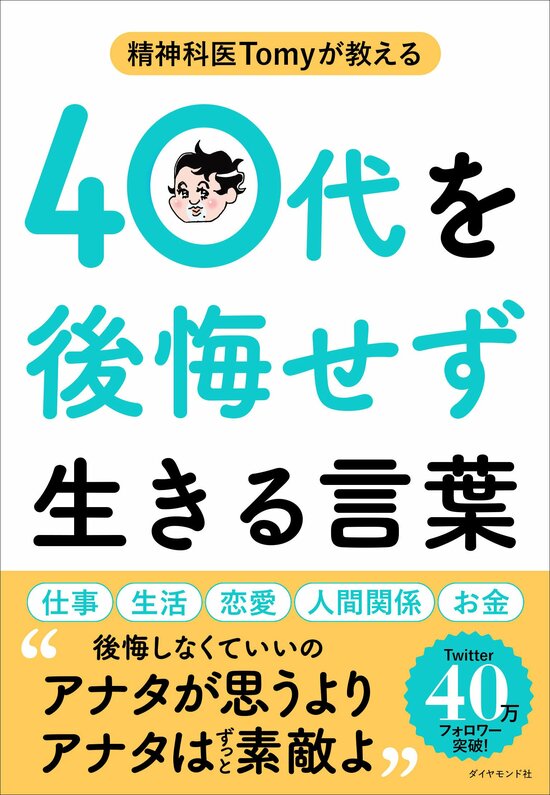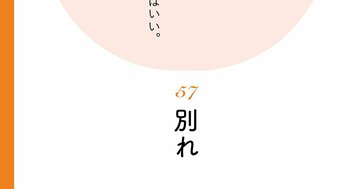自分のミスを棚に上げ逆ギレ…話が通じない人の脳内で起きていること
誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 40代を後悔せず生きる言葉』(ダイヤモンド社)など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。
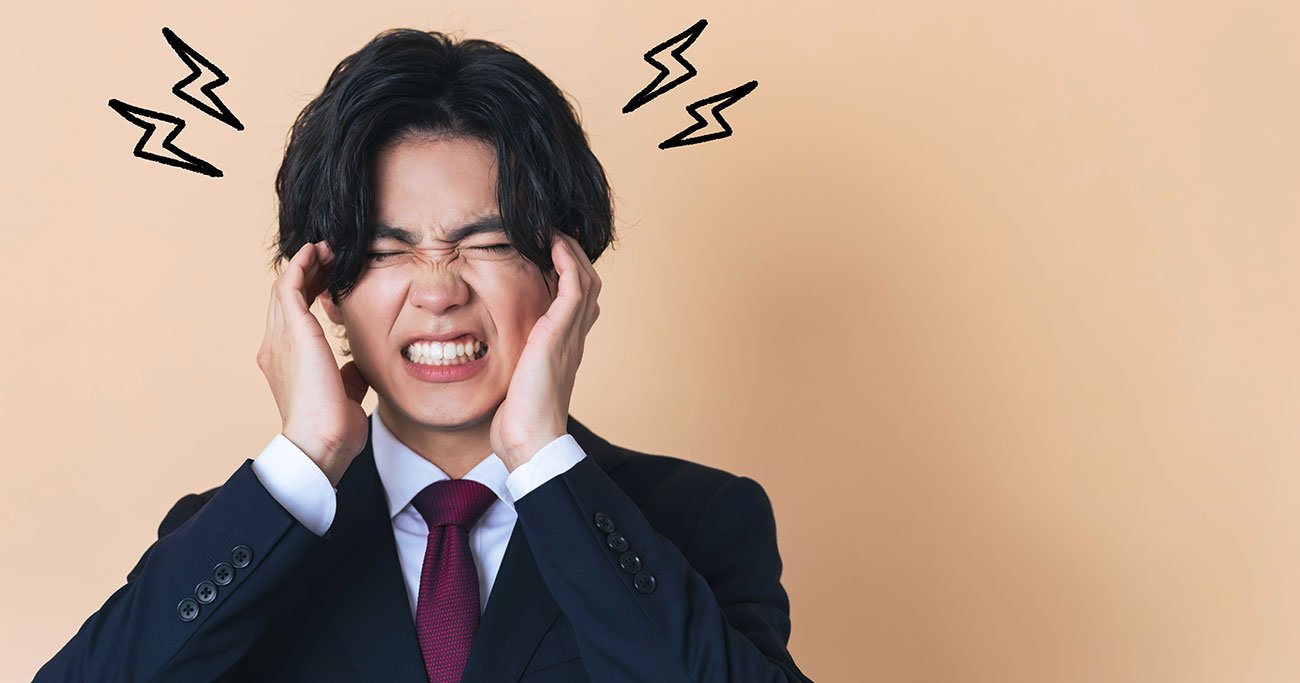 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
こんな人には気をつけよう
今日は、人間関係において「こういう防衛機制(ぼうえいきせい)を使う人には気をつけたほうがいい」というテーマでお話しします。
心を守るための「防衛機制」とは?
まず、「防衛機制」について少し解説します。これは元々、精神分析の世界から出てきた言葉です。医学的に完全に証明されたものではありませんが、人の心を理解する上で非常に分かりやすい概念です。
人間は生きていると、そのまま受け入れるには辛すぎる現実や、自分の心の中で矛盾する葛藤に直面することがあります。そんな時、心を守るために無意識に自分の気持ちを加工してしまうことがあります。
この「心の加工パターン」のことを防衛機制と呼びます。例えば、以下のようなケースが挙げられます。
タバコの例(合理化・否認)
ヘビースモーカーの人がいるとします。「タバコは体に悪い」という事実は分かっているけれど、「吸いたい」という欲求がある。この矛盾(認知的不協和)を抱えると苦しいですよね。
そこで、「近所のおじいさんはヘビースモーカーだけど100歳まで生きたから、俺も大丈夫だ」と思い込むことで、自分の行動を正当化し、不安を解消しようとします。
すっぱいブドウの例(合理化)
イソップ童話のキツネの話が有名です。高いところにあるブドウが欲しいけれど、どうしても手が届かない。この悔しさを解消するために、「あのブドウはどうせ酸っぱくて美味しくないに違いない」と決めつけることで、欲求を抑え込みます。
このように、防衛機制は誰もが無意識に使っているものであり、自分を守るために必要な機能でもあります。
最も厄介な防衛機制
「投影(とうえい)」とは?
防衛機制には様々な種類がありますが、中には人間関係をこじらせる厄介なものがあります。今回特に注意していただきたいのが、「投影」というタイプです。
「投影」とは、自分が相手に対して抱いている感情や後ろめたい気持ちを、相手が自分に対して抱いていると思い込むことを指します。
なぜこの話をするかというと、私の友人が仕事で体験したあるトラブルが典型的な例だったからです。
理不尽に怒り出したクライアント
私の友人が、ある新規のクライアントと仕事をした時の話です。
そのクライアントは、連絡が非常にルーズでした。「よろしくお願いします」と返事をした後、具体的な日程調整の連絡をしても無視。再度確認しても「確認します」と言ったきり放置されるなど、仕事が全く進まない状況でした。
なんと2年以上にわたり、何度も連絡をしてきたものの、埒(らち)が明かない状態が続きました。困った友人は、失礼にならないよう丁寧な言葉を選びつつ、「質問の意図が伝わっておりますでしょうか?」「進捗はいかがでしょうか?」といったニュアンスで、遠回しに催促をしました。
すると、そのクライアントから突然、激怒した返信や電話が来たのです。「あなたは僕のことを馬鹿にしていますね!」「私のことを軽く見ているんでしょう!」
友人は困惑して私に相談してきたのですが、客観的に見れば、相手を軽んじていたのは(返事を放置していた)クライアントの方ですよね。
自分の非を相手になすりつける心理
このケースで起きているのが、まさに「投影」です。
おそらくクライアント自身も、無意識化、あるいは自覚的に「自分が返事を止めているせいで迷惑をかけている」「自分が悪い」という後ろめたさを感じていたはずです。しかし、プライドの高さゆえに、その「自分が悪い」という事実を受け入れられなかったのでしょう。
そこで、「自分が相手を軽んじている(返事をしない)」という事実を、「相手が自分を軽んじている(馬鹿にしている)」という事実にすり替えてしまったのです。
この「投影」の恐ろしいところは、本人が嘘をついているわけではなく、本気で「相手が悪い」「自分は被害者だ」と信じ込んでしまっている点です。
投影が引き起こすトラブルと対処法
投影は、仕事だけでなく恋愛や日常の人間関係でもよく起こります。自分が相手を好きなのに、その気持ちを認めるのが怖くて「相手が自分のことを好きに違いない」と思い込む(ストーカー心理など)。
自分が相手を(嫉妬などで)嫌っているだけなのに、自分が悪者になりたくないため「あいつが俺のことを嫌っている」と思い込む。
投影を頻繁に使う人が近くにいると、常に「相手(こちら側)が悪い」という構図を作られてしまいます。事実を歪曲され、話が通じなくなるため、トラブルが解決せず泥沼化しやすいのです。ネット上の炎上などで、話が噛み合わなくなるのもこのパターンが多いです。
理不尽な嫌悪から逃れる
もし皆さんの周りに、事実をねじ曲げて「お前がそう思っているんだろう!」と攻撃してくる人がいたら、この「投影」を疑い、距離を置くなど気をつけてください。
そして同時に、自分自身も「あの人は私のことが嫌いなんだ」と思った時、ふと立ち止まって考えてみましょう。「もしかして、私が相手を苦手だと思っている気持ちを投影しているだけではないか?」と自己省察できれば、人間関係はよりスムーズになるかもしれません。
※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)の著者による特別原稿です。