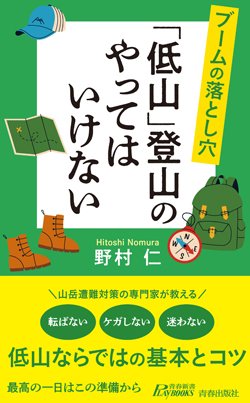注意するだけで遭難は防げる
山岳遭難についてはたくさんの本が出ていますが、その多くは遭難のドキュメント(記録)です。それも、社会を震撼させた大きな遭難や、死亡または重傷となった深刻な事例を取り上げているのが普通です。
さらに、遭難の話には尾ヒレがつきやすいというか、より印象が強まるような描写や構成が加えられていることがあります。遭難記録を読んで読者は恐怖感を与えられ、遭難はよくないもの、悲惨で残酷なものだと考えるようになります。
しかし、本に書かれるような遭難は、どちらかといえば一部の極端な事例です。実際には、この記事で挙げたような事例のほうが多いのです。そのことを知らないと、「遭難は難ルートでの話で、自分には関係ない」と勘違いしてしまいます。
「疲れて体調最悪。もう歩けない」
「だれもライトを持ってない。暗くて歩けない」
「道を間違えた。戻ろうとしたけれど時間切れ」
このような「軽い遭難」は、低山で起こっている典型的なものですが、遭難ドキュメント本になることはなく、新聞やテレビで報道されることもありません。でも、この種の遭難が非常に多いからこそ、年間約3000件という多発状況になっているのです。
リスクマネジメントの理論で、1件の重大事故の陰に29件の軽傷事故が発生しており、299件の事故寸前(インシデント)が発生している、というものがあります。インシデントというのは、事故に至る危険性のあるエラーが起こったことをさします。いわゆる「ヒヤリ・ハット」と呼ばれているものです。
インシデントを少なくすることは、軽傷事故を減らし、ひいては重大事故も減らすことにつながるわけです。
「軽い遭難」の事例はインシデントに近いものです。高尾山では町とはちがう低山の歩き方をすれば、疲れて歩けないこともなくなるでしょう。丹沢ではライトを持っていればよかったですが、夜道を歩く危険性にも注意する必要があります。
遭難は初心者・初級者に関係ないのではなくて、山を歩くときにかならず役に立つテーマです。遭難事例には、「やってはいけない」の見本がたくさん出ていますから、それを見て何がいけないか考えれば、多くのことを学ぶことができるでしょう。