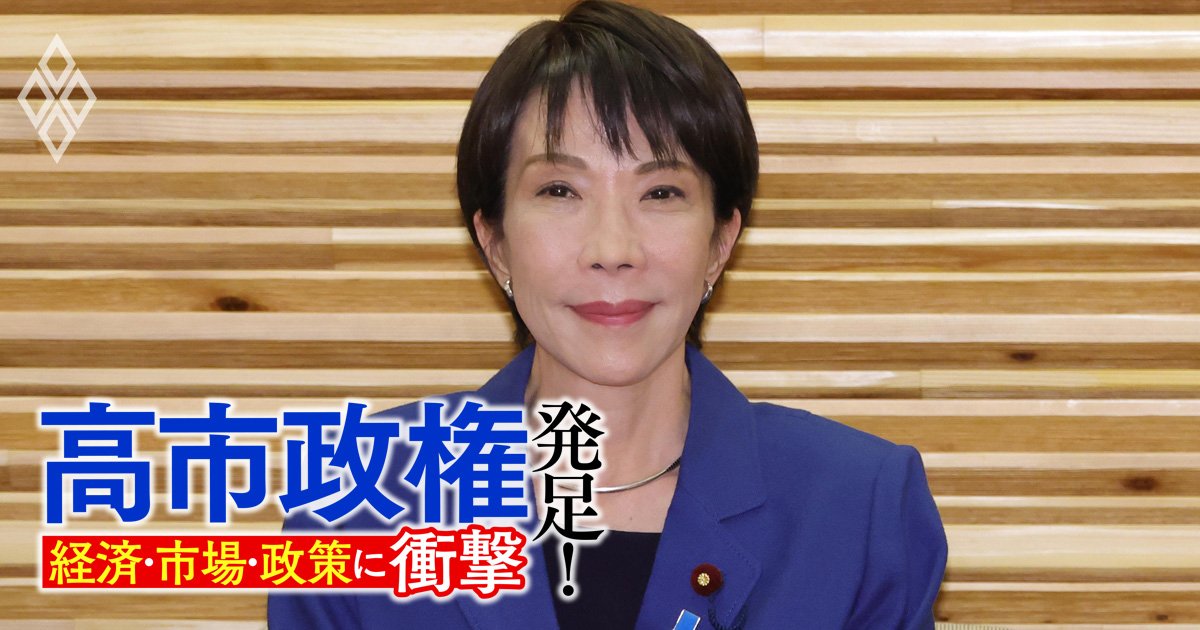 臨時閣議に臨む高市首相(11月21日) Photo:SANKEI
臨時閣議に臨む高市首相(11月21日) Photo:SANKEI
21兆円規模の総合経済対策を閣議決定
「危機管理投資・成長投資」が成長戦略の中核
「強い経済」実現を掲げる高市政権は、当面の最重要課題としてきた物価高対応を中心に、総合経済対策を11月21日に閣議決定した。
物価高対策として2026年1~3月の電気・ガス料金補助(一般家庭で計7000円程度を補助)、ガソリン税等暫定税率の廃止、プレミアム商品券・おこめ券の給付(地方自治体の重点支援地方交付金)、18歳までの子ども1人当たり2万円の給付(児童手当の上乗せ)などが打ち出されたほか、官民連携での危機管理投資・成長投資の促進や防衛費増額、トランプ関税の影響を受ける中小企業の資金繰り支援などが盛り込まれた。
財源の裏付けとなる25年度補正予算における一般会計の追加歳出は17.7兆円と、昨年度(13.9兆円の追加歳出)を上回る。
高い春闘賃上げが続くにもかかわらず、9月の実質賃金(共通事業所ベース)は前年比▲1.0%と9カ月連続で前年比マイナスとなっている。こうした中で、物価高対策は、低中所得層などの生活や消費を支える生活支援策としては意味があるだろう。
一方で、日本経済の現状が供給制約・円安・インフレ局面にある現状を踏まえれば、需要不足・円高・デフレ局面で始まったアベノミクス期と同じように財政拡張・金融緩和のポリシーミックス(リフレ政策)を継続することについては見直しが求められていると筆者は考える。
「サナエノミクス」は供給力を向上させる成長戦略に重きを置くべきだ。特に、投資拡大を通じた「国内供給力」の強化と生産性の向上による「企業競争力」の強化が不可欠だ。
この点で、高市新政権が「危機管理投資・成長投資」を成長戦略の中核に据え、経済安全保障を強化する観点から官民で投資拡大を推進する方針を掲げていることに筆者は注目している。
設備投資拡大や生産性向上は供給面から経済成長率(潜在成長率)を高めるという点でも重要だが、設備投資の拡大による国内の供給力強化は経済安全保障における「自律性」の実現につながり得ると同時に、生産性の向上(技術革新、高付加価値化)を通じた企業の競争力強化は「不可欠性」の実現につながるため、高市首相が重視する経済安全保障への対応とも密接に関連するからだ。
今回の総合経済対策には、危機管理・成長投資関連としてAIや半導体、造船などに対して7.2兆円が盛り込まれたが、政府が危機管理・成長投資で政府が有望領域・産業に重点支援を行い、
企業が人手不足や経済安全保障リスクなどの環境変化に投資拡大を通じて適応すれば、中期的に実質1%の成長が視野に入るとみている。
「サナエノミクス」の真価は、物価高対策よりも危機管理・成長投資でいかに成果を出すかだ。







