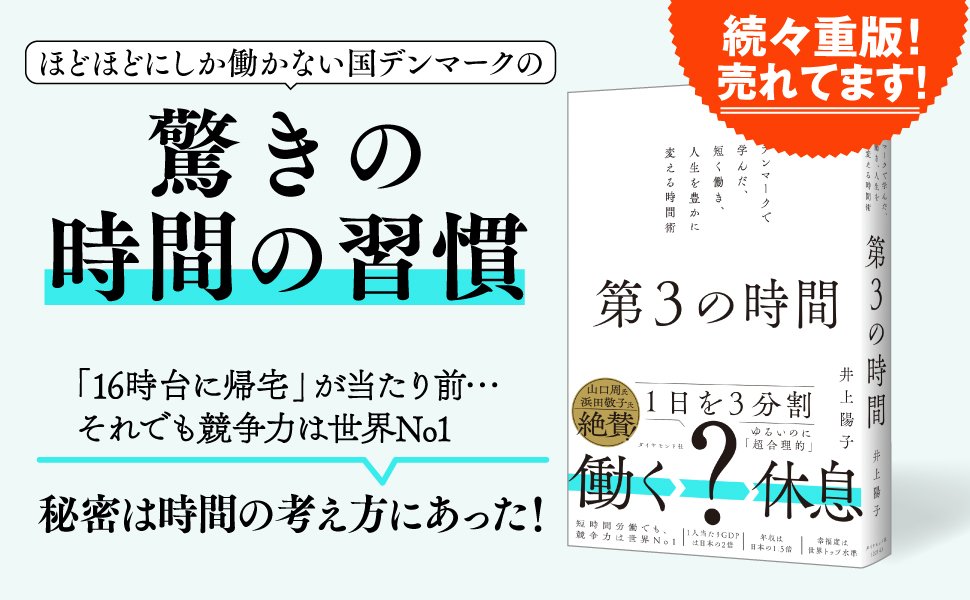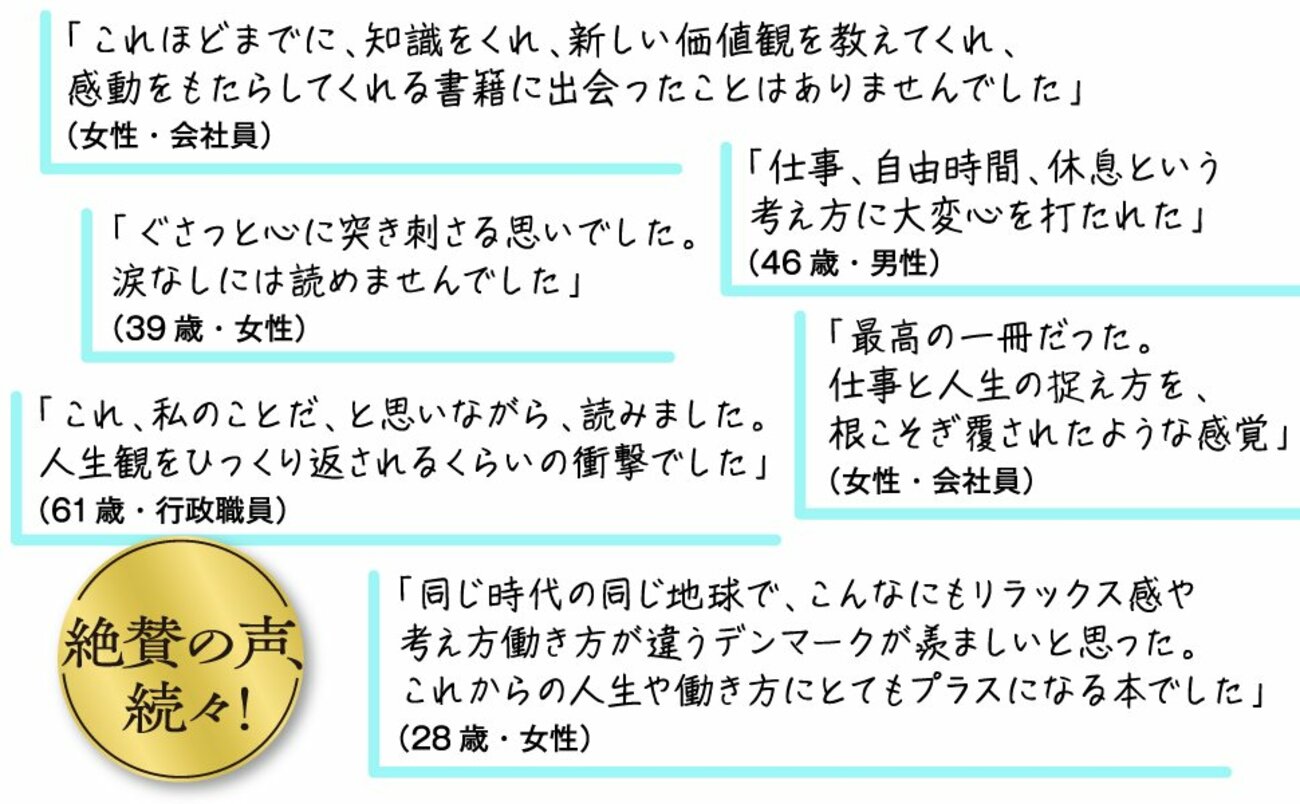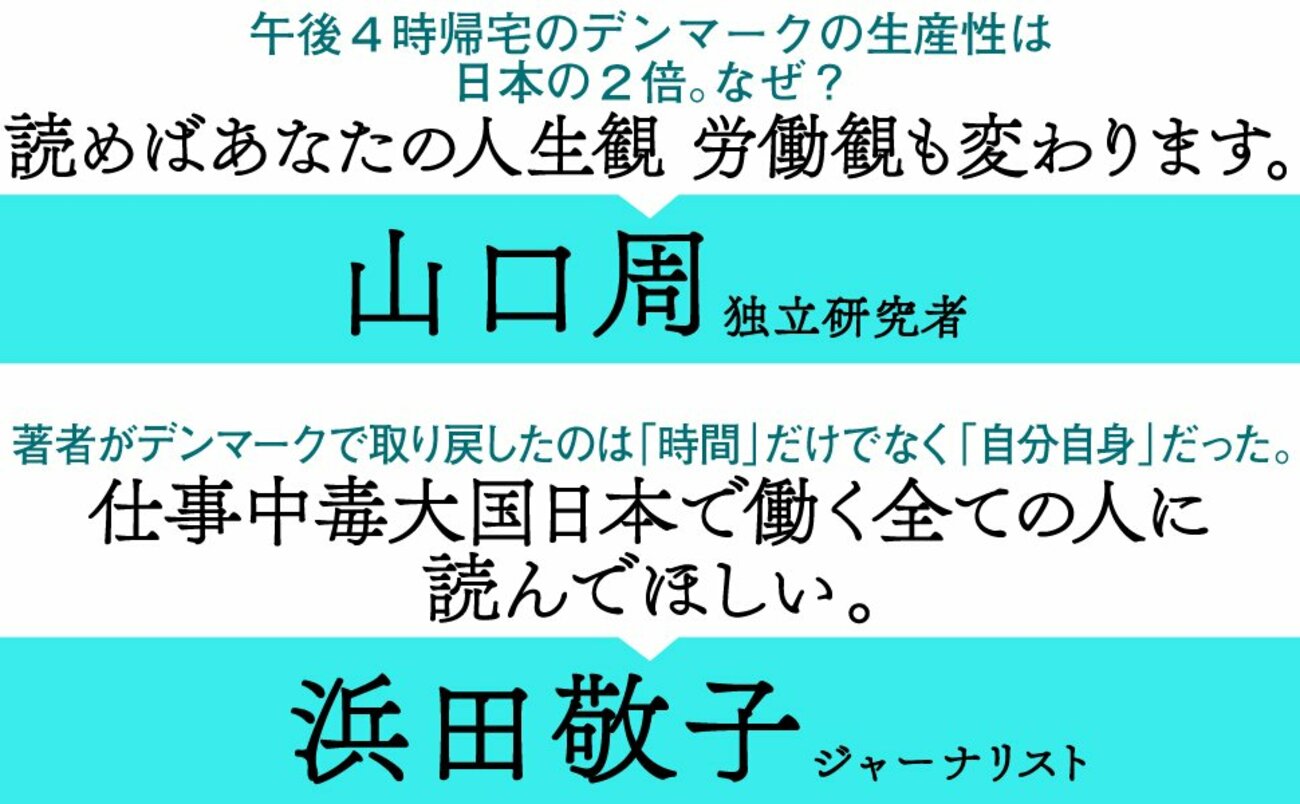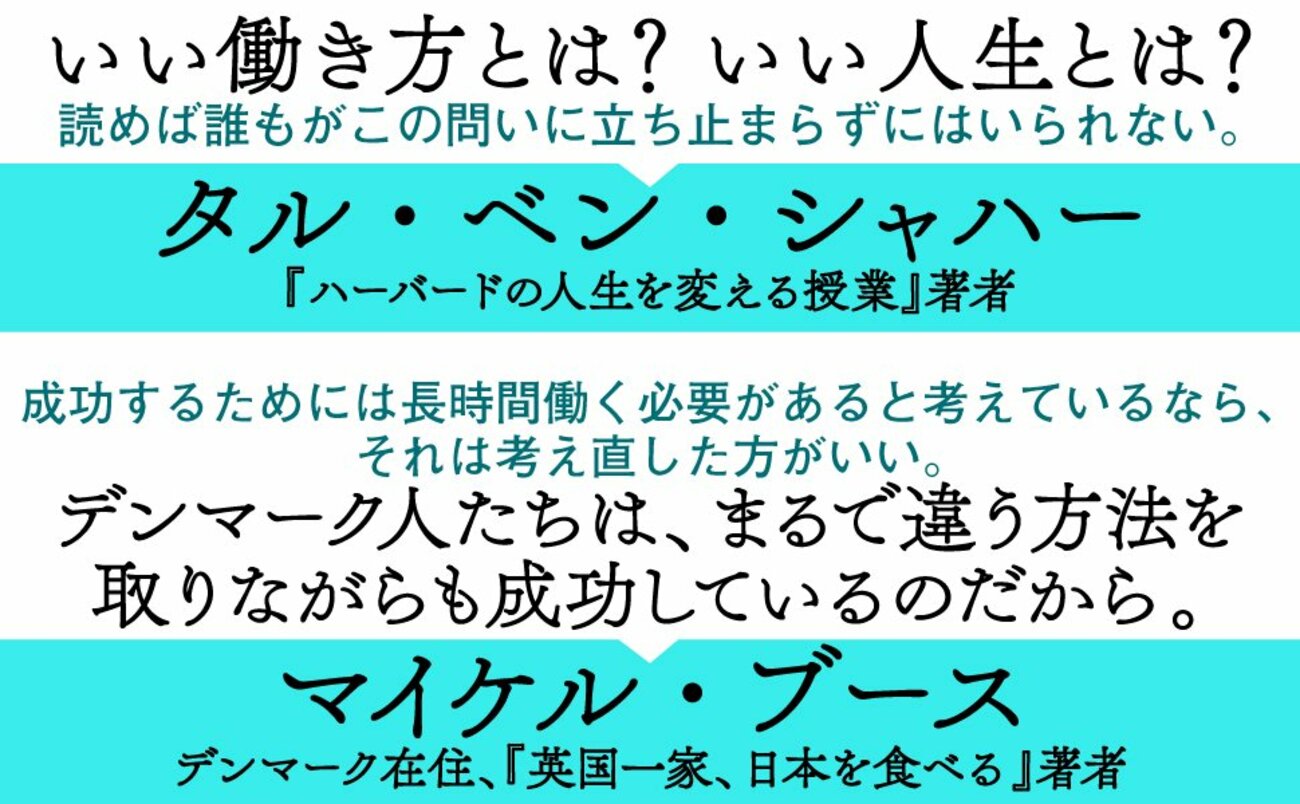16時台に帰宅するのが“普通”の国がある。長時間労働に追われていた新聞記者の著者が、39歳で移住したデンマークで目にしたのは、16時台に起きる帰宅ラッシュだった。働く時間は短い。それなのに、デンマークの1人当たりGDPは日本の約2倍。賃金水準は高く、国際競争力ランキングは世界No.1だ。なぜ、日本とここまで働き方や暮らしぶりが違うのか? 話題の新刊『第3の時間──デンマークで学んだ、短く働き、人生を豊かに変える時間術』から、特別に一部を抜粋して紹介する。
 写真:井上陽子
写真:井上陽子
“三遊間のボールは拾わない”働き方
デンマークの働き方の特徴は、実はデンマーク人よりも、日本の典型的な長時間労働を経験してきた人の方が、うまく説明できたりする。デンマーク人にとっては当たり前であることにも気づけるからだ。
日本の大企業で部下15人を抱える中間管理職だった日本人男性は、デンマークで実践している働き方を、“三遊間のボールは拾わない”働き方だと説明した。
日本にいた頃、ピーク時の残業時間は月約80時間に上っていたが、それは、やれることは全部やろうとしていたからだった、と振り返る。日本では、誰の仕事なのかが曖昧な“三遊間”のボールを拾う人が重宝される一方で、それが残業を増やす要因でもあった。
「考え方を変えれば、それが三遊間である理由は、仕事としての価値が高くないから。価値が高いなら、初めから担当がいるはずですよね。デンマークでは、価値あることのなかでも、時間内でできる最重要なことしかやらない。60~80点ラインを想定して、それ以上はオプションと割り切る。日本ではそこから100点にしようとするから、残業になってしまう」
デンマーク企業のソフトウェアエンジニアとして働くようになって、この男性がやめたことの一つが、「おせっかい」だ。
例えば、他の人が作ったソフトウェアの設計に懸念がある時。これはいずれ問題が起きるな、とわかる時、日本であれば親切心から指摘するところだが、デンマークでそれをやると、他人の仕事に口を出していると受け取られ、面倒な事態に陥る可能性もある。
そもそも労働時間が短いので、自分の仕事で価値を発揮することに集中しないと、あっという間に時間が過ぎてしまう。だから、そういう時は、あえて何も言わないそうだ。
仕事を、「あるといいこと(nice to have)」と、「ないと仕事として成立しないこと(must have)」の二つにシビアに分類し、“あればナイス”の仕事は一切やめた、との説明である。
「やる意味ある?」と問い直すカルチャー
そんな感覚をデンマーク企業で身に付けた日本人たちが、「なぜ日本ではあんなことをしていたのか」と振り返るのは、機能がほぼ変わらないのに製品のモデルチェンジを繰り返すことや、同業他社がやっているという理由で、不毛な過当競争にしのぎを削ること、などなど。大量の人を会議に呼び、長時間拘束したうえに、大したことが決まらない、というのもそうだろう。
経営学の父と呼ばれるピーター・ドラッカーは、「そもそもやる必要のないことを効率的に行うことほど、無駄なことはない」と端的に表現したが、そんな視点で見直せば、「これって、そもそもやる意味ある?」という仕事は、色々とあぶり出せるのではないだろうか。
この作業ってやる意味があるのかな、と思ったとしても、「俺がやれって言うんだからやれ」と上司に言われれば、問答無用で従うのが普通だった時代は、確かにあった(私だってその経験者)。でも、今後、職場で増えてくるZ世代は、なぜそれをやるのか、その仕事にはどういう意味があるのかを重視する傾向がある。単なる上下関係で仕事をやらせることが難しくなればなるほど、仕事の意味を問い直す作業は、ますます大事になってくるように思うのだ。
デンマークでは、人件費が高いからこそ、労働者の側にも、それに見合う価値を出そうという切迫感が生まれる。上司の側も、「部下にこの成果を求めたい。でも、使えるのは週37時間だけ」という意識があるから、割り振る仕事を厳選する。
「かけた時間よりも、仕事の価値」という考えで、どんな肩書の人であっても時間とは貴重なものだという感覚があれば、会議の時間や人数を限定するといったルールを一律で決めずとも、無駄はおのずとなくなっていくはずだ。
短時間労働が理にかなっているという「Why」の部分がしっかりしていれば、各人にとっての最適な「How」を考え出して実践するのは、さほど難しくないのである。
※本記事は、『第3の時間──デンマークで学んだ、短く働き、人生を豊かに変える時間術』を抜粋、再編集したものです。