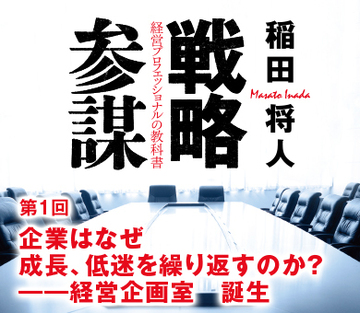「誰がいたんだ?」
「常務の大久保さん」
「大久保さんだったら、お前の屁理屈話は不愉快かもな。なにせ営業の叩き上げの人だから。けど大久保さんって、不愉快だからって、いきなりお前を店から外すような人じゃないだろ?」
「えっと……他にもあとから来て、僕の後ろに立っていた人がいた」
「誰?」
「管理本部の阿久津専務」
「あ……」
と言って沼口の食事の手が止まった。よりによって、あの阿久津専務のいるところで、給与制度について、『べき論』をぶったのか……。
「まずいな、それ」
「阿久津専務、僕が話し終わるまで、ずっと後ろにいたんだと思う。まったく気づかなかったけど。で、僕がいったん話し終わったら、いきなり後ろで拍手しだしてさ、『お前、ええこと言うなあ。よう勉強しとるなあ。大したもんや』だって。振り向いて顔を見たら、目がぜんぜん笑っていなかったけど」
沼口は、もし自分がその場にいたならば、高山の話を何としてでも止めたろうにと思ったが、すぐに、その考えを改めた。こいつが調子に乗って話している時は、それを止めるのは至難の業だから。
「高山。お前、聞いている人たちの視線とか、その場の空気の変化とかに気づかなかったのか?」
今さら聞いても仕方がないとは思いながらも、沼口は尋ねた。
「最初は『そうだ、お前の言う通り。いいぞ』っていう感じで皆、うなずいて聞いてくれてたんだけど」
「だけど?」
「言われてみれば、途中から皆、あんまり僕の顔を見なくなったな。視線も外して、目が泳いでいたような気がする」
「大体お前、いつもそうだ。場の空気に……もっと、気がつけ」
ヘンな日本語、と思いながら高山は再びランチに手を付けはじめた。