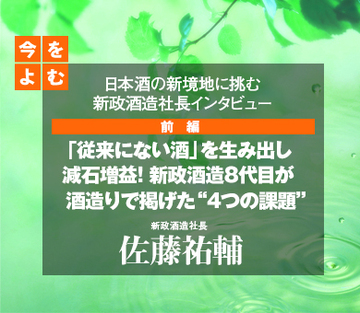東大卒のフリーライターから、約170年の歴史をもつ酒蔵の8代目へ―——。秋田「新政」の佐藤祐輔社長は、31歳だった2007年に蔵に舞い戻った。そして、わずか7年の間に新たな酒をつぎつぎと打ち出して、にわかに注目を集め、赤字だった蔵の経営も減石増益と筋肉質に立て直しつつある。改革断行の背景や、酒造りのポリシーを聞いた前編に続き、業界の先行きや経営観を語ってもらった。
地酒流通が激変するなか
悩ましい販路の選択
――前編で複数の商品ラインナップができてくるまでを伺いました。これだけの製品群を確保されたのは、販路を見直す意味もあったと聞いたのですが。
販路ありきではありませんが、小さな地酒の蔵にとって販路の選択は非常に重要です。
 佐藤祐輔社長 1974年12月生まれ。新政酒造の8代目として秋田県に生まれる。秋田高等学校卒業後、明治大学商学部を1年で中退、東京大学文学部に入学。同学卒業後はフリーのライター/編集者として活動していた。幼少時より家業とは距離を置いていたが、31歳のときたまたま飲んだ「磯自慢 特別本醸造」で日本酒に目覚め、酒類総合研究所の研究生を経て、2007年に新政酒造入社。普通酒主体から純米造りに切り替え、<No.6><やまユ><クリムゾン&ヴィリジアンラベル>など革新的な酒を次々と打ち出して人気を集めている。12年より現任。趣味はヨーグルトなど発酵食品を自家用に作ること。
佐藤祐輔社長 1974年12月生まれ。新政酒造の8代目として秋田県に生まれる。秋田高等学校卒業後、明治大学商学部を1年で中退、東京大学文学部に入学。同学卒業後はフリーのライター/編集者として活動していた。幼少時より家業とは距離を置いていたが、31歳のときたまたま飲んだ「磯自慢 特別本醸造」で日本酒に目覚め、酒類総合研究所の研究生を経て、2007年に新政酒造入社。普通酒主体から純米造りに切り替え、<No.6><やまユ><クリムゾン&ヴィリジアンラベル>など革新的な酒を次々と打ち出して人気を集めている。12年より現任。趣味はヨーグルトなど発酵食品を自家用に作ること。
売れている時代は卸さんにお願いしておけばよかった。私が戻った当時は、普通酒を8割以上地元に卸しているのを主体に、県内外の総合酒類卸会社さん十数軒ともお付き合いがあるという状態でした。
でも、純米造のみの酒蔵に変わった今は、それぞれお客様の顔を想像して味をつくっていますから、お届けしたいお客様に提供できる形にならなければいけません。そういう意味では、卸会社に商品を任せきりにしてはいられなくなりました。
現在、当蔵と取引のある卸会社は、地元の「秋田県酒類卸」さんと、地酒専門の卸会社である「日本名門酒会」さんのみです。また「日本名門酒会」さんとのお取り引きについても、全加盟店のうち、40店ほどの専門店とのみ密接な関係を結んで「No.6」をお取り扱いいただいています。ほかに全国の専門店さん20軒ほどとも、直接の取引をさせていただき、「亜麻猫」をはじめとする実験酒や、「やまユ」といった特殊な小仕込みのお酒をお出ししています。
当蔵はまだ少し手前のところにいますが、地酒流通そのものも、この10年ほどでかなり変化してきているんですよね。
ーーぜひ佐藤社長からご覧になった地酒流通の変遷を教えて下さい。
かつて地酒で先陣を切って卸を通さない直販を推し進められたのが、新潟県・朝日酒造さんの「久保田」ではないでしょうか。久保田会とよばれる特約店を組織して、販売目標を設けると同時に勉強会を開催するなど密接な関係をつくりました。
そののち、山形県・高木酒造さんの「十四代」は、小仕込みということもあって、販路を50~60店程度にしぼりこんで、いわゆる限定流通の方針を打ち出しました。市場価値を価格に転嫁せず、生産量もそれほど増やさなかったため、常に売り切れが続くブランドとなりました。これがいわゆる「幻」銘柄の走りです。
この戦略は、小規模の蔵にとっては真似しやすく、多くの蔵が追随しました。ただし、卓越した品質の高さがあれば人気も出ますが、それは簡単に達成できることではありません。しかも、市場自体の拡大が伴わなければ、年々、競争率が高くなるばかりです。長期的に高い評価を維持している蔵は、ほんのひと握りです。
そこへ、消費者に直接アピールすることで話題をつくり、製造能力を増強して、品質と供給量を極限まで追求して在庫を切らさない、という戦法をとったのが山口・旭酒造さんの「獺祭」です。度胸が試される戦略ですが、地酒流通に与えたインパクトは強烈でした。この成功を見て、そうか、今まではストイックな意識が強すぎて、むしろ市場を縮小させる方向性での酒造りや経営しかできていなかったのではないだろうか、と同様のスタイルを追求する蔵がまたいろいろ出てきています。