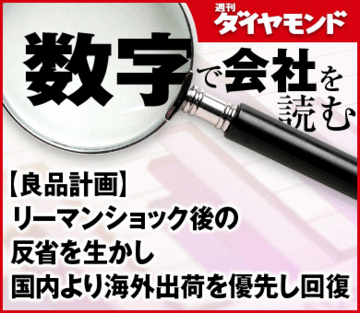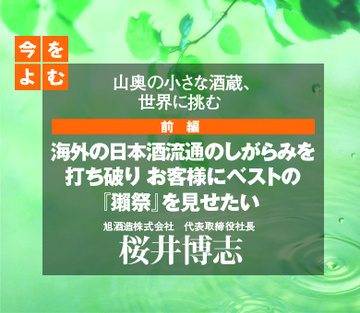一時は深刻な経営危機に瀕しながら、起死回生を図って東京に進出し、ひたすら日本酒の本質を追求して純米大吟醸<獺祭>を世に送り出した旭酒造。その「余計なモノをそぎ落として、シンプルで良質な酒を造る」というコンセプトを決めた際、当時、新進ブランドとして注目を集めていた無印良品を参考にしたそうです。そこで今回は、旭酒造の桜井博志社長が、無印良品を世界に展開する良品計画の松井忠三会長に、ブレないコンセプトづくりや、それを商品や販売という形であらわすオペレーションの仕組み作りなどについて聞いた、対談前編です。
日本の消費市場が大きく変わる
過渡期に産声を上げた無印良品
桜井 私が先代から旭酒造を引き継いだのは1984年で、当時は普通酒を造る山口県岩国市内でもしんがりに甘んじている酒蔵にすぎませんでしたし、焼酎ブームに圧倒されて日本酒市場自体が縮小していました。
そこで、純米大吟醸造りを始めて、背水の陣で1990年頃から東京進出に活路を求めたわけですが、ちょうどその頃に無印良品が注目を集め始め、瞬く間に消費者の心をつかんでいった印象が強く脳裏に焼き付いています。<獺祭>開発のコンセプトを考えるうえで、「シンプルなパッケージでありながら中身が良質」という無印良品を、勝手ながら(笑)随分参考にさせてもらいました。
 松井忠三(まつい・ただみつ)1949年、静岡県生まれ。株式会社良品計画会長。73年、東京教育大学(現・筑波大学)体育学部卒業後、西友ストアー(現・西友)入社。92年良品計画へ。総務人事部長、無印良品事業部長を経て、2001年に社長就任。赤字状態の組織を「仕組み」の見直しをテコに改革し、業績はV字回復を遂げた。現在も、組織の「仕組みづくり」を継続している。08年より現職。著書に『無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい』(角川書店、2013年)。
松井忠三(まつい・ただみつ)1949年、静岡県生まれ。株式会社良品計画会長。73年、東京教育大学(現・筑波大学)体育学部卒業後、西友ストアー(現・西友)入社。92年良品計画へ。総務人事部長、無印良品事業部長を経て、2001年に社長就任。赤字状態の組織を「仕組み」の見直しをテコに改革し、業績はV字回復を遂げた。現在も、組織の「仕組みづくり」を継続している。08年より現職。著書に『無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい』(角川書店、2013年)。
松井 確かに、旭酒造さんが東京に進出された時期と近いですね。1980年、当時はセゾングループの傘下にあった西友のプライベート・ブランド(PB)として、無印良品は誕生しました。その基本コンセプトは、大手メーカーによる既存のナショナル・ブランドに対するアンチテーゼ(真逆の主張)で、当初は「わけあって、安い」というキャッチコピーを用いてその点を訴求しました。
原点にあったのは日本の禅や茶道の精神です。飾り気がない状態にとことん削ぎ落として簡素化し、その結果として最後に残る価値を表現したいと考えたのです。極めて清楚な、(セゾングループの創業者である)堤清二さんの言を借りれば「ピューリタン」なイメージでした。
周知の通り、バブル経済を迎えていく局面では、「最高にいいモノがほしい」という志向のもと、多くの消費者がルイ・ヴィトンやシャネルといった高級ブランド品を持つことで他人との差別化を追求したものです。しかし、その次に訪れたのは、個々の感性や価値観に基づいて商品が選ばれる時代で、「他人とは違うモノを手に入れたい。本当に価値のあるモノを持ちたい」というニーズが次第に強まっていきました。そんなふうに日本の消費市場が大きく変わっていく過渡期に、無印良品は登場したわけです。
桜井 私たちの<獺祭 磨き二割三分>も米の真の旨みだけを抽出するために、精米歩合23%まで磨いて造り上げたのですが、無印良品の商品開発の姿勢にならうところがあったと思います。
松井 いや、恐縮です。
我々のコンセプトは世の中に広く受け入れられ、1983年にセゾンや西武色を一切廃して「無印良品」の路面店を東京・青山にオープンさせたところ、1年分の予算を1ヵ月で達成するほど商品が飛ぶように売れました。これは商売になる!ということで、1985年には西友の中の事業部のひとつに昇格し、将来の分社・独立も見据えた戦略を練っていくことになりました。実際に1989年には独立を果たし、その翌年には西友から営業権も譲り受けております。振り返れば、最初の10年間は前期比約30%増という増収増益が続きました。