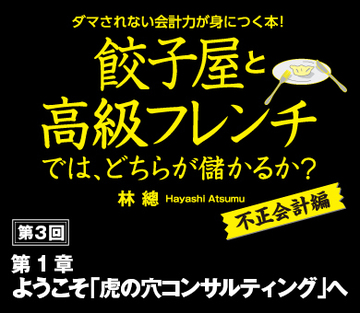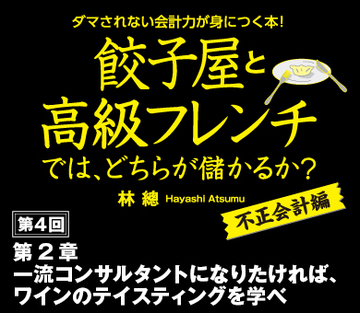会社の香りを嗅ぐ
そこにソムリエがやってきて、安曇のグラスにシャトー・ラトゥールを注いだ。安曇はグラスをくるくると回して、グラスを鼻に近づけた。
「『外観』で不足する情報を補うのが、『香り』の観察だ。臭覚という繊細なセンサーを働かせるのだ。君の仕事でいえば、それまでに収集した情報から仮説を立て、会社の担当者に直接質問する作業だ。そして、回答に全神経を集中させる。その過程で、会社が抱える課題を、慎重に、思慮深く、えぐり出す。コンサルティングで一番大切なのは、この『香り』のステップといっていい」
安曇は青カビのチーズを手でつまんで、ポイッと口に入れた。
「ボクたちの嗅覚のすごさを知っているかな。何百種類もの香りや臭いを嗅ぎ分けることができるんだ。その意味で、味覚とは次元が違うと言っていい。コンサルも同じでね。会社に行って自分の目で現場を確認し、責任者から直接話を聞くことができれば、決算書から得られなかった膨大な情報を集めることができるんだよ」
ヒカリは濃い黒みがかった赤色の液体が入ったワイングラスを持ち上げて、鼻に近づけた。すると不思議なことに、さっきは感じなかったさまざまな香りが次々と、ヒカリの臭覚を刺激した。それは、カシスソーダのようでもあるし、カカオのようでもあった。
「では『味わい』の説明をしよう。テイスティングでは口の中全体を使って、ワインのすべてを味わい、分析し、評価する作業だ」
安曇はラトゥールを口に含むと、目をうっとりさせ目を閉じた。
「さすが五大シャトーだ。ブラックベリー、カシス、チョコレート、タバコ、それから何百もの香りと味が混じり合っている。この絶妙な渋味と酸味、濃厚にして繊細な舌触りはまるで最高級のビロードのようだ。君にこの素晴らしさがわからないのは、誠に残念というしかない。経験を積まなくては、この幸せは味わえない」
安曇は、もう一口飲んでこう続けた。
「まっ、コンサルも同じだがね」