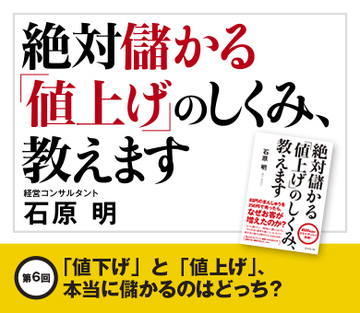焼肉店を立て直せ!
「もともとうちの社員だった宇佐美君という男がいてな。彼は今39歳なんだが、焼肉店を4店舗やっているんだ。名前は『味樹園(みきえん)』という。
焼肉業界は狂牛病以来、何かと外的要因が多くてな、ユッケによる食中毒問題、生レバーの提供禁止など、消費者の焼肉離れに拍車をかける問題が立て続けに起こってしまった。随分景気が良くなったとは言っても中にはそこから立ち直れていないお店があるのも現実だ。
ちなみに焼肉業界が何度となくそういった状況に陥ってしまったというのは2人とも理解しているよな?」
「もちろん。私、ユッケ大好きだもん……」
あすみは子どものころから大の焼肉好きで中でもユッケが大好きだっただけに、昌一郎の話を聞いて心底落ち込んだ表情を浮かべた。
「私はレバ刺しが食べられなくなったのが悔しい」
はるかはそう言うと、ため息を漏らした。
「まあ、そういう状況で、宇佐美君のところもまだ業績的に立ち直れてないんだ」
「わかった。私はその『味樹園』の業績を伸ばしてくればいいってことだね?」
「そうだ。やれるか?」
「だからぁ……やれるかどうかじゃなくて、やるから大丈夫」
「はるか~」
「だからさ、パパ、もうそのくだりはいいって」
あすみが冷たい目で昌一郎を見た。
「コホン。ま、そういうことだ。じゃ、いつもの感じでまずは2人でストコン(店舗視察・店舗比較)に行って来なさい。それから改善プランを立ててパパにレビュー。それから、乗り込む」
「OK! 任せといて。はるか、“ピン試験”頑張ります!」
はるかは昌一郎とあすみにいつもの敬礼のポーズを取った。
「ち・な・み・に……私、もしこの“ピン試験”に落ちて社員になれなかったとしても、どこにも就職しないから。『鮪馳』でバイトしながらいずれは必ずK’sの社員になるし。それだけは理解しといてよね。昌ちゃん」
「はるか~ 昌ちゃんマジで嬉しいよ~」
「とにかくガチでやってくるから。任せといてよ!」
「頑張れ、はるか! その調子だ。期待してるぞ!」
「はるか、頑張って。私もバックアップするからね」
「いやいや、今回は大丈夫。私1人でやるから。ね、昌ちゃん」
「そうだな。あすみは今回手出ししないようにしてくれよ」
「は~い、わかりました。ちょっと寂しいけど……ま、はるかの勝負だもんね」
「うん。私、本気でやってくるよ。とりあえずストコンは付き合ってね。日程、決めよう」
その時、満園が声をかけた。
「社長、お客様がいらっしゃいましたが……」
「おう、そうか。今日のミーティングはここまでだな。はるか、頑張れよ」
初めてのピンでのミッション。はるかは高鳴る緊張感に、背筋がピンとなるような感覚を覚えた。