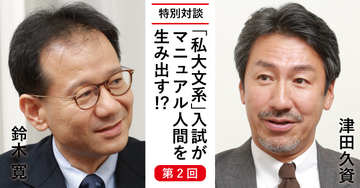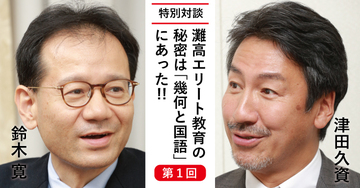【津田】だから僕は、日本人というのはどこかで「外国語を学ぶように日本語を学ぶ機会」が必要なんじゃないかなと思っているくらいです。
【鈴木】そうですね、論理日本語を学ぶ機会というのは必要かもしれません。
【津田】まず「単語の意味」を徹底的につかむ必要があるし、さらには暗唱してしまうくらい「ちゃんとした文章」を読まないといけない。
【鈴木】読んだだけでは頭に入らないという人もいるでしょうから、何度も何度も精読することです。1人でやっていては大変なら読書会をやるのもいいでしょうね。
本当の学びには「縦」だけでなく
「横・斜め」が必要
【鈴木】原理原則をしっかりつかむ方法として、もう1つ考えられるのは、教えることです。ラーニングピラミッド(学習ピラミッド)によれば、知識を定着させるうえでは「人に教える」のが一番なんです。
【津田】本当にわかってないと誰かに教えられませんし、わかりやすく教えるには「言葉」の力が求められますからね。
【鈴木】たとえば私は、東大と慶應でも教鞭をとっているんですが、ゼミの学生たちが「教え合う」ように仕向けています。思えば「精力善用 自他共栄」の精神が行き届いた灘高にも「教える」文化がありましたよね。
受験のときも個人技というよりは団体戦を戦っているようなイメージ。受験生同士が得意科目を教え合っていました。
【津田】成績上位の人はもう「受かる」ってわかっているから、余裕があるんだと思いますが(笑)。

【鈴木】あと、教えられる側にとっても、仲間から教わったほうが、わかりやすかったりするんです。
先生たちはもう何十年も前に理解したことを教えているわけだから、そもそも自分がどうやって理解したのかという「プロセス」を忘却してしまっているんですよ。
一方、同級生というのは、つい1カ月前くらいに理解したばかりだったりするから、理解までのプロセスをビビッドに覚えている。「このルートをたどり、この瞬間に自分はわかった」という体験が頭の中に残っているから、先生よりもうまく教えられることがある。
【津田】なるほど、それはとても説得力がありますね。それにしても、「先生が教えない教育」というのは、ある意味では究極ですよね。
【鈴木】「先生が教えずに生徒たちに考えさせる、教え合わせる」というのはハーバードなんかも一緒だと思います。灘高に追いつこうと頑張っている学校がなかなかうまくいかないのは、先生たちが一生懸命「教えよう、教えよう」と努力してしまっているからかもしれませんね。
私もゼミを設計するときには、「縦の学び」「横の学び」「斜めの学び」のバランスを気にするようにしています。同級生間の横の学び、先輩後輩の斜めの学びをうまくかみ合わせれば、本来、縦の学び(先生・学生の学び)はゆるいほうが、学生は伸びるんですよ。
【津田】なるほど。
【鈴木】灘はやっぱり横の学び、斜めの学びがよかった。先生が教えない教育。そうすると自主的に考えますから。でもこれには、どうしても教員のほうに我慢がいるんです。
【津田】普通の先生は教えたくなっちゃうでしょうね。