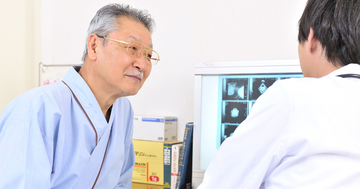がん診療、研究を実施する国公立病院など32施設が加盟する全国がん(成人病)センター協議会(全がん協)が28種類のがんの10年生存率を公表した。
1999~2002年に診断と治療を受けた約3万5000例のデータで、これだけ大規模な情報公開はわが国では初めて。
それによると、全臓器・全ステージ(病期)の10年生存率は58.2%だった。臓器別では甲状腺がんの90.9%に続き、前立腺がん84.4%、子宮体がん83.1%、乳がん80.4%と続く。
このところ増加傾向の大腸がんの10年生存率は69.8%、がん死因トップの肺がんはぐっと下がって33.2%、ワースト1位は膵がんの4.9%だった。
データを利用する際は、全病期を丸めた生存率を鵜呑みにするのではなく、病期別のデータを参考にする必要がある。病期が1期の「早期」と4期の「進行・末期」とでは条件が違い過ぎるからだ。
実際に経過途中の5年生存率を見ると、前立腺がんの場合1~3期は100%だが、4期では5年生存率でも54.5%まで下がる。
前立腺がんは治療の選択肢が多いこともあり、他の臓器や骨への転移が深刻ではない限り「手を替え、品を替え」余命を引き延ばすことが可能だ。言い換えれば「転移」を抑える長期戦に耐える覚悟が必要だということ。
一方、肺がんの5年生存率は、全病期を通じて39.5%。1期は77.9%と8割近いが、4期になると5.6%と衝撃的な数値が出てくる。しかも病期が進むほど治療開始1、2年目の生存率ががくっと落ちる。早期発見の重要性は言うまでもないが、短期決戦で濃厚な治療を覚悟すべきだろう。
逆に女性の乳がんは10年生存率でも8割以上と高いが、ジワジワと低下し続けるのが特徴。一般に治癒の目安といわれる5年を過ぎても再発・転移の可能性があり、10年、20年はがんと付き合う心構えと経済計画が必要だ。
なにせ、2人に1人ががんにかかる時代。このデータはいたずらに余命に怯えるのではなく、がん発症を織り込んだ生活設計を立てる際の参考にしたい。
(取材・構成/医学ライター・井手ゆきえ)