記事検索
「数学」の検索結果:2321-2340/2844件
第44回
「私大文系」入試がマニュアル人間を生み出す!?――鈴木寛×津田久資対談【第2回】
「スズカン」こと鈴木寛・文部科学大臣補佐官との対談をお送りする。じつは「灘中→灘高→東大法学部」の先輩・後輩関係にあるという2人。教育改革のプロフェッショナル・鈴木寛氏と、ビジネス教育のスペシャリスト・津田久資氏のトークは「大学入試」や「ビジネススクール」の問題へと展開していく……。(第2回/全3回)
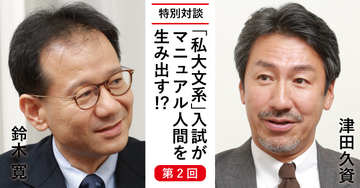
第43回
灘高エリート教育の秘密は「幾何と国語」にあった!!――鈴木寛×津田久資対談【第1回】
「スズカン」こと鈴木寛・文部科学大臣補佐官との対談をお送りする。教育改革のプロフェッショナル・鈴木寛氏と、ビジネス教育のスペシャリスト・津田久資氏による「灘・東大」トークは、どんな広がりを見せるのか?(第1回/全3回)
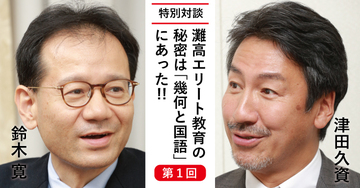
第135回
お札を刷って国の借金を帳消しにできるか。これはある程度は可能である。政府紙幣の発行と量的緩和は、効果の面ではほぼ同じだ。バランスシートという観点から、それらのメリットとデメリットを見てみよう。

第11回
優先度の高いものから暗記していく最強の勉強法
覚えても忘れてしまっては意味がない。さらに、知識として使えないのであれば、ただの徒労である。15万部超の『読んだら忘れない読書術』著者の樺沢紫苑さんを迎え、最強の勉強法について語ります。
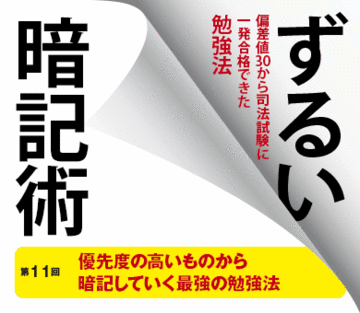
第10回
覚えた「情報」を自分の「知識」に変える忘れない技術
覚えても忘れてしまっては意味がない。さらに、知識として使えないのであれば、ただの徒労である。15万部超の『読んだら忘れない読書術』著者の樺沢紫苑さんを迎え、情報を知識につなげる方法について語ります。
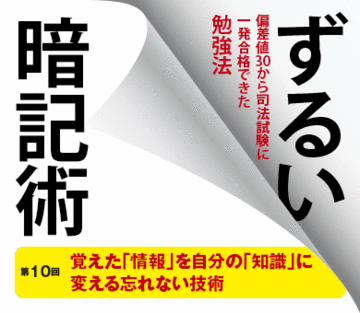
第39回
ハーバードMBAはなぜ「講義をやらない」のか?
「『これまでいかに自分が何も考えていなかったか』を痛感しました」——去る10月26日に開催され、大好評を博した津田久資氏『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか』スペシャル著者セミナー。即座に100名を超える参加希望者が殺到し、当日には熱気あふれる満席の会場から活発な質問が飛び交った。セミナーの様子を少しだけご紹介!!(第1回/全4回)
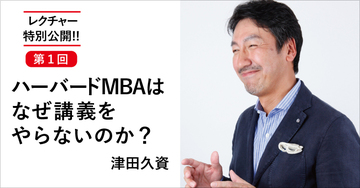
第37回
「700個のケーキ」を「800人の避難民」に届ける方法を考える
「ミスターリクルート」藤原和博さんと、独自の「思考法・発想法」が話題の津田久資さんが対談!! お互いの最新刊を読んできた2人の議論はますます白熱!「リクルートがなければ、東大からBCGに入社していたかも…」と語る藤原さんは『あの人はなぜ、東大卒…』をどう読んだのか?
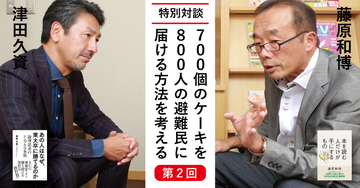
第18回
私たちは毎日、無数の決断をしています。優れた決断の根底には優れた判断judgment)があるわけですが、すでにある選択肢の中から合理的に決めること(decision)とは異なり、判断には選択肢自体を考える知恵が必要です。チームリーダーとなれば、日々判断を求められる場面に遭遇します。その際、「自問自答すべき問い」を今回から解説していきます。この問いを繰り返し考え、実践することによって、将来、賢慮のリーダーとなる能力が磨かれることでしょう。
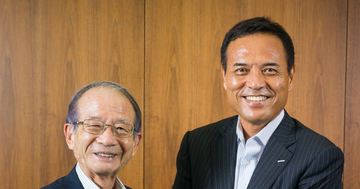
第2回
アメリカを二分した「モンティ・ホール問題」をベイズ統計学で推定する
画像解析などの最先端技術に使われる「ベイズ統計学」の考え方をやさしく解説します。第2回は、かつてアメリカ全土を巻き込んだ有名な論争「モンティ・ホール問題」を題材に、ベイズ統計学の重要な性質を紹介しましょう。
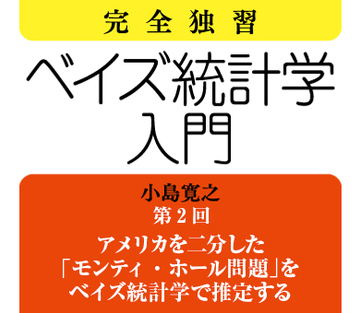
第2回
「ドラッカーにも読ませたい!」上田氏が絶賛する『もしイノ』の内容とは?
280万部のベストセラー『もしドラ』第2弾がついに発売。著者の岩崎夏海氏と、ドラッカーの「日本での分身」と言われる上田惇生氏が語り合う、刊行記念対談。上田氏から「ドラッカーに読ませたい!」と言われた新作の内容とは?

第403回
若年層への投資教育に力が入れられ始めている。だが、投資教育が真に必要なのは、高齢者世代ではないか。彼らはお金を持ち、また判断力が甘くなるがゆえに狙われている。それを放置するのは不適切であり、不健全だ。

第1回
ガン検査が「陽性」でも気に病む必要はない?――「ベイズ統計学」の推定のしくみ
検索エンジンの予測変換機能などに使われる「ベイズ統計学」。そのしくみを、中学数学さえ忘れてしまっても理解できるようにエッセンスを凝縮して解説します。第1回は、「ガン検査」を題材にして、「ベイズ統計学の重要な性質を紹介。
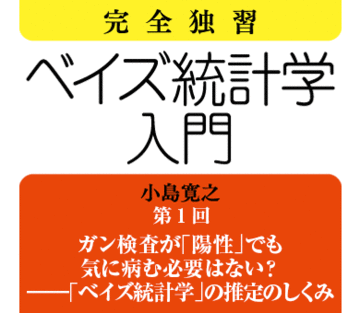
第10回
経済学と現代アートの底流にある共通点
超長期的な視点で経済を分析した『なぜ今、私たちは未来をこれほど不安に感じるのか?』の著者・松村嘉浩氏と、世界的なアーティストを複数擁するミヅマアートギャラリーを主宰する三潴末雄氏。異色の対談が、一見全く関係のない“経済学や金融”と“現代アート”の共通点を明らかにします。
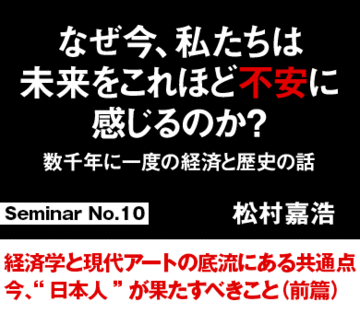
第8回
記憶力を最大化するために必要な2つのコツ
ただやみくもに知識を詰め込むことが、勉強ではない。正しい勉強法を知っているのと知らないとでは、勉強の成果は一目瞭然。『出口汪の「最強!」の記憶術』がロングセラー、”受験の神様”ともいわれている出口汪さんを迎え、一生使える勉強法について語ります。
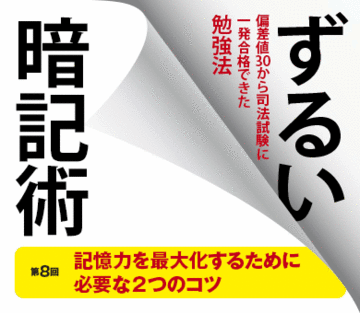
第26回
「東大卒・元マッキンゼー」の芸人だけど何か質問ある?(中)
早くも第3刷が決定し、1ヵ月以上にわたりオンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで第1位に輝き続けている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。本書の主題である「思考型人材」のモデルとして、元BCGの津田久資氏は当初から「いくつかの職業」をイメージしていた。その1つが「お笑い芸人」である。そこで今回、東大卒→元マッキンゼーという「異色のキャリア」を持つお笑い芸人・石井てる美氏と津田氏による対談を企画。マッキンゼーで身につけた思考法は「笑い」にどうつながるのか? ビジネス界とお笑い界の意外な共通点が見えてきた。異色の組み合わせによる対談、第2回!!

第24回
「”WHY?”をもっと!」情報の鵜呑みを防ぐ方法
ここ1ヵ月、オンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで売れ行き第1位を獲得し続け、早くも第3刷が決定した『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。前回までの連載では、「情報収集」の技術について見てきたが、そもそも情報を集めただけでは、競合に打ち勝つためのアイデアは出てこない。頭の中の情報素材を「知恵」へと加工するには何が必要なのだろうか?

第32回
「私なんか中卒だったから、国語でも数学でも社会科でも、わからないことがいっぱいあるんですよ。だから、勉強するだけですごいなあと思うし、だから、俳句でいろんな勉強をしたあとの飲み会が楽しいんです」

第12回
文章力とメディアリテラシーは自分で試行錯誤しないと育たない
LINE株式会社・上級執行役員 法人ビジネス担当である田端信太郎氏をゲストに迎えたシリーズの最終回です。『広告やメディアで人を動かそうとするのは、もうあきらめなさい。』などの著作も持つ田端氏と、外資系投資銀行の社員から作家に転身した藤沢氏の文章とメディアへの思想に迫ります。
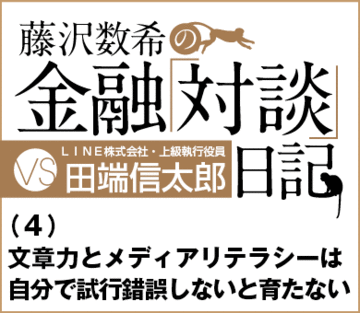
第25回
2014年4月、母親と二人で生活保護を利用して生活していた福島市の女子高校生が、奨学金を全額返還するよう求められた。しかし2015年8月、厚労省は市の決定を不当とする裁決を下した。そんな渦中にある女子高生は、どんな生活を送っているのか。

第27回
会話の中に数を入れると、数字に強い子になる――カヨ子ばあちゃんの子育て日めくり27
83歳になった「脳科学おばあちゃん」が、自身初の『カヨ子ばあちゃんの子育て日めくり』を出版! 読むだけでパパ・ママがホッとしながら、子どもの脳が活性化する「カヨ子ばあちゃん31の金言」を紹介する。
