記事検索
「PwCコンサルティング」の検索結果:181-200/207件
第1回
多くの企業が環境変化に対応すべく、新規事業開発などに新たな活路を見出そうとしている。しかし、長年の取り組みにもかかわらず、期待した成果を出せず苦戦するケースも多い。本連載では全6回にわたり、部品メーカーの方々にもわかりやすい形で、新規事業による未来創造を進めていく方法を紹介していきたい。

日本企業においても、デジタルトランスフォーメーションが喫緊の課題となるなかで、これをけん引するCDO(Chief Digital Officer、最高デジタル責任者/Chief Data Officer、最高データ責任者)という役職が注目を集めている。CDOのためのコミュニティ組織を目指して創設されたCDO CLUB JAPANの代表理事&CEO、加茂純氏に日本企業におけるCDOと専門組織の現状と課題、欧米の先進事例などについて語ってもらった。

今後その必要性がさらに高まると考えられる「健康経営」に対し、本連載で取り上げてきた「ピープルアナリティクス」をどのように活用できるのか。その可能性について述べる。

第2回
アマゾンはなぜ最強なのか。破壊者に共通する最強の思考法
歴史上の破壊者には、ある共通した考え方がある。競争優位をポジショニングや強みに求めず、どこまでも顧客の立場で考えるということ。新旧激突時代に、破壊されずに生き残るには、どのような考え方が必要か?

【特別対談】BoxとマイクロソフトAzureの連携で「働き方」はどう変わるのか
日本企業の働き方に関するさまざまな課題に応えるべく、クラウド型コンテンツ管理プラットフォームのBoxとマイクロソフトが連携を強化している。その狙いはどこにあるのか? Box Japanの古市克典代表取締役社長と、マイクロソフトの高橋美波執行役員 常務 パートナー事業本部長が語った。

今日では、国内企業による海外市場への進出が加速し、ビジネスのグローバル化がますます進んでいる。そうした中、海外の有力企業の買収など、積極的なM&A戦略を展開する企業も増加。それに伴い、それら被買収企業を含む海外拠点の財務状況などの情報をいかに正確かつタイムリーに把握し、グローバル全体でのビジネスを適正にマネジメントしていくかが、企業にとっての重要な課題として浮上している状況だ。経営戦略の策定から業務改革、およびITシステムによるその実行に至る総合的なコンサルティングサービスを展開するPwCコンサルティング合同会社にあって、金融領域の顧客支援に当たる押谷茂典氏と、日本オラクルの桐生卓氏の対談により、その課題解消に向けたアプローチを検証する。

第7回
企業はどのように持続的な成長に向けた準備を進めていけばよいのだろうか。そのカギとなるキーワードが「Fit for Growth」である。これまで多くの企業で行われてきた、企業を収縮させるだけの単純なコスト削減ではなく、企業をより強くする戦略的なコスト削減を行ったうえで、捻出された資金を企業の未来へ投資することが重要となる。

今日では幅広い業種、多様な規模の日本企業が、グローバル市場でのビジネスを志向し、それに向けた取り組みが加速している状況だ。そうした中で重要なテーマとなるのが、グローバル規模での経営管理にかかわるガバナンスを、いかに担保していくかという問題だ。そこでは統一化されたシステムの各拠点への適用や、業務プロセス、各種経営指標の標準化などが不可欠である。そうした取り組みの実践において、企業が直面する課題や、その解消に向けたアプローチについて、コンサルティングファームとして多くの国内企業のグローバル展開を支援してきたクニエの勝俣利光氏と日本オラクルの桐生卓氏が語り合った。

第9回
『ブロックチェーン・レボリューション』で予言されたICOの現在(後篇)
世界的ベストセラー、『ブロックチェーン・レボリューション』で予言された数々の変革が日本でも起こり始めた。なかでも大きなインパクトが予想されるのが、ICOというこれまでにない資金調達手法だ。同書の翻訳協力者でもある勝木健太氏に最新情報を整理してもらった記事の後篇。

第8回
『ブロックチェーン・レボリューション』で予言されたICOの現在(前篇)
世界的ベストセラー、『ブロックチェーン・レボリューション』で予言された数々の変革が日本でも起こり始めた。なかでも大きなインパクトが予想されるのが、ICOというこれまでにない資金調達手法だ。同書の翻訳協力者でもある勝木健太氏に最新情報を整理してもらった。

第5回
セプテーニ・ホールディングスは、事業の競争力に直結する人的資産を恒常的に高めるために「人的資産研究所(Human Capital Lab)」を2011年に設立。ピープルアナリティクスに関する研究と社内向けのサービス開発に取り組んできた。本取組みを牽引した同社取締役グループ上席執行役員の上野勇氏に聞いた。

第7回
音楽ビジネスにおけるデジタル革命音楽が水や電気のようになるメリットとデメリット
「デジタル変革期における音楽ビジネス」をテーマに、メディア戦略コンサルタントの松永エリック・匡史さんが“4人目のY.M.O(イエロー・マジック・オーケストラ)”としても知られるシンセサイザープログラマーの松武秀樹さんと、音楽ビジネスにおけるビジネス革命のリアルについて議論した内容をダイジェストでお届けします。

第2回
GDPR施行まで1年弱、いまからでも対策は可能である。ただししプロジェクトは経営者がリーダーシップを執り、リスク管理や法務だけでなく、経営企画、IT、総務人事、営業・マーケティング等、あらゆる部門も巻き込んで推進することが重要である。

第6回
音楽ビジネスにおけるデジタル革命音楽を変えた「楽譜」というイノベーション
デヴィッド・ボウイは2002年のインタビューで「音楽が水や電気のようになる日が来る」と現代を見通していたかのように語っていました。本記事では「デジタル変革期における音楽ビジネス」をテーマに、ギタリストでデジタル事業のパイオニアでありメディア戦略コンサルタントの松永エリック・匡史さんが、音楽発展の歴史を振り返ります。

第4回
日本最大級の人事向けポータルサイト「HRプロ」を運営するProFuture株式会社代表取締役であり、HR総研所長を務める寺澤康介氏に、日本国内におけるピープルアナリティクスの動向について聞いた。
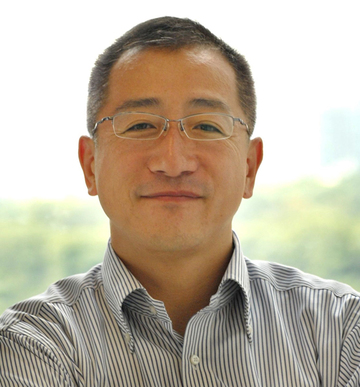
第1回
GDPR(EU一般データ保護規則)は、遠いヨーロッパのことだから日本の本社には関係ないという誤解もいまだに散見されるが、違反時に高額な制裁金が課される可能性があり、財務的なインパクトや評判リスクの大きさは計り知れない。また、ライバル企業の訴訟戦略に巻き込まれるリスクもあり、対応の遅れは命取りになる。

第6回
企業は変化が激しい市場に合わせ、統合された需給コントロールを実施する必要がある。サプライチェーンの個別機能の最適化だけではなく、他部門を含めて全体最適を目指した構造改革が必要となっている。この構造改革をどのように実現していけばいいのか。

第3回
日立製作所では、以前から人事領域におけるデータ分析に着目しており、2016年には自社における新卒採用にピープルアナリティクスの考え方を取り入れた。今回は、実際の取り組みの概要から、得られた効果、苦労話に至るまで、本取り組みを牽引した人財企画部 タレントマネジメントグループの中村亮一氏に話を聞いた。

第5回
国際化、多極化を進めている企業はグローバルサプライチェーンのリスクにどう向き合うべきか。価格変動(原料、為替、エネルギー)はある程度統制可能なリスクだが、自然災害や地政学リスクへの対応は難しい。日本企業の課題、(1)テクノロジーを活用したグローバルリスクマネジメントと、(2)数値管理に基づく経営戦略との連携の2つについて考えてみる。

第4回
昨今、企業の中期経営計画や年度計画には必ずといっていいほど「コスト削減」「最適化」といった表現が見受けられる。特に間接材コスト(一般的に、販管費)については経営側も現場側も普段の注目度が低く、現場も方法がわからずに混乱する。このような状況を打破するためには「2つの城門」を突破する必要がある。
