保田隆明
第16回
法務省が第三者割当を規制する方向で動いている。第三者割当は手間暇コストのかからない資金調達手段だが、既存株主をないがしろにするケースも見られる。しかしそこまで市場から評判が悪い理由は何なのだろうか?

第15回
豊富な資金を元に日本企業が買収攻勢に打って出ている。報道のされ方を見ていると、日本企業万歳論のトーンがたぶんに出ているように感じるが、もっと疑問や懸念を表明する意見があってはいいのではないだろうか。

第14回
景気悪化の局面では、なるべく多くの事業を抱えて、1つの事業のマイナスを他で補えるようにしたいと考える経営者が増えると思われる。では、どういう状態の多角化経営なら株式市場から評価されるのだろうか。

第13回
先日北京に出張した時、「北京の人たちはとにかくよく勉強する」という話を聞いた。学ぶことの貪欲さに関しては日本よりも高いそうだ。中国ではむしろ大卒よりも大学院卒が当たり前の時代が来ているという。

第12回
いま世界で起きている金融危機がいつまで続くのか?その処方箋は?となると、皆目見当がつかない。最近はこのような質問をされることを嫌がる専門家も少なくないようである。「答えが分からないから」だそうだ。

第11回
経済報道の中で当たり前のように使われる「株価と為替の値動きは連動する」といったコメント。しかし統計的に分析する手法を身に付けると、それらがいかに曖昧で説得力に欠けるかを認識することとなる。

第10回
株式投資家が株式に投資をする際、国債よりどの程度高いリターンを要求するか?その数値を「マーケットリクスプレミアム」と呼ぶ。これは企業価値算出の際に重要となる。

第9回
JR東海の株式への投資を検討する投資家の多くは、JR東日本との比較検討を行なうはず。今回の「呼値変更」は両社銘柄への株式投資をよりフェアな形で比較検討できることになる。

第8回
先日受けた「ファイナンスのための数学基礎」の授業でのこと。基礎を学んだり、誰かに教える場合の効果的な方法について大いに教えられた。苦手意識を克服し、理解度を高めるための工夫が随所になされていたからだ。

第7回
最近、航空会社は従来のエコノミークラスのシートよりも少しスペースの広い「プレミアムエコノミーシート」を導入しつつある。しかし、なぜ今までこのプレミアムエコノミーシートがなかったのであろうか?

第6回
日本で上場第1号の「伊藤園優先株」が普通株の株価を下回っている。本来なら、配当額の高い優先株が普通株を上回ってもよさそうなものである。その理由を先日大学院の授業でディスカッションする機会があった。
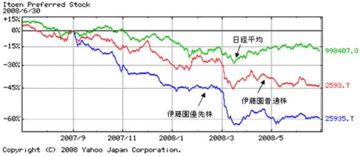
第5回
社外監査役が経営陣に“物言い”をつけるケースがちらほらと出始めている。だが、反乱ばかりがクローズアップされると、監査役制度の形骸化がますます進む恐れもある。

第4回
社会人大学院生が増えている。その背景には、本質を考える場としての大学院の価値の認識向上がある。社会人は変わり、大学院も大きく変わった。次に変わらなければならないのは、それらを有効活用すべき企業である。

第3回
株主総会の時期が近づくと、話題になるのが委任状争奪戦。勝利のためには、マスメディアを通じたメッセージ発信が効果的といわれる。だが会社法の授業では、その手法は法的にグレーとの解釈もあると教えられた。

第2回
4月最終週の日経ヴェリタスの巻頭特集はソニーの復活であった。その記事を読んで最初に思ったことは、「もしやコングロマリットプレミアムの議論が再燃するのか?」である。

第1回
私は4月より公共政策とファイナンスを学ぶために大学院に通い始めた。それを伝えた時に多くの人は「なぜ必要なの?だって金融とか詳しいじゃない?」という反応がほとんどだった。

最終回
東芝グループから独立し、更なる成長のための「攻め」のMBOを果たしたコバレントマテリアル(旧:東芝セラミックス)。その香山社長にその経緯と狙いを伺った。今回はその【後編】である。

第8回
東芝グループから独立を果たしたコバレントマテリアル(旧:東芝セラミックス)は、業績が好調な中、更なる成長を目指してわざわざ自らMBOという選択肢を取った企業である。

第7回
日本のファンドビジネスの草分け的存在であるMKSパートナーズの松木伸男代表取締役に、日本のファンドビジネスの変遷とその特徴についてお話を伺った。今回はその【後編】です。

第6回
日本のファンドビジネスの草分け的存在であるMKSパートナーズの松木伸男代表取締役に、日本のファンドビジネスの変遷とその特徴についてお話を伺った。今回から2回にわたって掲載する。
