保田隆明
第3回
集計屋さんの延長線上では、ベンチャーのCFOは務まらない
社長やCEO、CFOになるまでの人は、実際にどのように会計やファイナンスを使っているのか、あるいは勉強をしてきたのかは意外と知られていないものです。この連載では一般社員がなかなか知ることのない、経営者と会計&ファイナンスの関係性に迫ります。
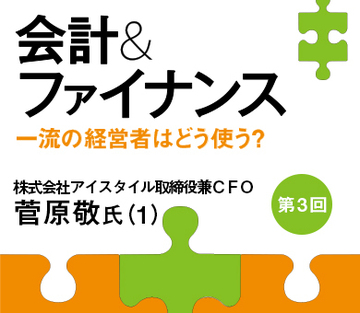
第9回
見た映画、読んだ本、会った人に感化されて何かの行動を取ることは誰にでもある。時にはそれが人生を大きく左右するような大決断にもつながる。もちろん、転職や就活も含まれる。
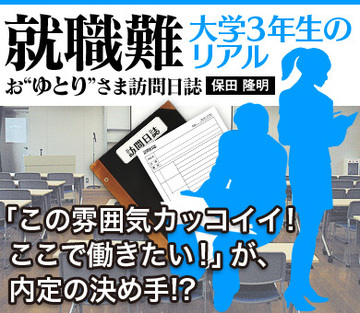
第8回
そもそも学生に限らず、日本では地方対首都圏での対立軸でものごとが語られることが多い。そして、地方の人たち(学生を含む)は「東京はスゴイ」という色眼鏡をかけさせられている可能性が高い。
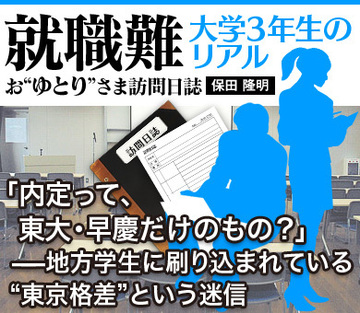
第7回
学生が仕上げてきたES、エントリーシート。ざっと目を通すと、記入スペースの小さなある質問項目のところで目が止まった。「専攻内容を教えて下さい」。一見、スルーしてしまいがちな小さなスペースだが、黙っていられずケチをつけてしまった。
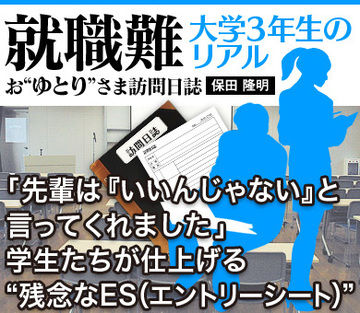
第6回
1月にもなると、学生は一応、通り一辺倒な自己分析とやらは行っている。しかし、大体は薄っぺらなものだ。学生自身もうすうすとそれが分かっているものの、それ以上はどうしようもないので、セミナーやら面接やらで自分を忙殺することに一生懸命になる。
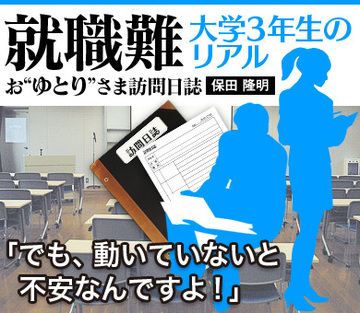
第5回
どの会社のエントリーシートでも「大学時代で打ち込んだこと」「その中で成し遂げたこと」を書いてくださいと指示されていると、学生は「就活は“スペック”採用」なんだと思い込んでしまう。これは学生にとって悲劇に他ならない。
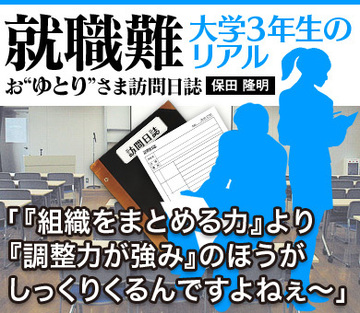
第4回
「分からない」と「分かろうとしない」は大いに違う。多くの学生は分かろうとしない。しかし今回取り上げるポワンちゃんは分かろうとして分からなかったのだ。それでも、授業で「分からない」と発言することは勇気がいる。それはビジネスの場でも同じだ。
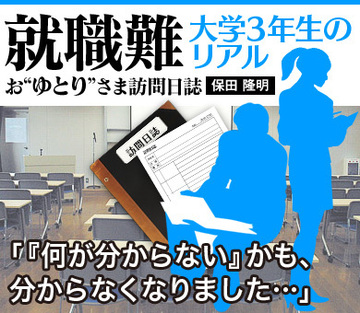
第3回
学生生活で、群れずに何かをしようとすると、「なんだか真面目にやっちゃっているね」という目で見られる。この真面目に見られてしまうというのは学生には居心地が悪い。見出しの「見た目チャライのに」発言は、実際に研究室にやってきたチャラ男くんが発したものである。
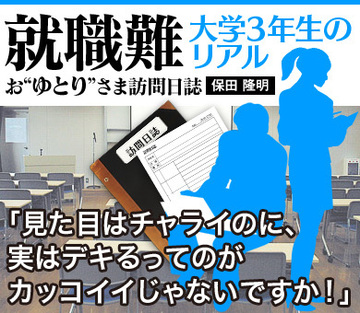
第2回
リアルな就活の現場のひとコマを、北海道のとある国立大学からお伝えする短期連載。今回は、初対面の人と話すのが苦手だから、経理を志望しているという学生の話をしたい。可能性の大きさを楽しむ度量が、最近は失われているようだ。
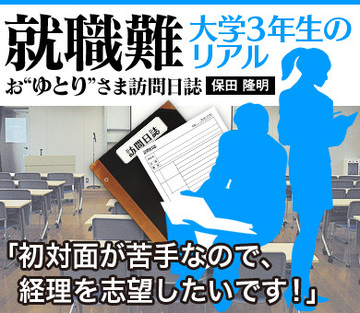
第1回
北海道のとある国立大学で教鞭を執る著者のもとに、毎日やってくる大学3年生の学生たち。就活、恋愛、人生……。不安を抱えながらも、どこかのどかで牧歌的。そんな彼らは、本当に「ゆとり」なのか? リアルな現場の一コマを毎週リポートする。
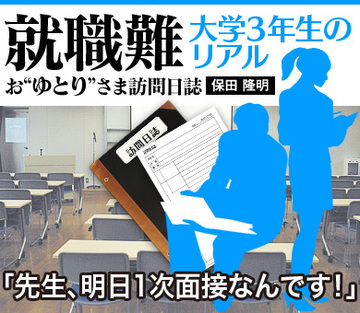
第46回(最終回)
3月で大学院を修了すると同時に、4月からある国立大学の大学院の教員に赴任することとなった。それは研究の中には、実務で転用可能なものが多く、一方でそれらを実務界に伝達する存在が多くはないことを知ったからだ。

第45回
デフレ進行中ということで、外食や小売り、アパレルなどにおいては「こんなに安い店が人気」という語られ方をすることが多い。しかし、デフレ時代においても、勝てる外食産業の方程式は決して値段だけではない。

第44回
オリンピックを見ていると、選手が様々な企業に所属していることが分かる。ただ、メダルを獲得できる選手は一握りで、選手を抱えることの投資効果は、ほとんど見合わない。それでも企業が選手を雇用するのはなぜだろうか。

第43回
今回の経営統合破談は、両社の統合比率で合意できなかったことが原因とされている。その背景には、日本式である統合決定後に統合比率や買収金額などの中身を調整手法があり、これがリスクになったとも考えられる。

第42回
国内各証券取引所の上場規定が改正され、「ライツイシュー」が解禁された。この「ライツイシュー」、一部メディアが新株予約権を無償で「もらえる」と表現しているため、得をしそうな錯覚に陥るが、全く得はしない。
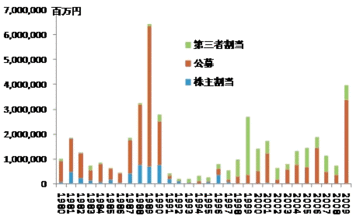
第41回
「1本60円のアイスキャンディで、電車のラッピング広告やテレビCMを打って利益は出ているのだろうか」と余計な心配をしてしまう商品、ガリガリ君。しかし実はこのマーケティング戦略こそ、とても優れたものだった。

第40回
2005年グループ連合の支援を受け再生した三菱自動車。今度はプジョーが出資交渉中と報道されている。しかしこの10年、日本企業には三菱のようにグループ結集でシナジーを生み出すという視点が抜け落ちているように感じる。

第39回
つい1年~半年ほど前は日本市場で歓迎されていた公募増資だが、景気が相対的に持ち直した今、批判が集まっている。しかし、今回の増資に関しても、いつも通り批判の対象とすべきではないのではないだろうか。

第38回
「我々は誰のためにコーポレートファイナンスを学び、誰のために最適と思われるコーポレートファイナンスを実践するのか?」今回のコラムでは、この質問に対する答えを整理してみたい。

第37回
日本には3000ほどの投信商品が存在する。ある程度の商品数に絞ったほうが投資家にとっても、運用側にとってもいいと思うのだが、商品提供側がひたすら新商品を提供し続けた結果、商品数が膨大になってしまった。
