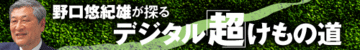野口悠紀雄
第43回
新聞ではニュースが間に合わないという事態が続いている。リーマン破綻の翌日は休刊日、米連邦議会が金融安定化法案を否決したときも翌日の朝刊はそのニュースを掲載できなかったのである。株価も為替レートも、めまぐるしく揺れ動く情勢に振り回されて、ジェットコースター並みのスピードで乱高下している。金融に直接関係しない人でも、新聞だけでは仕事に必要な情報を時間遅れなく得ることができないと実感するようになった。今回の金融危機はさまざまな点で新しい経験であったが、従来のメディアがスピードの点で対応できないことが暴露された点でも、大きな事件だった。
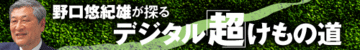
第42回
日本の巨大メディアが「公衆の番犬」(国家を監視する機能)の機能を果たしているとは到底思えない。むしろ政府のプロパガンダの伝達役でしかない。政府の宣伝文句に何の疑いも持たず、受け売りで報道している。
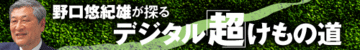
第41回
現在の新聞には大きな問題がある。第一に、ページ数が多すぎる。第二に、見出しの重要性を十分に認識した紙面構成になっていない。ネット時代において、紙の新聞が果たすべき役割を少しも自覚していないように見える。
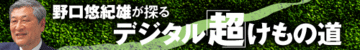
第40回
日本では新聞もテレビもウェブへのコンテンツ公開は限定的で「ウェブへの移行」があまり実感できない。日本のジャーナリストたちは、いまだに「インターネットは草の根メディア」と思っているようだ。
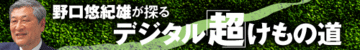
第39回
私はしばらく前から「新聞の株式欄はなぜあるのだろう?」と疑問に思っていた。各銘柄の株価なら、ウェブでより早く大量にデータを無料入手できる。翌日の新聞で初めて株価を見る人が、いったい何人いるのだろう。
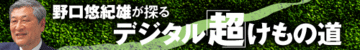
第38回
オリンピックはインターネットで見たい――では、どのサイトで見ればよいだろう?私が調べた限り、オリンピックに関するウェブサイトで群を抜いて充実しているのは、MSNBCのオリンピック特集ページである。
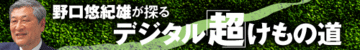
第37回
この1~2週間の間にウェブの世界には大きな出来事が2つ起こった。1つはグーグルマップの「ストリートビュー」の日本版が公開されたこと。そしてもう1つは新しい検索エンジン「Cuil(クール)」が公開されたことだ。
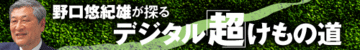
第36回
グーグル検索を続けていると、これが常に自分が調べたい目的の重要度順に並んでいるような錯覚に陥り、その正しさを疑うことを忘れる。しかし時には、きわめて良質の情報を取り逃がしてしまっている可能性もある。

第35回
世界各国の首脳と比べ、日本の首相の認知度はどの程度だろうか?洞爺湖サミットに参加した首脳についてニューヨーク・タイムズの記事数を調べると、主催国である福田首相の記事数は参加者中最低だった。
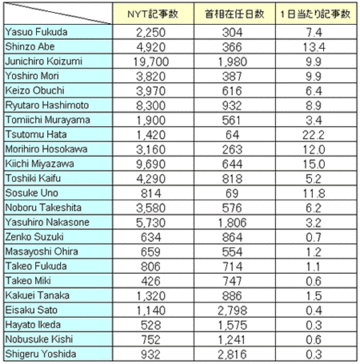
第34回
昨年夏に始まった世界的な経済混乱は、終息するどころかますます深刻さを深めているように見える。この問題に関するニューヨーク・タイムズと読売新聞の記事を比較してみた。
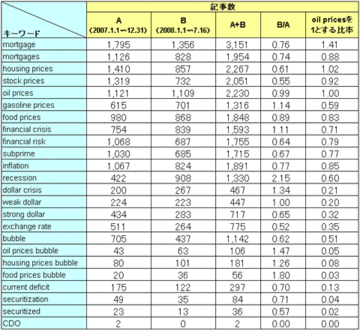
第33回
過去のアメリカ大統領選について、選挙以前の時点でのニューヨーク・タイムズ記事数の推移はどうだったのか?ここでも、選挙の結果を正しく、しかも「大接戦であった」ことまで予測していたのだ。
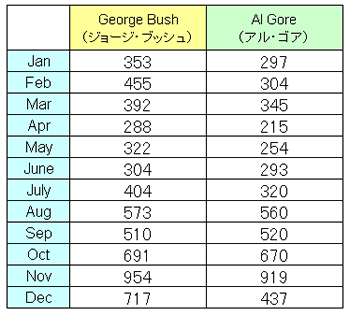
第32回
前回、ニューヨーク・タイムズの検索がアカデミー賞の結果を事前に予測していたように見えると述べた。政治的な動きについても同じような予測がありうるのか、大統領選を例にとって見てみよう。
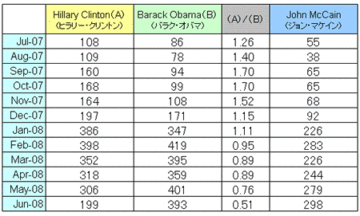
第31回
今回はニューヨーク・タイムズの記事数から、アメリカの映画賞である「アカデミー賞効果」について考えてみる。やはりアカデミー賞は、作品の評判を増幅させる役割を持っているのだろうか。
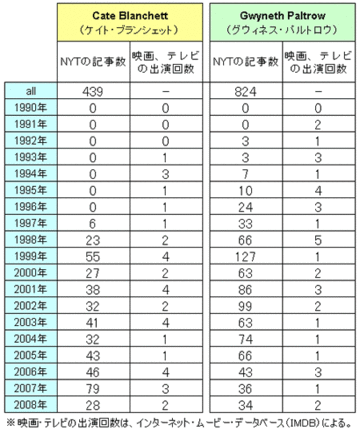
第30回
これまでの分析をさらに進めて、販売戦略に関する重要な情報をニューヨーク・タイムズの記事分析から抽出、表を作成し、各項目の構成比を見比べてみると、興味深いことがわかった。
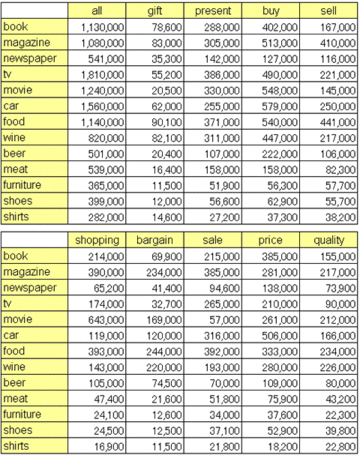
第29回
「NYTの検索ページ」で、gift(贈り物)というキーワードから、アメリカ人の贈り物に関する行動を調べてみた。そこにはビジネスモデルの重要なヒントが隠れていた。
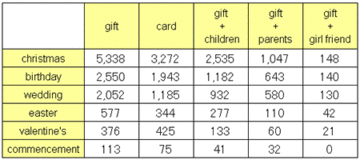
第28回
前回に続き、今回も「NYTの検索ページ」の有効な使い方を紹介しよう。検索結果を改めて表にしてみると、アメリカ人たちが日本・中国・ドイツに対して何に関心を持っているか、興味深い事実が見えてくる。
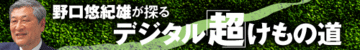
第27回
1981年以降、ニューヨーク・タイムズの記事に登場したJapan,China,Koreaという言葉の登場数を調べてみた。するとその数字から、各国の経済変化や関心度の高さが浮き彫りになった。
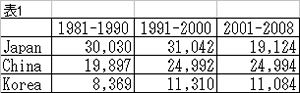
第26回
ニューヨーク・タイムズが、過去記事のオンライン検索・閲覧を2007年の秋から無料化している。これは実に大きな事件だと思う。なぜなら、われわれの情報環境がこれによって一変したからだ。
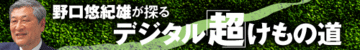
第25回
「あらたにす」では3紙を比較するということが前面に出ているが、「比較」ということにどれだけ意味があるのか。利用者が求めているのは、むしろ3紙の「相互補完」ではないだろうか。
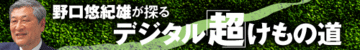
第24回
インターネットによって情報の切り抜き作業は大きく変わった。検索機能を活用すれば、大量の情報を、ウェブから簡単に「プル」することができるからである。