
野口悠紀雄
第14回
東証1部上場企業の09年3月期決算は、経常利益が60.8%減と大幅減益になると予想される。企業収益の急速な落ち込みは、税収、ことに法人税収に大きな影響を与える。企業減益と同程度水準まで落ち込む可能性が強い。
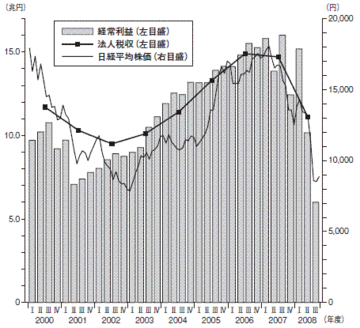
第13回
経済の急激な落ち込みで、経済指標への関心が高まっている。これら指数変化は、対前年比のものと、対前期(月)比のものがある。最近のように変化が激しくなると、どの尺度で見るかで印象がかなり異なってくる。
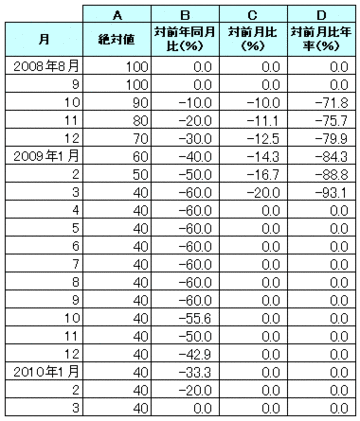
第12回
08年第3四半期までのアメリカの経常赤字はほぼ7000億ドル程度。これが半減するには、第4四半期の値よりさらに2000億ドル程度の減少が必要である。では、これはどの程度のスピードで実現するだろうか。
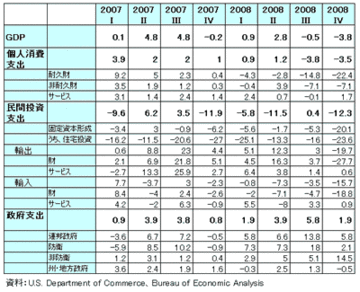
第11回
MBAの人気復活はいまや世界的傾向である。しかし日本企業は学校の勉強よりも実務を重視しており、大学院での勉強成果を給与に十分反映してくれない。この点が変わらないと日本でMBAを普及させるのは難しい。
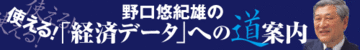
第10回
「経済危機が深刻化すると、ビジネススクールへの入学志望者は、増えるだろうか、減るだろうか、あるいは影響を受けないだろうか?」「In Tough Times, M.B.A. Applications May Be an Economic Indicator(不況時にはMBAの志望者数が経済指標になるかもしれない)」というタイトルの「ニューヨーク・タイムズ」の記事は、このようなクイズで始まる。この答えは、「増える」である。しかも、顕著に増えるのだ。
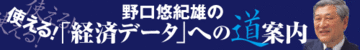
第9回
アメリカの住宅バブルの崩壊によって輸入が減少すると、日本は2重の意味で影響を受けることになる。アメリカに対する直接の輸入が減少するだけでなく、中国を経由する分も減少するのだ。
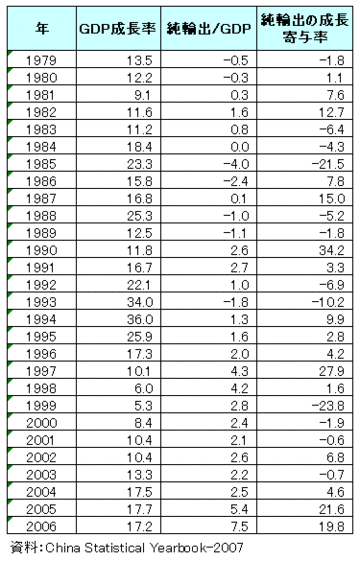
第8回
IMFが09年世界経済成長率見通しを、日銀も09年実質GDP成長率見通しを大幅に下方修正している。これでもまだ楽観的ではないかと考えられるが、政府の経済見通しいたっては09年の実質成長率はゼロ%である。
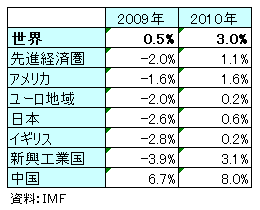
第7回
1月22日に発表された貿易統計で、日本の輸出が壊滅的な事態に陥っていることが改めて明らかにされた。もっとも激しいのは自動車で、対前年比45.4%減。対米自動車輸出は52.6%の減という信じられないような値だ。
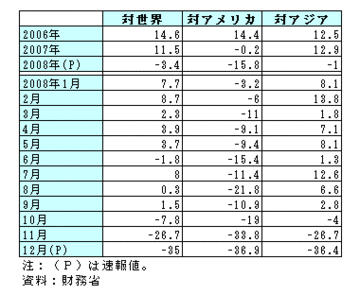
第6回
今後輸出の大幅な増加は見込めないため、貿易収支の赤字はもはや定着してしまったと考えることができる。つまり、製造業をベースにした「ものづくり輸出立国」の時代は、終焉したのである。
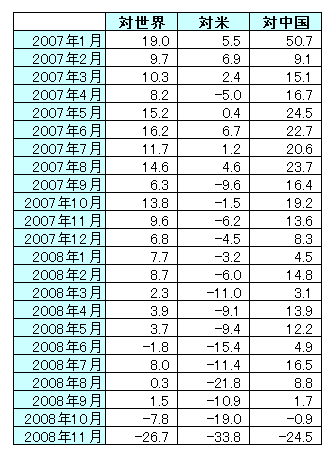
第5回
アメリカ議会予算局(CBO)が1月7日に公表した経済見通しは、「住宅市場の落ち込みによって発生した今回の景気後退が、第二次大戦以降で最悪、かつ最長のものになる」と結論づけている。これは、かなり悲観的な見通しだと言うことができよう。以下では、この見通しを念頭におきつつ、最近のアメリカの経済情勢と、それが日本に及ぼす影響について考えることとしよう。
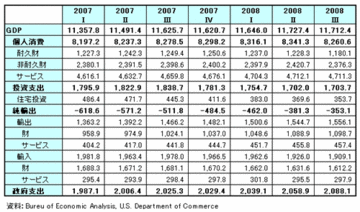
第4回
アメリカの経常収支の赤字額があまりに巨額になったためにドルに対する信頼がゆらぎ、それが金融危機を発生させた。したがって、赤字が持続可能なレベルまで縮小しないかぎり、経済危機は終息しないと考えられる。
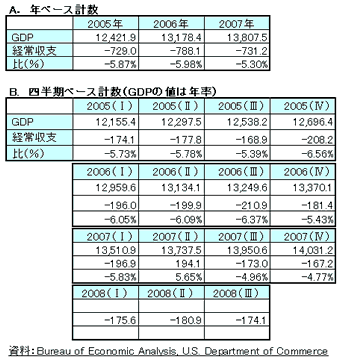
第3回
日銀はCPの直接購入に踏み切った。対象企業の範囲などの詳細はまだ決められていないが、これが前代未聞の措置であることは間違いない。最大の問題は、企業の破綻リスクを日銀が負ってしまうことである。企業が破綻すれば、資金を回収できず、日銀の資産が劣化する。そして、通貨への信頼が失われる。また、財政負担となり、国民に負担が及ぶ。したがって、これまでは禁じ手と考えられていた措置だ。日本銀行は、パンドラの箱を開けてしまったことになる。
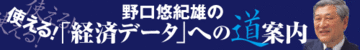
第2回
意味ある経済政策となるためには、3年で25兆円規模の財政拡大が必要である。その財源として日銀引き受けの国債発行が考えられる。しかしこれは封印されていたパンドラの箱をあけることになる。
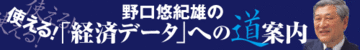
第1回
いま世界で起きているのは、マクロ経済学の教科書に書いてあるとおりの事態だ。しかしこれまで私は、「マクロ経済学はくだらない」と考えていた。現実の世の中とかけ離れていたからである。
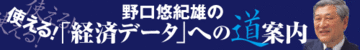
最終回
クラウド・コンピューティングとは、重要な情報を手元に置かず、他人に預けてしまうという方法。大事なものが手元にないというのは不安なものではあるが、その不安を克服できたものだけがメリットを享受できる。
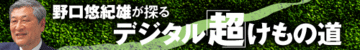
第48回
Gmailの下書き機能は、メモのオンライン格納にも便利である。PCからも携帯からも入力したり見たりすることができる。しかし、オンライン格納を行なうようになってから、意外にも紙の使用量はかなり増えた。
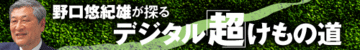
第47回
データをHDではなくオンライン上に格納する方法として「自分宛にメールを出す」という方法がある。しかしそれ以上にもっと簡単な方法に気づいた。Gmailの「下書き」機能を利用するのである。
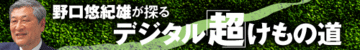
第46回
クラウド・コンピューティングには、さまざまなものが含まれる。今回は、NYタイムズの記事を参考に、その概念を整理するとともに、企業向けサービスの最新事例を紹介したい。
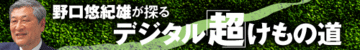
第45回
グーグルが「クラウド・コンピューティング」を志向するのは、同社のこれまでのビジネスモデルを考えれば、当然の方向である。注目されるのは、この方向を志向しているのがグーグルだけではないということだ。
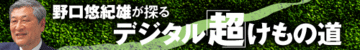
第44回
「クラウド・コンピューティング」という考えが、今後のコンピュータの使い方を示すものとして注目を集めている。データやソフトをPCから「雲」の中に移し、必要に応じて取り出して使うというものである。
