
高橋洋一
ふるさと納税制度が定着し始めている一方で、返礼品規制など国からの干渉や介入は相変わらずだ。多額の寄付を集めた4市町村に対し2018年度の特別交付金(3月分)を減額したのはやり過ぎだ。

大阪府知事・市長の「ダブル選挙」は「大阪都構想」が焦点になっているが、近畿圏の活性化では大阪万博・IRも注目されていい。IRは“国際観光拠点として近畿圏のGDPを押し上げる効果が期待できる。

景気動向指数の基調判断が下方修正され「戦後最長」とされている景気拡大が怪しくなった。だが指数の動きを見れば、2014年4月の消費増税を機に景気循環は一度、「谷」をつけていたと判断するのが妥当だ。

大阪の松井知事と吉村市長が入れ替わりで“ダブル選挙”に出る方向だ。「大阪都構想」の是非を問う住民投票を再び実施する狙いだが、「大阪都」が実現すれば行政効率化だけでなく近畿圏の活性化につながる。

野田市で起きた父親による小学生虐待死事件は、その痛ましさだけでなく、児童相談所や経験のある職員が不足し「SOS」を受け止められなかった、子供を守る行政の心もとなさを浮き彫りにした。

今国会の代表質問で野党議員が原稿をタブレットで読もうとして認められなかった。ペーパーレス化の遅れだけでなく、質問の事前通告や大臣の拘束時間など、長年続いてきた“時代遅れ”を変えることが急務だ。

2018年の全国の自殺者数が記録的に減ったのは超金融緩和で失業率が低下したことが背景にある。金融政策の「成果」といえるが、肝心の日本銀行に金融政策が雇用政策だという認識がないのが問題だ。

辺野古移設「反対」派には、サンゴの生息環境が破壊されることを理由にする人がいるが、基地移設とサンゴ環境の保護は両立できる。サンゴを守るために他国からの脅威が増すのでは本末転倒だ。

日経平均株価が1年3ヵ月ぶりに2万円台を割り込んだが、株価だけでなく、来年は自然災害や極東情勢の不安定化など「さまざまリスクの年」になりそうだ。消費増税はやめるのが合理的だ。

産業革新投資機構の社長以下、民間出身の取締役全員が辞任を表明したのは当然の結末だ。政府に新産業の育成ができるというのは幻想で、“官主導”でリスク投資をする「官民ファンド」の限界が露呈したものだ。

ゴーン・前日産会長逮捕の背景には、仏政府が最大株主のルノーの支配が強まることへの日産社内の抵抗や、国内メーカーを守りたい経産省、さらには米国の思惑が反映した複雑な力学が働いたと考えられる。

新在留資格による外国人労働者の受け入れ拡大で政府は「5年で34万人」を検討しているというが、政府方針通りならアベノミクスの成果の雇用創出や一部の賃金上昇を台無しにする恐れがある。

白川方明・前日銀総裁が書いた話題の本、『中央銀行』を読むと、デフレや円高について、いかに誤った考えを持っていたかがわかる。デフレ脱却を妨げた「戦犯」だと言わざるを得ない。

来年10月の消費増税を政府が閣議決定したような報道があったが、増税を確定させたい財務省の思惑に乗ったような書き方だ。財務省が増税の根拠にする「財政破綻」の可能性は怪しくなっている。増税論議はゼロからやり直すべきだ。

ノーベル賞を受賞した本庶佑・京大特別教授が“無駄”の多い基礎研究に資金を使う重要性を強調したが、これは人口減少などが進んでも経済成長が維持されれば年金や財政の破綻が回避できること示唆する。
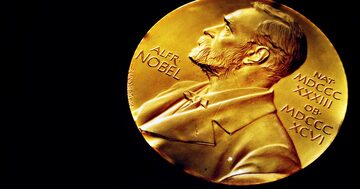
返礼競争の“過熱”を抑える名目で野田総務相が打ち出したふるさと納税制度の規制強化は、時代に逆行する。安倍政権での立ち位置が微妙な状況で制度導入に抵抗していた官僚に乗せられた要素が強い。

自民党総裁選は安倍首相と石破茂元幹事長の間で「脱デフレ」の政策論争が予想されるが、アベノミクスは大恐慌の教訓を踏まえた正しいリフレ政策だ。財政健全化に力を入れる石破氏は処方を間違う可能性がある。

コメや麦の種の生産や開発の国の管理を決めていた「種子法」が廃止されたが、外資や農業法人の参入を懸念して一部の農家では反発が根強い。だが誤解によるもので、「TPP反対」と同じだ。

2020年の東京五輪の暑さ対策として「サマータイム導入」が浮上しているが、夏の日照時間が極端に長いわけではない日本では効果は限られる。そもそも夏場の五輪開催は商業上の事情で避けられないことになっている。

学校のエアコン設置率にばらつきがあるのは、自治体が優先して予算を配分しているかどうかの「やる気」の違いだ。電力不足への対策など、考え方や工夫次第でやれる“酷暑対策”はほかにもある。
