
高橋洋一
第161回
今回の釜山の慰安婦少女像の設置について、安倍政権は毅然とした外交姿勢を示したが、非は日韓合意を破った韓国側にある。韓国は、国家の信用を問われており、信用がなければ、通貨スワップ協定はできない。

第160回
「景気」は「雰囲気」で語られることが多い画が、筆者は二つの経済指標「雇用」と「GDP」で考えている。これら指標で判断すると2016年の経済政策は雇用は改善したが、GDPが今一歩なので70点程度と考える。

第159回
15日から日ロ首脳会談が行われる。注目はやはり北方領土問題だが、日ロの領土交渉はそれほど甘くない。それでも、戦後70年間で1ミリたりとも動かなかった交渉話が「やっと動いた」という意味で画期的なことである。

第158回
筆者は本コラムで「日銀当座預金を民間銀行の「預金」と勘違いする人々へ」を書いた。それに田中秀明・明治大教授が「埋蔵金と日銀の国債購入で日本の借金は消えるのか?高橋洋一教授に反論!」というので再反論する。

第157回
安倍首相は17日、トランプ次期大統領の会談する。しかし、課題の多い日米関係について、十分に話し合う時間はない。まず、行いたいのは、個人的な信頼関係の構築である。そこで、両者が好きなゴルフがカギになりそうだ。

第156回
先日の「ダイヤモンド・オンライン」で、日銀BSの負債の「預金」が債務性のある民間銀行の預金と同じと勘違いしている記事が見られた。同様の間違いは他の経済学者にも見られる。これらの間違いついて、指摘したい。

第155回
日銀による金融政策の「総括的な検証」を受けて、「リフレ派の敗北」を強調する報道が見受けられる。日経新聞をはじめ「失敗して路線変更を余儀なくされた」という記述が共通して見られるが、本当だろうか。

第154回
基礎研究のように、懐妊期間が長く、大規模で広範囲に行う必要のある投資は、公的部門が主導すべきだ。その場合、投資資金の財源は、税金ではなく、将来に見返りがあることを考えると、国債が適切である。

第153回
蓮舫新代表の民進党は、党内人事が上手くいっておらず、たたでさえ、前途は容易でない。それに加え、経済政策を見ても見劣りしている感がある。

第152回
北方領土返還は実際問題として難しいのは事実だが、プーチン大統領の訪日を12月に設定できたのは、今回の日ロ首脳会談の成果であり、北方領土問題が今年12月に動く可能性は十分にある。

第151回
音楽業界業界4団体は8月23日、チケットの高額転売に反対する共同声明を発表した。このチケット転売問題は、経済学ではどう考えるのだろうか。検証してみた。
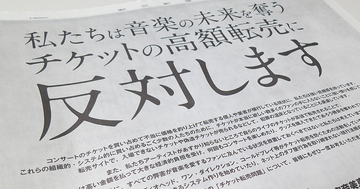
第150回
中国船の尖閣諸島周辺への領海侵入が連日相次いでいる。じつは尖閣諸島は米軍射爆撃場が設定されている。中国の領海侵犯に対し、この際、米軍に射爆撃場として活用してもらってはどうか。

第149回
今回の政府の経済対策を考えてみると、ベースとなるのは、国債発行による財政支出と今行われている量的緩和。GDPの押し上げ効果には真水が必要であり、それがどうなるかがポイントとなる。

第148回
最近、「ヘリコプターマネー」という経済政策が話題となっている。政府はこの政策を検討しているとの報道もある。そもそも「ヘリコプターマネー」とは何か。政府はこの政策を実施するのだろうか。

第147回
イギリスのEU離脱による世界経済の混乱は当面続くと予想される。その悪影響はリーマンショック級とみて、日本はそれなりの経済対策で備えておく必要がある。

第146回
三菱東京UFJ銀行による国債市場特別参加者の返上について、マイナス金利の弊害とするマスコミの論調も多い。こうしたマスコミの指摘は本当なのだろうか。

安部首相は2017年4月からの消費増税の先送りを表明した。財政再建至上主義の財務省は、相当な抵抗をしたようだが、現状をみると、経済政策として消費増税の延期は当然である。

第144回
日銀は、今の失業率水準である3%前半をこれ以上低下できない構造的な下限水準(構造失業率)とみている。そう考えると、これ以上金融緩和しても無意味ということになるが、その見方には異論がある。
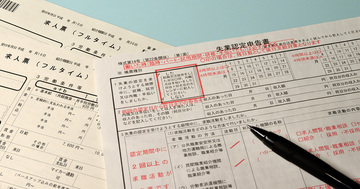
第143回
熊本地震の発生により、一部で自粛ムードが漂っている。自粛は控え、個人ではふるさと納税で被災地を支援し、国はヘリコプターマネーを活用して積極的に復興支援をすべきだ。

第142回
財政学者には依然として消費増税による財政再建を主張する人が多い。だが増税や歳出削減はかえって財政を悪化させる恐れがある。財政再建の手段はそれだけではない。彼らはなぜ増税に固執するのか、どこが誤りなのか指摘しよう。
