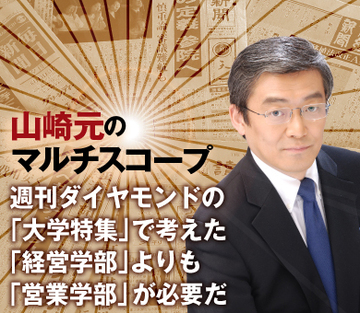山崎 元
第318回
ソフトバンクが大学の新卒採用に関して、選考を通年で行う方針を持っていることなど、最近大学と企業との関係について、将来の改善の可能性を感じさせるニュースが出て来た。優秀な人材を社会に輩出するための大学改革の必要性を論じたい。
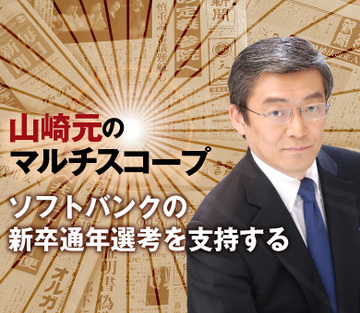
第317回
現在発売中の『週刊ダイヤモンド』の特集タイトルは、「お客をつかむ33の法則」だ。この中で地方消費のボリューム層として“ヤンキー世帯”が取り上げられている。実はヤンキーのライフスタイルには、我々が学ぶべきポイントが多くある。
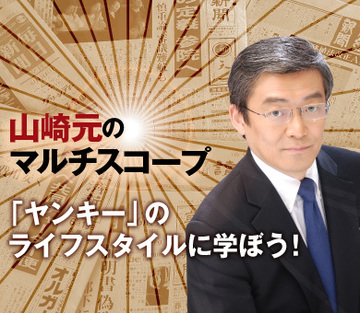
第316回
金融庁が2015年中にも保険の販売ルールを創設する意向で、現在の株式や投資信託並みの説明義務を課すものになりそうだという。筆者の率直な感想は「今頃か」というものだ。保険業界では、これまで消費者無視の販売が続けられてきた。
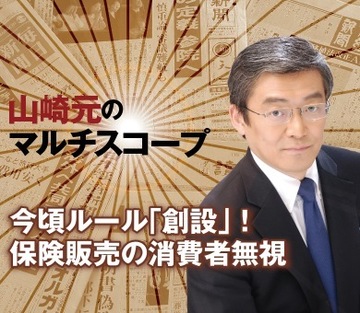
第315回
最新号の『週刊ダイヤモンド』の株特集は、株式投資の今を考える上で絶好の教材である。株式投資をまじめに考える上で参考になるテーマが、バランス良く配されている。今回はこの特集の内容に触れながら、株式投資の「今」を考えたい。
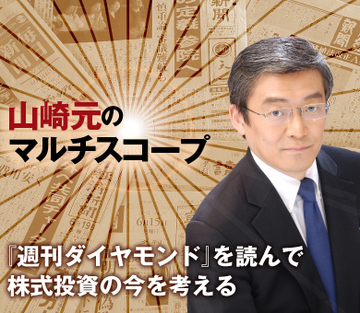
第314回
筆者は獨協大学で「金融資産運用論」と題して、学生にお金の運用方法について伝える授業を持っている。期末になったので、先日試験を行った。今回は、筆者の出題意図を述べると共に、学生の答案からわかった金融リテラシーを分析してみよう。
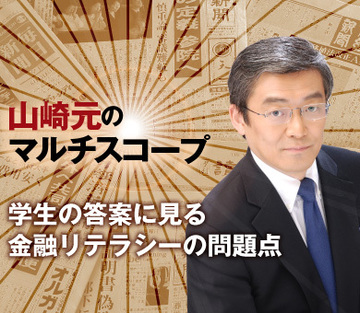
第313回
新聞報道によると、投信残高全体に占める毎月分配型投信のシェアは一時期よりも低下してきたものの、それでもまだ約3割を占めているという。投資家には、「毎月分配型」から早く卒業することをお勧めする。その理由を改めて述べたい。
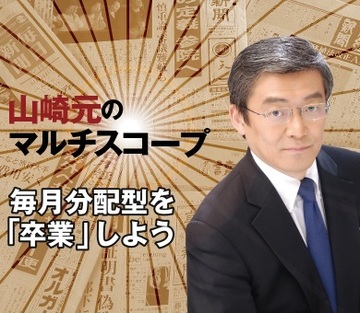
第312回
新年からNISA(少額投資非課税制度)が始まった。市場が年初から波乱含みの展開になったため、含み損を抱えて運用をスタートした人も多いだろうが、NISAを嫌いにならないでほしい。ここで改めて、投資家にとっての留意点を述べたい。
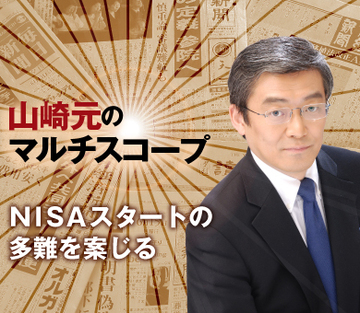
第311回
消費を止められなくなる「依存症ビジネス」は消費者にとって困りものだが、現在国会で継続審議中のカジノ解禁法案に筆者は賛成だ。日本に登場するかもしれないカジノをはじめ、依存症ビジネスとの正しい付き合い方を考えてみたい。
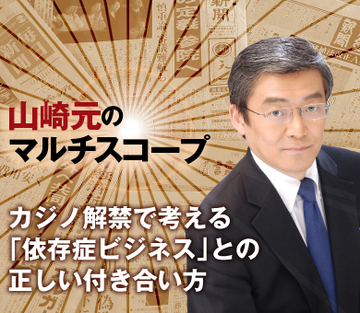
第310回
アベノミクス相場には、これから「後半戦」があると思っている。予想というものは難しく、筆者も自分の見立てが必ず当たるとは思っていないが、その後半戦に乗るに当たって、投資家が「転ばぬ先の杖」をつくべき5つのポイントを、お伝えしよう。
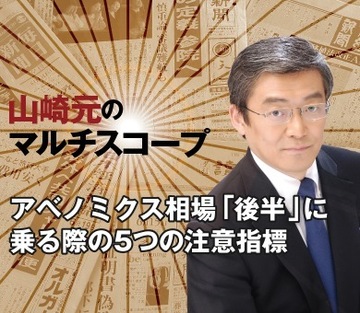
第309回
先日筆者はダフ屋、特にネットに活動の場を移した「ネットダフ屋」についてどう思うかについて、取材を受けた。筆者は、ネットダフ屋“積極”肯定論者だ。ネットダフ屋が育つことで、ダフ屋の弊害はむしろ克服され、メリットが増えるだろう。
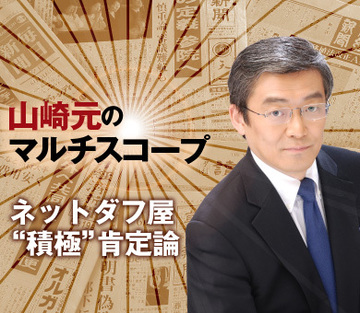
第308回
大企業15社が、学生の授業ごとの成績を採用情報として活用するという。これまで民間企業では、選考段階で学生に成績を提出させなかったので、これは大きな方針転換だ。実は「できるビジネスマン」になれるかどうかは、高校の学力で決まる。
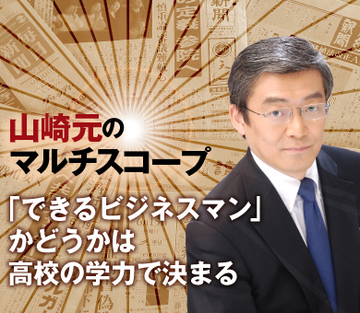
第307回
現段階で筆者は、相場・景気・経済政策いずれの点でもアベノミクスの「終わり」が近いとはさらさら考えていないが、相場にも景気にもいつかは終わりが来る。それがどのような形で来るのか、筆者なりに5つの可能性について考えておきたい。
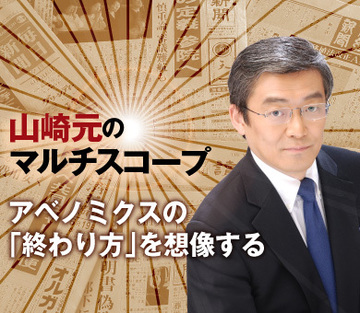
第306回
11月下旬の日経新聞に、「生保、逆ざや解消」のニュースが躍った。主要9生保の今年の4~9月期の生保決算で、生命保険会社の利差損益がプラスに転じたのだ。生保勤務の経験がある筆者には感慨深い。生保を苦しめ続けた原因と教訓を振り返ろう。
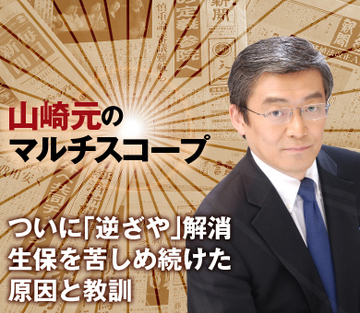
第305回
『週刊ダイヤモンド』11月23日号では、「守る資産運用」のタイトルの下、資産運用を特集している。同誌で長らく連載を持っていた筆者は、卒業生が母校に持つような関心を持ちながら、この特集の読みどころとツッコミどころを述べたい。
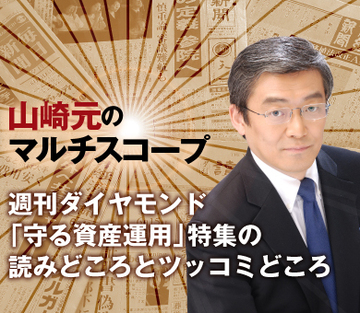
第304回
ヤマダ電機が営業赤字に転落した。消費者が家電購入時に小売店で商品の実物を確かめ、そこで買わずにネット通販で買い注文を入れる「ショールーミング」の普及が、家電量販店に危機感を与えている。ショールーミングは正しい消費行動なのか。
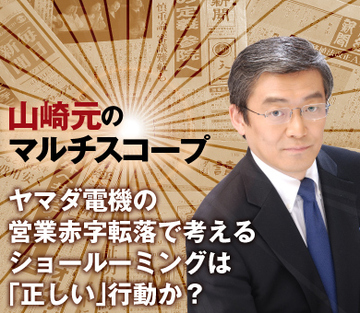
第303回
連合総研が行ったアンケートによると、民間企業で働く20代の社員の23.5%、30代の20.8%が、自分の勤め先を違法な働かせ方で若者を使い捨てにする「ブラック企業」だと感じているのだという。ただし、どの企業・職場が真に「ブラック」なのかは、判断が微妙な場合があろう。
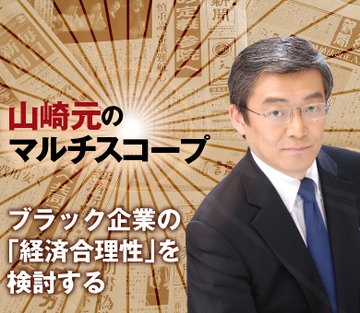
第302回
時を同じくして「謝罪」をすることになった、阪急阪神ホテルズの出﨑弘社長とみずほ銀行の佐藤康博頭取。筆者は今回直接の被害者ではないが、会見に臨んだ2人のトップ及び会社側の立場から、謝罪と言い訳の出来不出来を評価してみたい。
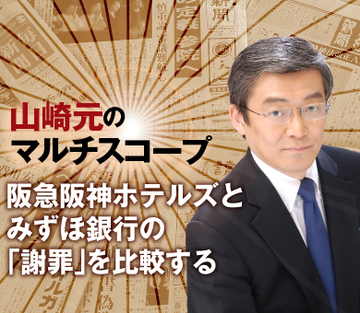
第301回
現時点で、アベノミクスの現状をどう評価すればいいのだろうか。最終目標をデフレ脱却とすれば、現在はどの段階にあるのか。筆者はアベノミクスの、主に金融緩和政策に対して肯定的な立場であるが、なるべく客観的に中間評価をしてみたい。
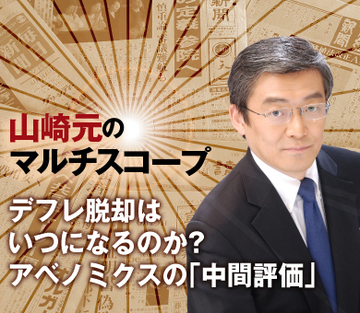
第300回
母体である旧第一勧銀で起きた総会屋事件の教訓から、「反社」に敏感なはずのみずほ銀行で、なぜ今回のような不祥事が発覚したのか。人が倫理的な組織を築けない原因を、行動倫理学分野の研究成果を紹介した『倫理の死角』という本から読み解く。
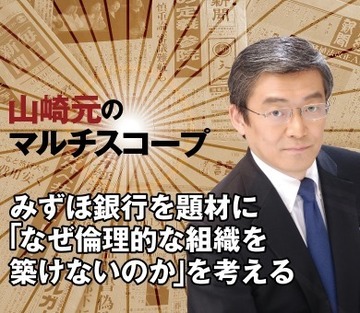
第299回
今週号の『週刊ダイヤモンド』の特集「大学 徹底比較」を読んで、気づかされたことがある。大学は専門知識を教える一方、企業の仕事は約8割が営業だという。ここに、採用における大学と企業のズレがある。大学には「営業学部」が必要だ。