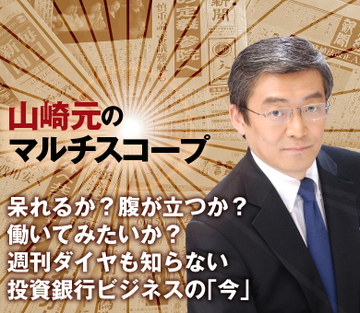山崎 元
第358回
雑誌の読者が目に見えて高齢化しているせいか、筆者は最近、「60歳からのマネー運用について」とか「退職金の運用方法について」といったテーマで取材を受けることが多い。この際、重要だと思うポイントについて、簡単にまとめておきたい。
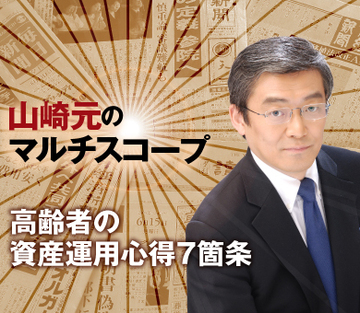
第357回
衆議院選挙が昨日公示された。安倍政権にとっての勝敗は、実はぎりぎりの勝負だと筆者は見ている。気になるのは、突然の解散という「奇襲」を受けた野党の戦い方だ。果たして彼らのマニフェストは、自民党に対抗でき得るものだろうか。
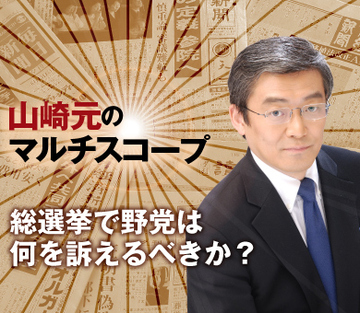
第356回
安倍首相がアベノミクスを争点に解散総選挙に臨む。中間層が割を食う側面があるアベノミクスは、中間層の反発を招く可能性がある。そのための政策的な手当てが成長戦略なのだが、そこに解雇規制緩和が含まれていないことについて論じよう。
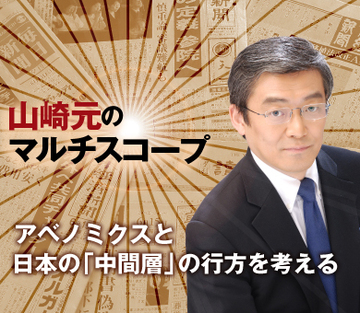
第355回
安倍首相は、消費税率再引き上げの延期と衆議院の解散を発表した。筆者は、解散医は十分な大義があると思う。今回は、総選挙の争点となる安倍内閣の経済政策について整理しよう。総選挙後の「アベノミクス2」を、我々はどう評価すべきか。
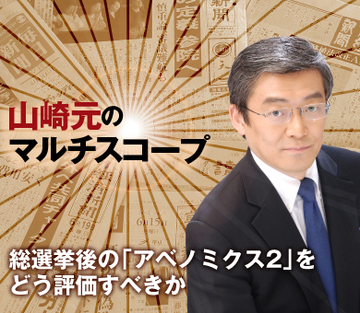
第354回
安倍首相が、消費税率再引き上げを延期して衆議院を解散するのではないか、というムードが、にわかに高まってきた。もし解散が本当にあるなら、いつになりそうか。また、そのときにマーケットはどう動くだろうか。投資家の判断が迫られる。
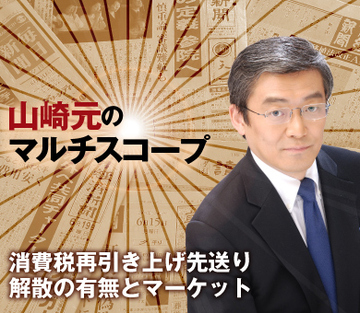
第353回
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が新しい中期計画を発表し、基本ポートフォリオの内容がわかった。個人投資家は、GPIFの新方針をどう読むべきか。筆者は、「真似する」「利用する」「反面教師とする」の3つの読み方をお勧めしたい。
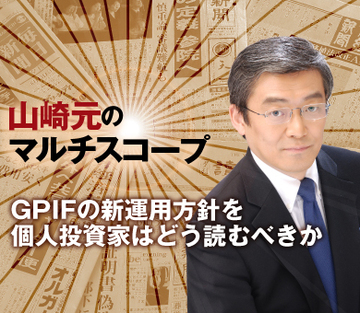
第352回
地方銀行に勤める女性行員が、配偶者の転勤先にある別の地銀で働けるようにする仕組みを、全国の地方銀行64行が検討するという。筆者はそれ自体を前向きに評価したい。しかしその実現には、地銀の人事システムに関わる深い課題が横たわる。
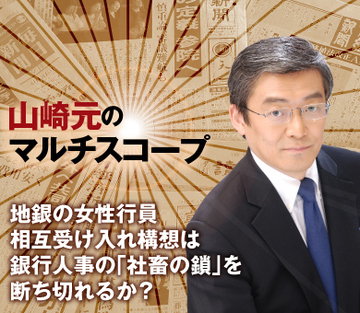
第351回
株価が足もとで不安定な動きを続けている。昨年5月の波乱局面以来、1万6000円近辺を抜けきれずに跳ね返される展開は、感触が良くない。投資家は、まだパーティー楽しんでいていいのか。果たして、アベノミクス相場は終わったか否か?
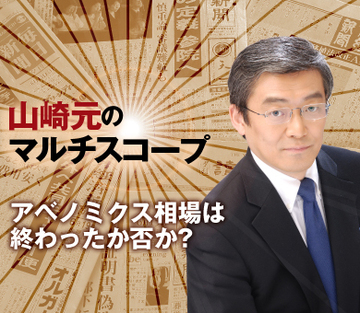
第350回
我々は「老後不安」に対して、どう備えたらいいだろうか。このような人生の大問題は、今持っているお金の運用だけで解決できるとは考えない方がいい。ただし、老後を怖がり過ぎるのも考えものだ。老後不安と資産運用について、考えてみよう。
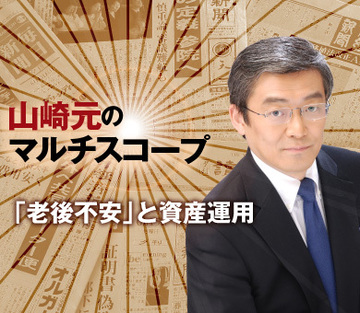
第349回
日立製作所の年功賃金廃止は、日本企業の人事制度全体にとって、エポックメイキングな出来事として振り返られることになりそうだ。その意義を考察すると共に、世の中のビジネスパーソンがこの流れにどう適応していくべきかを考えよう。
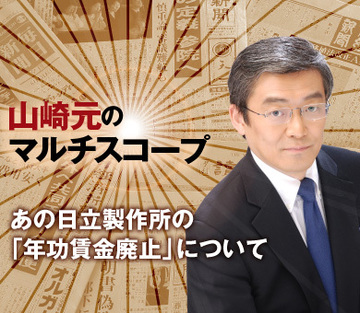
第348回
ピーター・ティール氏の著書『ゼロ・トゥ・ワン』は、今年最高のビジネス書だと思う。多くの経営書、ビジネス書は「思い込み」か「経営者の自慢話」だったが、本書は一味違う。我々も「なるほど」と唸らされる示唆に富んでいるのだ。
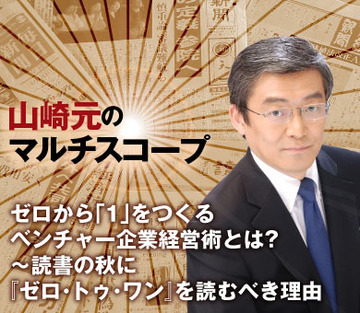
第347回
ざっと1年停滞し膠着していた為替レートと株価が、円安・株高方向に抜けてきた。現状に対して経済界からも警戒の声が出てきたが、この円安・株高は本当に喜ぶべきことなのか。投資家が心得るべき「動き方」を、筆者なりに論じてみたい。
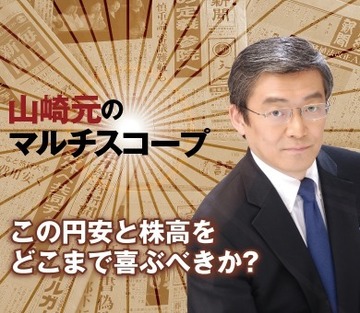
第346回
目先のドル円相場に注目が集まるが、その行方は専門家の間でも意見が分かれる。どんな投資家でも、特定の為替レートの予想が当たることを前提にした賭けは難しい。そうした理由を踏まえて、個人投資家が考えるべき「為替リスク」を説こう。
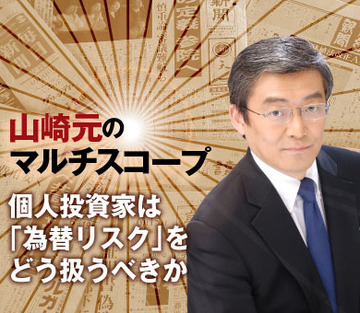
第345回
第二次安倍内閣の陣容で筆者が最も注目するのは、厚生労働大臣に就任した塩崎恭久氏だ。運用通でもある塩崎氏は、GPIF改革に積極的であると目されている。国民は彼に期待していいだろうか。筆者には、この機に提言しておきたいことがある。
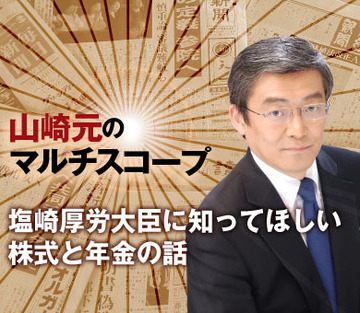
第344回
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が新しい運用計画を発表する目処とされていた9月に入った。日本株に対して、数兆円規模の買いが発生するかもしれない。先んじて具体的な情報も流れているが、そもそもそれらはどこから漏れるのか。
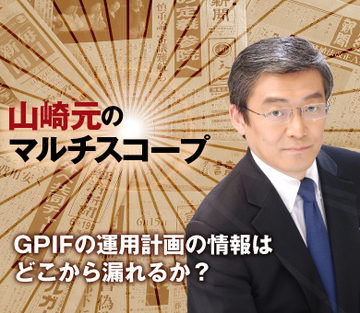
第343回
三大予備校の1つであるあの代々木ゼミナールが、全国の校舎の7割に当たる20校舎を閉鎖すると発表した。背景には、日本の受験生を取り巻く大きな環境変化もある。代ゼミの決断から、縮小する市場で生き残るための経営戦略の在り方を読み解こう。
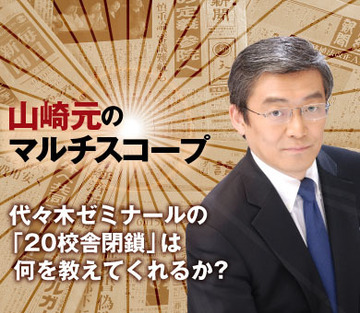
第342回
最近世間では、ROE(自己資本利益率)を流行らせようとする風潮が見られる。だが、株主に企業がどれだけ報いているかは、純利益そのものの水準や変化、株主にとってのリターンなどで評価する方が直接的だろう。“ROE教”をこっそり笑おう。
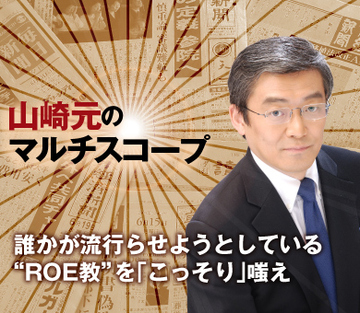
第341回
牛丼チェーン「すき家」の長時間労働問題で、第三者委員会の調査報告書が発表された。従業員の待遇改善への提言も発表されたが、それで十分かどうかは意見が分かれるだろう。「すき家」に対する不買運動の可能性について、考えてみたい。
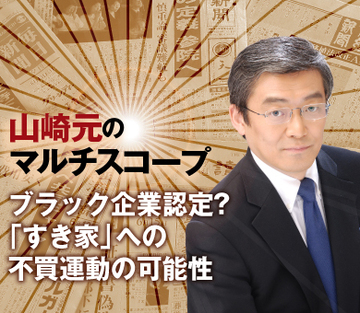
第340回
課題が指摘されるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)のあるべき運用・組織体制とは、どんなものか。GPIFの前運用委員で経済学者の小幡績氏の新著には、そのヒントがたくさんある。小幡績氏と筆者の見解の一致点・相違点を基に論じたい。
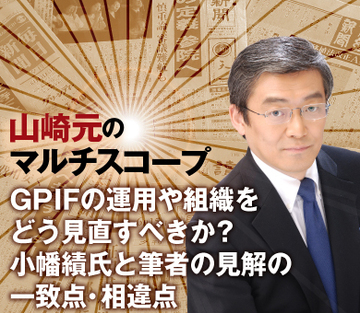
第339回
『週刊ダイヤモンド』7月26日号の特集では、グローバル金融規制強化でビジネス環境が変わる投資銀行業界を取り上げている。筆者は投資銀行に勤めていたこともあり、大いに関心を持っている。その最新事情は、いったいどうなっているのか。