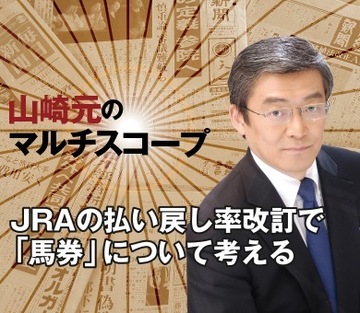山崎 元
第338回
ベネッセコーポレーションの個人データ漏洩が、大問題となっている。この機に考えたいのは、ビッグデータ時代に業者の様々なマーケティング手法によって、我々の個人情報が取得されている不気味さだ。賢い消費行動の基礎知識をお伝えしよう。
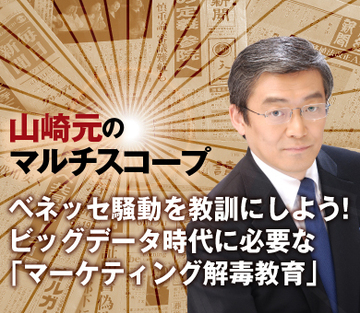
第337回
先頃金融庁が発表した試算は、2003年度から2013年度にかけて、投資家が仮に2年ごとに売れ筋投信に乗り換えた場合、投資した資産が3%減っただろうという無残な内容だった。金融庁もイラ立つ、投信の乗り換え勧誘を抑止する法を考えよう。
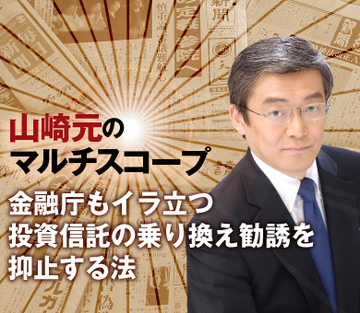
第336回
6月初旬に発表された公的年金の財政検証結果では、複数のシナリオが発表された。政府にとって、批判の的を絞りにくくしたことと、将来の環境悪化に対する事前の言い訳の2つの意味がありそうだ。その前提からは「灰色の未来」が垣間見える。
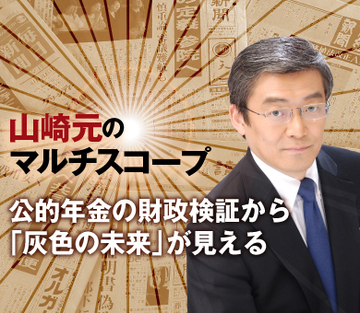
第335回
東京都議会で質問中の女性都議に対して、セクハラと受け取られるやじを飛ばした男性都議がいたことが、大問題となっている。この「都議会やじ問題」を教訓に、ビジネスパーソンも気をつけるべき、セクハラ・リスクの測定と管理について考えよう。
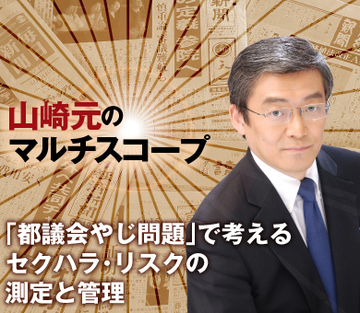
第334回
安倍政権がまとめつつある「成長戦略」には、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の運用改革が組み込まれている。これが日本の成長戦略とは情けない。筆者は、GPIFは株式を買い増ししない方がいいと思う。「5つの理由」を挙げてみたい。
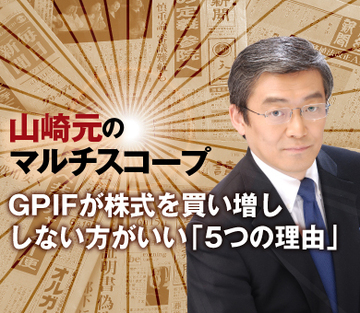
第333回
政府は非正規社員の待遇改善や正社員への登用を進めるため、非正規雇用労働者を対象とした資格制度を創設する方針を固めたという。筆者は、この資格制度は無駄であり上手く行かないと考える。最もよい評価方法は「試しに使ってみる」ことだ。
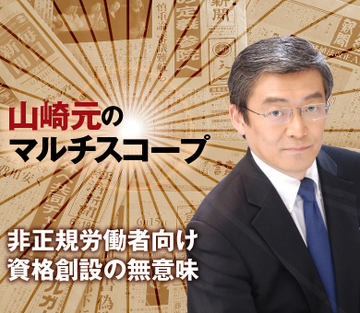
第332回
牛丼チェーン「すき家」の労働環境が、最近話題になっている。店員による深夜の1人オペレーションが取り上げられ、実際には大きな動きはなかったようだが、アルバイトに欠勤を呼びかけるストライキも計画された。今回の騒動の教訓は何か。
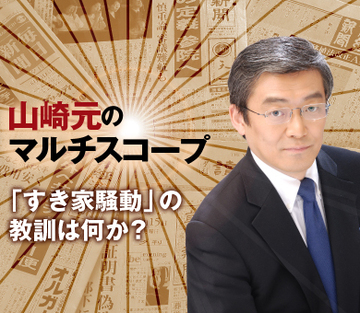
第331回
2014年3月期の銀行決算は、メガバンク、地銀とも過去最高益が続出し、絶好調だった。しかし率直に言うなら、今回の絶好調決算は「一過性」の印象がつきまとう。その理由は、銀行にとって日本国内のマーケットが儲かりにくくなっているからだ。
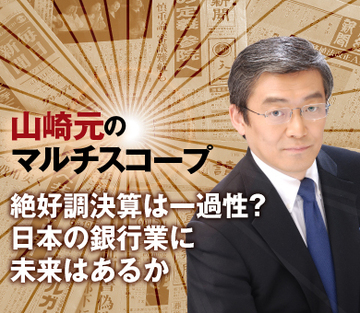
第330回
銀行が保有する自国国債をリスク資産にカウントする国際ルールの導入が、検討されているという。大量の国債を保有する日本の銀行にとっても、影響は大きい。そもそも安全資産と言われている国債は、どの程度安全なのか。徹底検証してみたい。
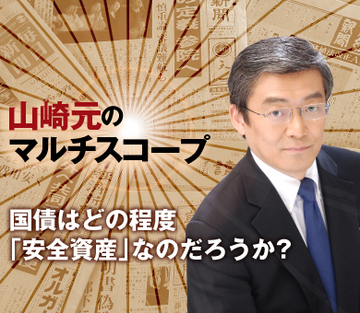
第329回
新社会人にも「5月病」はある。この会社で良かったのか、このままここで働いていていいのかという疑問が湧いて、憂鬱になる人もいる。いずれの場合でも対策があるので、安心してほしい。筆者の経験を基に、その対処法を教えよう。
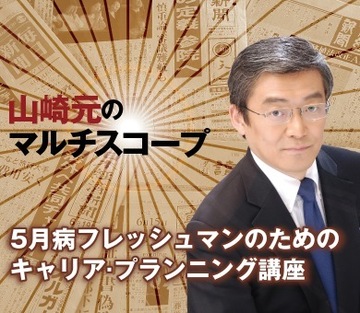
第328回
大学生の来年度就職予定者の就活が、「第二ラウンド」に入りつつある。内定長者もいれば、どこからも内定をもらえずに焦り始めた人もいるだろう。就活中の学生に向けて、就職先を最終的に決定するための考え方をお伝えしたい。
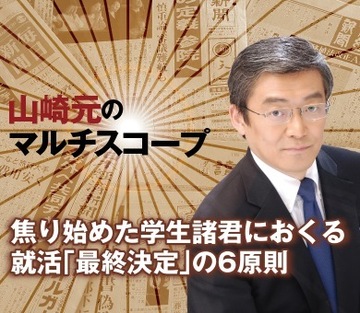
第327回
女性の社会進出によって成長する企業の株を集中して組み入れた「なでしこ」投信など、イメージ訴求型の金融商品が増えている。だが、テーマは投資のポートフォリオを制約してしまいがちだ。金融商品版“キラキラネーム”の課題を考える。
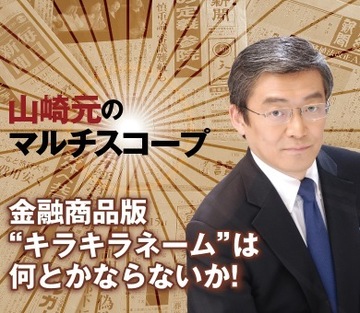
第326回
爆発的とまでは言い難いが、確定拠出年金の普及が進んでいる。現行の制度では、個人よりも企業単位で普及する方が現実的だろう。今回は、確定拠出年金を導入した企業が、どのような運用商品のラインナップをつくるのがいいかを考えてみたい。

第325回
「STAP細胞」の問題に関して小保方晴子氏が記者会見を行った。見ているうちに筆者が思ったのは、現時点で重要なのは、STAP細胞の存否や、小保方氏の責任や貢献への評価ではなく、理研の運営がまともになされているのか否かではないか、ということだ。
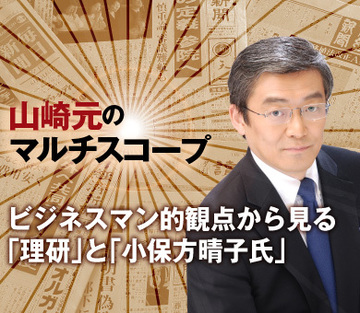
第324回
GPIFの年金運用の方針について、伊藤隆敏東大教授を座長とする有識者会議と、三谷隆博GPIF理事長の見解が、複数の点で鋭く対立している。『週刊ダイヤモンド』の特集記事で紹介された論点に従い、どちらの意見が正しいのかを判定してみたい。

第323回
企業は採用選考の際に、出身大学による差を付けないことが対外的な建前になっているが、関係者間で「学歴フィルター」という言葉は広く用いられているようだ。企業や学生にとっての学歴フィルターの弊害とは何か。その対策を考えよう。
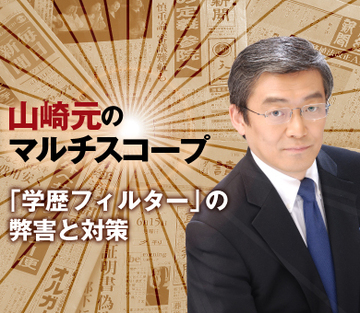
第322回
若い社員は、残業に対して「ブラック企業」に近いイメージを持つかもしれない。一方、残業が多いことを誇らしく思う向きもある。残業のコントロールは、自分自身の自立や成長を促す上でも重要だ。「いい残業」「悪い残業」を考えてみよう。
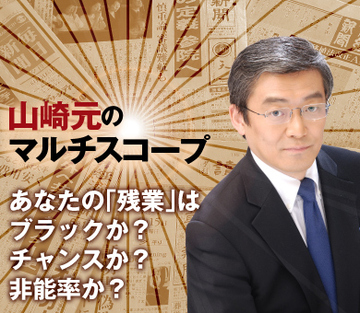
第321回
今週の『週刊ダイヤモンド』の特集は、「速効!『営業』学」だ。筆者は以前から、大学には営業学部が必要だと訴えていたので、特集の内容は興味深かった。だがここには、買い手側の心理と論理の分析が足りない。それを筆者が補講してみたい。
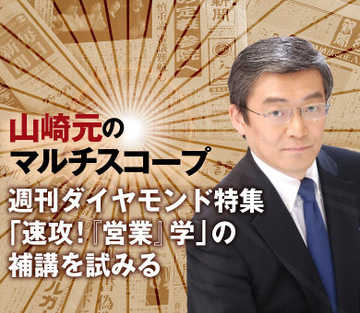
第320回
今、筆者には「嫌な予感」が1つある。それは、公的年金積立金の運用方針変更によるリスク資産の積み増しが、「経済対策」として相場のテコ入れに使われるのではないかという懸念だ。これがアベノミクスの次の手なのだとしたら、がっかりだ。
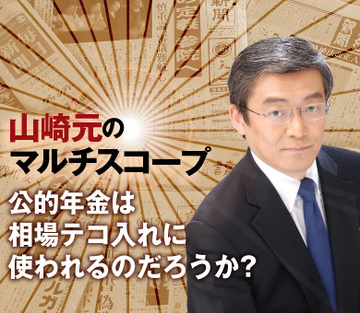
第319回
日本中央競馬会(JRA)は、6月7日から馬券の種類別の払い戻し率を改訂すると発表した。当たりやすい馬券の払い戻し率を上げ、的中しにくい馬券の払い戻し率を下げる改訂だが、彼らは何を狙っているか。また馬券購入者が考慮すべきことは何か。