
山崎 元
第199回
「どじょう内閣」という言葉にも飽きてきた。もともと、どじょう鍋は、何日も続けて食べたいと思うような食べ物ではない。特に、首相の所信表明演説原稿を読み返すと、官僚が脚本を書く田舎芝居の新しい演目に過ぎないことが分かって、早くも「もういい」という気分に傾く。
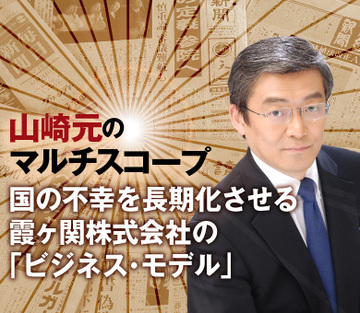
第198回
発足9日目に早くも閣僚の辞任者を出した野田政権。しかし、鉢呂前経産相の言動は辞任に値するものだったのか。筆者は、「結論として辞任は仕方がない」と思ったが、同時に釈然としない思いが残った。
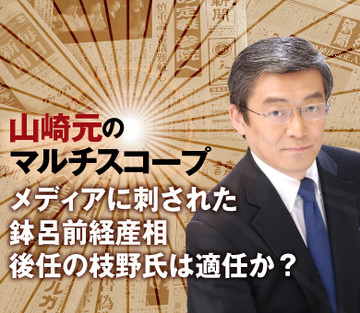
第193回
先日、野田佳彦氏が民主党の代表そして日本の首相に選ばれる様子を見て、筆者が昔書いた、官僚問題に関する懸賞論文を思い出した。

第197回
お金の運用の「目的」にこだわり、これを顧客に語らせようとする金融セールスマンやファイナンシャル・プランナーには気をつけた方がいい。どちらも「使ってはいけないアドバイザー」だ。
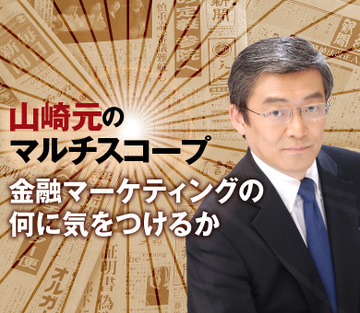
第192回
行動ファイナンスは、認知心理学の成果をファイナンス研究に取り入れた研究分野だが、応用には四つの方向性がある。その知識を個人が使ううえで基本になるのは、自己の非合理な投資行動傾向チェックへの応用だろう。

第196回
野田氏は自ら「シティボーイには見えない」と仰っていたが、世間は彼のことを財務省が育てた「増税ボーイ」と見ている。今回は主にマーケットの立場から野田首相体制について考えてみたい。
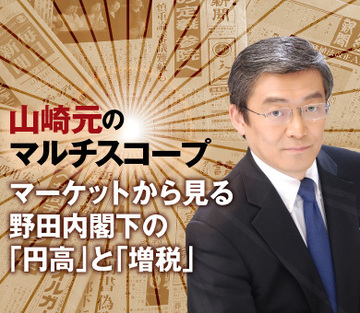
第191回
簡単な問題を考えてみてほしい。あなたは金融機関の窓口で「新しい(魅力的な)金融商品」を勧められたとする。取るべき対応として正しいのは次のどれか。

第190回
米国債デフォルトの可能性をきっかけに円高が進んだ。本稿執筆時点では、対米ドル76円台で推移している。今後を考えてみよう。

第195回
子ども手当は、一見すると、「大きな政府」的な政策に見えるが、実は官僚機構による裁量的な支出を、単純なルールに基づく非裁量的な経済力の再配分に置き換える「小さな官僚政府」を目指す政策である。だからこそ、子ども手当は、官僚の敵なのである。
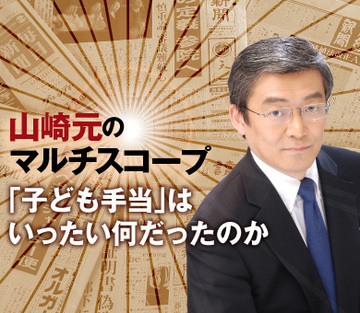
第194回
これから首相になる人物には、鳩山・菅時代の失われた2年間を取り戻す政策の実行を期待したい。この際に頼るべきは、あらかじめの大連立政権といった枠組みではなく、個々の問題について国民に広く議論を晒すことによる支持の獲得だ。
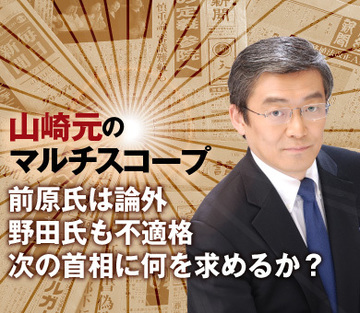
第193回
流動性の罠の状況に関しては、日本の方が米国よりも先輩であり、長きにわたってデフレに陥っている点を考慮するとより重症の先輩患者だ。新しい「病友」が何を考えているのかを見て、また、先輩患者としてアドバイスができないのか、考えてみよう。
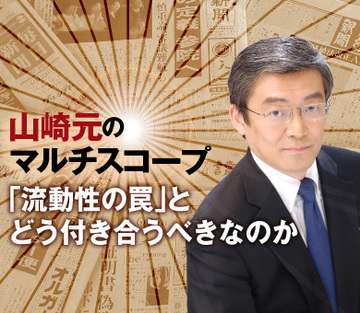
第189回
タイトルに「さよなら」と付けたものの、通貨選択型投資信託はブームの真っ最中だ。しかし、筆者は、正しい理解を持たない顧客が多く買っていることを思うと、この種の商品を制度的に規制してもいいとさえ思っている。投資家は相手にしないのがいちばんいい。

第192回
まさか、あの場面で泣くとは思わなかった。海江田万里経産相は、7月29日の衆議院経済産業委員会で泣き崩れる場面があった。はたして、この場面で泣く人物に、収束しない原発事故やTPPなど大きな問題が目白押しの経産大臣を任せていていいのだろうか。
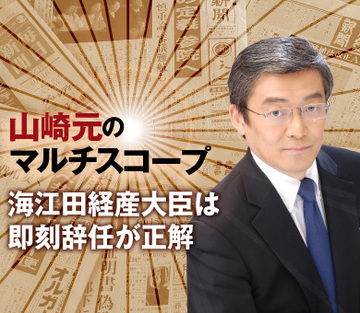
第188回
債券は、多くの場合金利が年率○.○%と決まっていることもあり、一見、親しみやすい投資対象だ。慎重なマネー初心者に適した投資対象のように思えるかもしれないが、どうなのか。

第191回
議会と政府の債務上限引き上げ協議が順調に進まず、米国債が一時的な利払いの遅延などの「デフォルト」(債務不履行)に陥る可能性が出てきた。仮にそうなった場合、何が起こるのか、日本への影響を含めて、短期と長期の視点で考えてみよう。
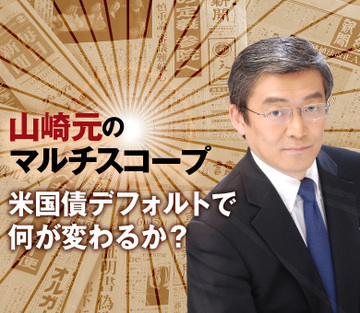
第187回
「日本経済新聞」(7月4日朝刊)に、「長期の外貨投資 『購買力平価』軸に」(編集委員 田村正之)と題するよい記事が載っていた。

第186回
人生全体を通じた経済生活の豊かさに影響を及ぼす要因は何だろうか。一般に大きいと思われる順に挙げてみたい。

第190回
個人の資産運用にあって、外貨建て資産への投資知識は「普通のこと」から「避けられない常識」になりつつある。週刊ダイヤモンド最新号の特集「為替投資入門」を参考にしながら、勘所を押さえておこう。
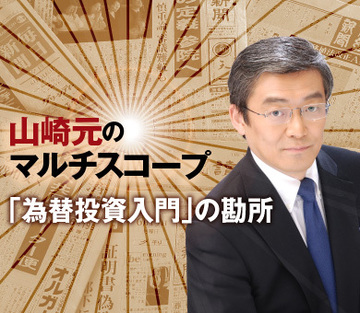
第189回
暑い夏の最中に起こった「九電やらせメール事件」。結局何が問題だったのかを考えると、リスク感覚なき電力会社の経営と共に、多数決のアンケートに頼る議論なき民主主義のお寒い現実が見えてくる。
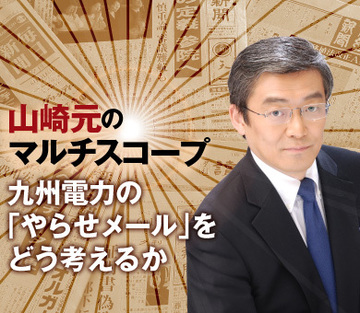
第185回
以前、このコラムでブログを使った運用サービスの可能性について書いた。模擬ポートフォリオをブログで公開し、管理者と読者がやりとりしつつ、読者が自分の資金でこのポートフォリオを適宜まねする構想だった。これは現在も今後も可能だ。
