
情報工場
第58回
京都大学は自由を重んじる学風で知られる。京大は科学技術分野では日本で最多のノーベル賞受賞者を輩出しているがいずれもそれまでにない独自の着眼点による研究成果が評価されての受賞だ。京大の研究者たちがユニークなのは、「考える」だけでなく「深く考える」習慣が身についているからだという。「考える」と「深く考える」の違いは何か。

第57回
「素人」の柔軟な発想で斬新なアイデアを出し、そのアイデアを実行する方法を「執念深く」試行錯誤を繰り返して「インスタントラーメン」を発明した日清食品の創業者・安藤百福。世紀の大発明に繋がった研究開発のプロセスは、現代のシリコンバレーの雄とも共通する優れたイノベーション手法だった。

今回、SERENDIP導入企業のうち時価総額2000億円以上の優良企業60社の幹部・管理職が、2017年度上半期に閲覧したダイジェストのランキングを作成。日本経済を牽引し、次世代のビジネスを創り出し、イノベーションを起こすことを求められている企業の経営幹部・管理職たちは今、どんな情報を求めているのか。トップ3にランクインした書籍を紹介しよう。

第56回
謝罪会見は、不祥事を起こした企業や有名人が、世間に「謝罪」するために開かれる。顧客やファンだけでなく、直接は関係のない世間一般の人々も謝罪の対象であり、状況を説明するなどして皆の怒りを鎮めるのが大きな目的となる。しかし会見を開いてもSNS上で「炎上」を招くことが多いのはなぜか。

組織全体の生産性を上げるために企業は人材をどう活用すべきか。ある調査によると優良企業と一般的な企業とでは優秀な「Aクラス人材」の人数はほぼ変わらないという。では、優良企業とそうでなく企業を分けたものは何か。「適材適所」である。優良企業では、Aクラス人材に力を発揮できる環境を用意している。

第54回
650年の伝統を誇る「能」。能の舞台はとても簡素だが、そこに観客各々の幻視を重ねられるような仕掛けになっている。何かに似ていないだろうか。そう、AR(拡張現実)やMR(複合現実)といった先端技術にそっくりなのだ。

第53回
失敗する新規事業は、事業の「アイデア」を思いつく。次にアイデアを形にするべく「商品化」を始める。そして「ブランド」を作る。以上すべてが揃った後に「顧客」を求めて営業を始める。この「アイデア」→「商品化」→「ブランド」→「顧客」、という順序が問題なのだ。その結果、多くのスタートアップは「絶望のループ」に陥ってしまう。

第52回
ビジネスや日常生活の中で、相手の言葉(日本語)が理解できなかったり、自分が意図した通りに相手に伝わらず、もどかしい思いをしたことが誰しもあるだろう。議論がかみ合わないまま会議が終わってしまったなどの経験もあるのではないか。そんな経験がひんぱんにあるという人は、実は国語の基本を身につけられていないのではないだろうか。
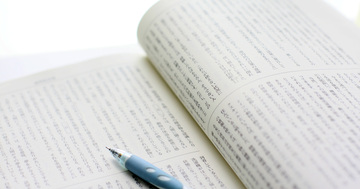
第51回
日本のものづくりの低迷が叫ばれて久しいが、それは電機産業のみにフォーカスを当てた主張だろう。自動車産業はまだ健在だ。トヨタ自動車には、有名な「トヨタ生産方式(TPS)」がある。これが同社の競争力の源泉であるのは間違いない。だとすれば、苦境にある電機産業をはじめ、日本の製造業全体がもっとTPSを学べばいいのではないだろうか。

第50回
超高齢化と言われる日本の年齢別人口分布グラフは逆ピラミッド型になる。このグラフをひっくり返してみるとどうだろう。多数の高齢者の層が、若年層を下支えする正のピラミッド型の、安定したグラフが出現する。若者が高齢者を支えるのではなく、高齢者が若者を支える。そんな「逆転の発想」に日本の未来を拓くヒントがあるのではないか。
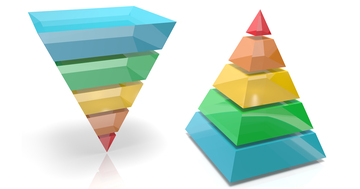
第49回
新しい技術が登場し普及していくと、その技術を活用して生産性を高めたり、生活をより便利にしようとする人々や企業が必ず出てくる。そして、そのための「新しい仕事」が生まれる。これから10年後にどんな「新しい仕事」が生まれているのか、想像してみると面白い。

第48回
ヤマト運輸は「働き方改革」に取り組むと発表。「デリバリー事業の構造改革」と銘打った改革案は、現場社員の労働環境の悪化に対応するものだ。だが、本書の著者、松岡真宏氏と山手剛人氏は、今、示されている対策では「宅配問題の根底にある『構造』には少しもメスが入らない」と指摘。今回の宅配をめぐる問題は「同時性解消」の視点から考えるべきと主張している。

第47回
本書『フェイスブック 不屈の未来戦略』の著者、ホフリンガー氏は、ザッカーバーグ氏率いるフェイスブックが「世界をよりオープンにつなげる」ために取り組んできた活動を目の当たりにしてきた。そして、フェイスブック創業以来のそれらの取り組みの歴史を追いながら、同社が急成長した秘訣を10の教訓にまとめている。そして、フェイスブックが今後どのような戦略でミッションを追求していくのか、という未来構想についても解説している。

第46回
今後は大量生産型ではなく顧客の個別ニーズをくみ取った商品やサービスづくりが主流になる。それを踏まえた戦略策定と実行は多くの企業の急務だ。そのための強力なヒントになるビジネスモデルが、実は意外なところにあるのをご存じだろうか。350年の伝統を誇る京都・花街(花街)の「お茶屋」である。

第45回
最近、レンズ付フィルムの「写ルンです」が売れている。「写ルンです」の機能やデザイン自体は大きく変わったわけではない。なのに勝手に売れ始めた。つまり、ユーザーがその商品に、メーカー側も想定していなかった「新たな意味」を見出した結果、再び売れるようになった。この現象はなぜ起こったのか。

第44回
バルミューダの家電は常識を覆すこだわりの製品ばかりだ。そのバルミューダ率いる社長の寺尾氏は、数年後の素晴らしい日々を待つのも、将来の計画を立てるのもいいが、「今日がお祭りの当日であり、今がフィーバータイムの真最中ということを忘れるな」と説く。生きているうちにどうしてもやりたいことがあるなら、今日始めろ、というのだ。

第43回
「一人だけで完結する仕事」など、この世の中に存在するのだろうか。仮にあったとしても、一人だけで完結できた仕事によるアウトプットは、十分に質の高いものにはならないのではないか。

第42回
原発子会社の巨額損失などにより経営危機に陥った東芝が、半導体事業の事業売却手続きを進めている。かつて日本のお家芸であった半導体で、東芝の半導体は日本にとって最後の砦でもある。だが『日本の電機産業失敗の教訓』の著者の佐藤文昭氏は、意外なことに「東芝は一刻も早く半導体事業を完全売却すべきだ」と、同社の事業売却に肯定的だ。その真意はどこにあるのだろうか。

第41回
「人工知能(AI)の進化が人間の存在を脅かすのでは?」といった話題を、最近よく耳にするようになった。「将来人間はAIに仕事を奪われてしまうのではないか」と懸念する向きもある。AIは人間にとってどの程度脅威なのか?

第40回
「開運!なんでも鑑定団」をはじめ、テレビ東京は他局にはない独創的なバラエティ番組をたくさん放送している。その独創的な番組作りの秘訣はどこにあるのだろうか。
