吉田陽介
最近、中国で「代行サービス」が急増している。忙しい顧客の代わりに、日常生活の諸々の用事を引き受けるものだ。なかには日本人には想像もつかないことを代行するケースもある。モラルの一線を越えやすい「代行経済」の光と影を考える。

10月1日に建国70周年を迎えた中国。中国共産党は「初心忘れず、使命を胸に刻む」を強調し、毛沢東ら過去の指導者の思想を学ぶことを提唱している。習近平の政策にも毛沢東の影響が見えるなか、これから中国で「毛沢東化」は進んでいくのだろうか。

独身者が2億2000万人もいる中国。なかでも、交際している人がいない未婚の20~40歳の大卒の若者は76.4%に達し、日本さながらの「おひとり様消費」を盛り上げているという。なぜ彼らは独身貴族を続けるのか。背景には中国ならではの事情があった。

アメリカが中国に対して関税引き上げを予告した後、中国メディアは速報を出した程度で、ほぼ「沈黙」を守り、トランプ政権を批判するような論評を掲載しなかった。「強硬」色を薄めている習近平の本心は、米中貿易戦争を避けることに他ならない。
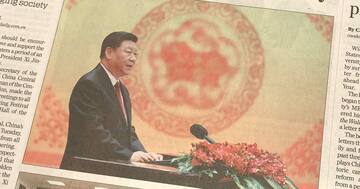
中国の国会に相当する全国人民代表大会(全人代)が始まり、「政府活動報告」の内容に注目が集まった。習近平・国家主席はその中で「危機」を素直に認めた。その狙いは何だったのか。

北京に近い河北省で、金曜日の午後から日曜まで休むという「2.5連休」政策が実施に向けて動いている。しかし、この政策はこれまでもあったのだが、まだ普及していない。何が問題なのか、そしてどうすれば普及するのだろうか。

中国の経済発展に大きく寄与した「改革開放」政策が始まってから40年。習近平国家主席は世界2位の経済大国となった成果をアピールした。だが、経済政策は後退しているようにも見える。習国家主席は何を目指しているのだろうか。

10月25~27日にかけて行なわれた安倍晋三首相の訪中は、“友好のバロメーター”といわれる両国首脳の相互訪問が再開したこともあり、両国関係の改善をさらに印象づけられた。その背景には、中国の思惑が隠されていた。

7月3日、サッカーワールドカップでベルギー代表に敗れたサッカー日本代表。彼らが試合後に取った行動を、中国の市民たち称賛している。だが、これは逆に中国人のマナーの悪さを浮き彫りにしたかたちだ。

5月8日から11日、中国の李克強首相が日本を訪問し、天皇陛下を始め、安倍晋三首相や与野党関係者と会談し、両国関係の改善を印象づけた。果たして日中関係は「新時代」に入ることができるのだろうか。
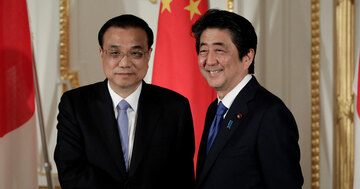
3月5日、中国で第19回党大会以後の全国人民代表大会(全人代)が開幕、憲法改正も審議され、「国家主席・副主席の任期は2年を超えない」という規定が撤廃された。これにより習近平は独裁強化を目指すのだろうか。

中国共産党大会が閉幕、翌日には新指導部が確定し、習近平政権の2期目がスタートした。党改革で成果を収めた習近平は、今後何を目指すのだろうか。それは「新時代の中国の特色ある社会主義」というものだった。その中身を解説しよう。
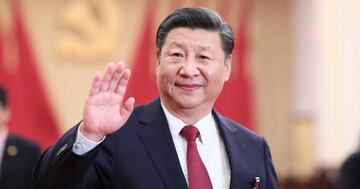
10月18日に開かれる第19回中国共産党大会で、習近平政権は2期目に突入する。共産党内では強硬路線を進めて着々と地盤を築いているが、さらに強固にするための「習近平思想」を導入するのかが注目されている。

「上に政策あれば、下に対策あり」という言葉がある通り、中国人はルールを守らないというのが定説だった。しかし、習近平政権になってから、さまざまなルールが定められ、徐々に変化し始めている。

最近、中国では「25歳で中年の危機」といった言葉をよく目にする。これは、ストレスを抱える中年の危機が、若者にまで広がっていることを指している。なぜそうした事態に陥っているのか探った。

中国社会に「睡眠不足」が広がっている。「2017年中国青年睡眠現状報告」によると、調査対象の76%が「なかなか寝付けない」と回答している。その一方で、睡眠について「全般的によい」と答えたのは24%で、「規則正しい生活を送っている」と答えたのは、わずか5%にすぎなかった。

中国の政府機関紙に趙宏偉・法政大教授が寄せた文章が中国国内で注目を集めた。趙氏は「93%の日本人は中国が嫌い」という調査数字を基に、日本に旅行する中国人に疑問を投げかけた。
