デロイト トーマツ グループ
「(日本は)居心地のよい場所にとどまり続けるとゆでガエルになる。今を変化のチャンスとしたい」――。今年1月に行われたオンライン版ダボス会議「ダボス・アジェンダ」におけるパネル「Japan's Great Reset」で、SOMPOホールディングス社長、櫻田謙悟氏はこう述べた。世界がステークホルダー資本主義へと向かう中、日本が「グレート・リセット」(大転換)を実現できず、「失われた30年」から抜け出せないのでは、という危機感がにじみ出た発言だった。あれから8カ月がたち、日本企業は行動を起こしているのだろうか。

あらゆるステークホルダーの利益を考慮する「ステークホルダー資本主義」が、全世界に広がっている。これまで欧米の株主偏重の考え方に違和感を覚えていた日本のビジネスパーソンから聞こえてくるのは、「やはり自分たちが正しかった」「これまで通りでよいのだ」との声だ。しかし、本当にそうであろうか?――というのも現在の日本企業は、こうした指摘とは逆のことが起きている。株主や投資家の存在が、かつてないほど大きくなっているのだ。

サイバー戦争の勃発が現実味を増している。激化するサイバーの脅威から日本も逃れることはできない。自国のインフラや企業を守る上で重要なのが「サイバー抑止」という安全保障の考え方だが、これをひもとけば国家が企業を守り切れない現実が浮かび上がる。

近時、スマート○○という単語が世の中にあふれている。スマートエネルギー、スマートモビリティ、スマートヘルス、スマートペイメントなどがあるが、それらを総括した概念としてあるのが、今回取り上げる「スマートシティ」である。
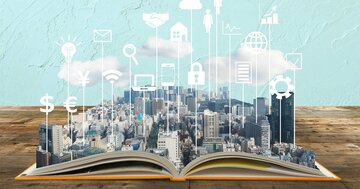
2021年5月初旬、米バイデン政権は新型コロナウイルス・ワクチンに係る知的財産保護義務の一時免除に前向きな姿勢を示す驚きの行動に出た。「知財」を通商戦略の柱にしている米国にとって、この動きはかつてない変化だ。その変化の意味を理解しなければ、コロナ禍で激変する世界の競争ルールを読み解けない。

女性の活躍や外国人人材の登用など、日本企業では昨今、さまざまな取り組みがなされている。しかし、それらはステークホールダー資本主義時代に向けてアップデートされているだろうか。企業の責任は、経済的価値のみならず社会的価値の創出へと拡大しているのだ。経済的価値を重視したダイバーシティ&インクルージョン(D&I)から、社会の公器としての“DEJI” (Diversity, Equity, Justice and Inclusion)への進化が求められている。

世の中はSDGsブームに沸いている。SDGsを特集した雑誌は異例の重版が決定し、テレビは連日、SDGsに関する取り組みを紹介している。最近ではSDGsをキーワードにした就活イベントや特集サイトまで組まれている。

近年の脱石炭火力発電、脱プラスチック製品等に代表されるように、日本企業視点から見ると「突然」の環境変化の対応に追われるケースが見られる。「ここまでサステナビリティーの圧力が強くなるとは思いもしなかった」と戸惑う経営者も多いだろう。しかしその背後にある現象をつぶさに見ると、こうした事例は「突然」ではなく「必然」だったことがわかる。

2015年、世界の経営者の間に激震が走った。ハーバード大学ビジネススクールが出す世界経営者ランキングで、2014年まで1位だったAmazon社ジェフ・ベゾス氏が87位に転落したのだ。1位になったのは、ラース・レビアン・ソレンセン氏。日本ではあまり知られていないデンマークの製薬会社Novo NordiskのCEOだった。

ステークホルダー資本主義に基づくESG(環境、社会、ガバナンス)やパーパス経営といったビジネスの在り方は、今や世界の経営者の常識となっており、既に名だたる大企業が実践に移行している。こうした新たな潮流の背景や、それが企業にもたらす影響を分かりやすく解説する。
