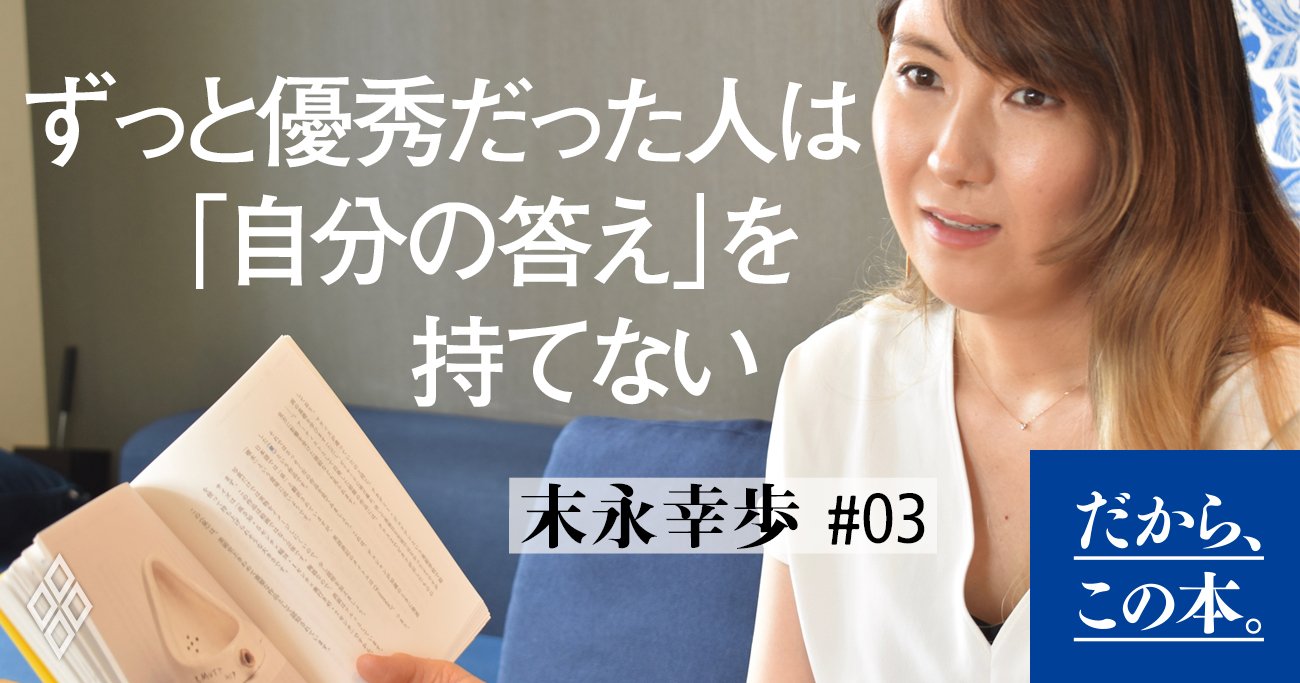
多くのビジネスパーソンから注目されている『13歳からのアート思考』。世の中が大きく変わろうとしているいま、「求められる力」も当然変わってきています。
それを育む「アート思考」とはいったい何なのか?
なぜアートが「現代に求められる力」と結びつくのか?
そんな「いま」という時代と「アート」との関係を、20世紀のアート作品を紐解きながら、著者であり、現役美術教師でもある末永幸歩さんに聞いてみました。全4回のインタビュー記事の第3回。
(取材・構成/イイダテツヤ、撮影/小杉要)
優秀だった人ほど、自分の答えを持てない
――「アート思考」が注目される背景には、やはり時代の変化が影響していると思うのですが、学校の教育現場では、そういった時代の変化に対応できているのでしょうか?
末永幸歩(以下、末永) 多くの方がおっしゃっているように、いま、世の中は大きく変化していて、「必要とされる力」も変わってきていると思います。
戦後の高度成長以来、求められてきたのは「正解を見つけ出す力」や「課題解決」、そういった力だったじゃないですか。それはきっと「みんなが求める目標」「指標」「価値観」などが統一されていたからだと思うんです。
でも、いまの世の中は価値観がどんどん多様化して、変動も激しいので、そもそもの正解自体も変わっていってしまいます。そんな世の中で、正解を追い求めていくのは限りなく難しいし、無意味でもあると思っています。
だから、いまの時代に必要なのは「正解を見つけ出す力」とか「課題解決」じゃなくて、むしろ「価値を生み出す力」とか「意味を作り出す力」、もっと柔らかく言えば「自分だけの答えを見つけ出す力」。そういうものなのかなとは感じています。
この話を教育という分野に当てはめていくと、そもそもいまの教育システムは19世紀、産業革命の頃の西洋社会をベースとしていて、そういう背景で枠組みが作られているんですよね。
産業革命の時代ですから、学校教育によって産業を発展させて、国を発展させていく、という思いが前提にあります。大げさに言うと「工場の機械のような人間」をたくさん生産するという目的が、本来的にはこのシステムにあるわけです。
そういう状況では、やはり「正解をいち早く導き出す力」とか「課題を最短ルートで解決する力」が求められて、非効率なものがことごとく排除されていきます。たとえば、「疑問を持つこと」や「質問をすること」って、工場のなかでは非効率なので、排除されるべきものじゃないですか。
 末永幸歩(すえなが・ゆきほ)
末永幸歩(すえなが・ゆきほ)美術教師/東京学芸大学個人研究員/アーティスト
東京都出身。武蔵野美術大学造形学部卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科(美術教育)修了。東京学芸大学個人研究員として美術教育の研究に励む一方、中学・高校の美術教師として教壇に立つ。「絵を描く」「ものをつくる」「美術史の知識を得る」といった知識・技術偏重型の美術教育に問題意識を持ち、アートを通して「ものの見方を広げる」ことに力点を置いたユニークな授業を、都内公立中学校および東京学芸大学附属国際中等教育学校で展開してきた。生徒たちからは「美術がこんなに楽しかったなんて!」「物事を考えるための基本がわかる授業」と大きな反響を得ている。彫金家の曾祖父、七宝焼・彫金家の祖母、イラストレーターの父というアーティスト家系に育ち、幼少期からアートに親しむ。自らもアーティスト活動を行うとともに、内発的な興味・好奇心・疑問から創造的な活動を育む子ども向けのアートワークショップ「ひろば100」も企画・開催している。著書に『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』がある。



