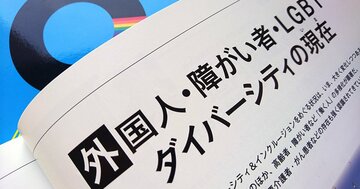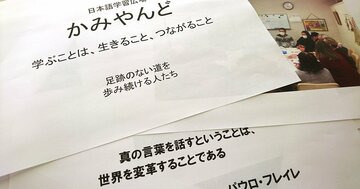「ゆるスポーツ」がかき混ぜはじめた境界線とは?
澤田さんが行っている“脱力系でローカロリーな福祉プロジェクト”のひとつが「ゆるスポーツ」だ。
運動が苦手でも、目が見えなくても楽しめる、まったく新しいスポーツ。既存のスポーツのように勝利至上主義だけじゃない、だれもが楽しめるようなスポーツ。そんなスポーツがあればいいんじゃないか──。そして2015年、自分という弱者救済のために「世界ゆるスポーツ協会」を立ち上げました。ハンドソープボール 、イモムシラグビー、ベビーバスケ……。 「スポーツ弱者を、 世界からなくす」ことをミッションにつくりはじめた「ゆるスポーツ」は、簡単に言うと「勝ったらうれしい、負けても楽しい」「運動音痴の人でもオリンピック選手に勝てる」「健常者と障害者の垣根をなくした」新しいスポーツで、これまでに90競技以上を考案して、10万人以上の方に体験してもらいました。
(本書より)
澤田 いろいろなプロジェクトを同時並行しながら、マジョリティとマイノリティって、人工的な線でスパッと分けられるものではなく、むしろ、すべての人の中に、両者は共存しているということを教えてもらったんです。
で、僕の中にいたのが、「極度の運動音痴」というマイノリティだったんです。小学生のときから体育の時間が大嫌いでした。足は遅いし、球技となると「澤田が決めたら、倍の点数な」とハンデをつけられる始末。なぜ、人間は間違える生き物なのに、体育の時間だけは一切のエラーを許されないのか――納得がいかないまま大人になり、僕は「スポーツができない」という弱さをひた隠しにして仕事に打ち込みました。ところが、福祉の世界に飛び込んでみて、「医学モデル」「社会モデル」という考え方があることを知ったんです。
たとえば、脳性まひで車イスを使っている人がいたときに、「日常生活が大変なのは、あなたに原因がある。だから、リハビリして、あなたを『健常者化』しましょう」というのが医学モデル。一方で、「日常生活が大変なのは、社会に原因がある。だから、段差をなくしたり、エレベーターを設置したりしましょう」というのが社会モデル。
これを知ったときに、「あ!」と思ったんです。体育が苦手なのは自分のせいだと思ってきたけど、「社会モデル」で捉え直すと、ひょっとして、「僕じゃなくて体育のほうが悪かったんじゃない?」。衝撃的な発見でした。
そして、「運動音痴」というネーミングを変えられないか?と思い、「スポーツ弱者(Sports Minority)」という言葉を考えました。すると、ただの運動音痴だった僕が、なんらかの外的要因でやむを得ず「スポーツをできない状況に陥ってしまった人」に見えてきたんです。それに、息子だって、同じくスポーツ弱者。目が見えないと、どうしてもできるスポーツは限られています。 「僕らはスポーツ弱者なんだ」。そう口にすると、世界が変わる予感がしました。
折しもそのタイミングで、東京2020オリンピック・パラリンピックの招致が決まりました。どうせ盛り上がるに決まっているお祭り。だったら、爪を噛んで外から眺めるよりも、思い切ってその中にダイブできないか。息子と、誰よりも自分のためにもやるしかない。こうして、清水の舞台から飛び降りる覚悟で、スポーツの世界に踏み込むことにしました。
「ゆるスポーツ」の競技とは、具体的にはいったいどのようなものなのだろう?
澤田 たとえば、「ベビーバスケ」という競技があるんですけど、ボールにセンサーとスピーカーが仕込まれていて、強い衝撃を検知すると「えーんえーん」と赤ちゃんのように泣き出してしまうんですね。ボールを泣かせてしまったら、容赦なく相手ボール。パスもそっとキャッチしなければならないし、ドリブルなんてもってのほかです。すると、どんなにバスケがうまい人でもスピードを封じられるので、みんな平等に下手になります。むしろ、球技のうまい人ではなく、「母性のある人」のほうが有利になる仕組みです。
実際、Bリーグ(日本プロバスケットボールリーグ)のファン感謝イベントでベビーバスケを行うと、身長2メートル近くある選手よりもファンのほうがうまいときがあります。
こんなふうに、いままでのスポーツ(競技)ではヒーローになり得なかった人が、「ゆるスポーツ」の中では輝いていきます。
一般的に、スポーツ(競技)というものは、「完成されたもの」と思われています。なので、既存のルールを守ることがなにより重要視されていますよね。だから、「ゆるスポーツ」に接した人たちは、「スポーツって、自分たちで作ってもいいものなんだ」とびっくりします。
スポーツに限らず、社会の仕組みも、完成型に見えてまだまだ未完成のサクラダファミリアみたいなものですよね。
アート作品を見た瞬間、それまで考えていなかったことに疑問を持つ経験がありますが、そうした意味で、「ゆるスポーツ」はアート的な存在と言えるかもしれません。
これまでのスポーツは、スポーツ強者を起点に進化してきたので、限られた人しか活躍できませんでした。だから、強者と弱者の間にある溝が年々深くなっていった。でも、既存のルールでは能力を発揮できない人でも、新しい前提条件をつくることによって、だれもがヒーロー、ヒロインになれる可能性がある。
ゆるスポーツは、強者と弱者の溝を、あるいは健常者と障がい者の壁を、スポーツで問い直しています。障がいの有無がリセットされ、ヒエラルキーがなくなり、バリアがフリーになる。ある意味、「オリンピック」と「パラリンピック」で分断されていた健常者と障がい者が、自然と交わることができる。「心にバリアフリーを!」なんてポスターで謳われるより、「イモムシラグビー」を一緒に3分間プレーするだけで、圧倒的に仲良くなることができるんです。
それを知った僕は、改めて「クリエイター」という仕事の役割を認識しました。この社会に、新しいアイデアで、新しいスタートラインを引く。それこそが、「クリエイター」と呼ばれる僕らの仕事なんだと気づいたんです。