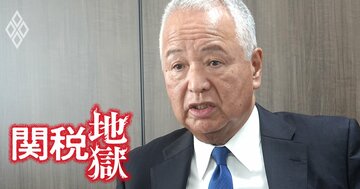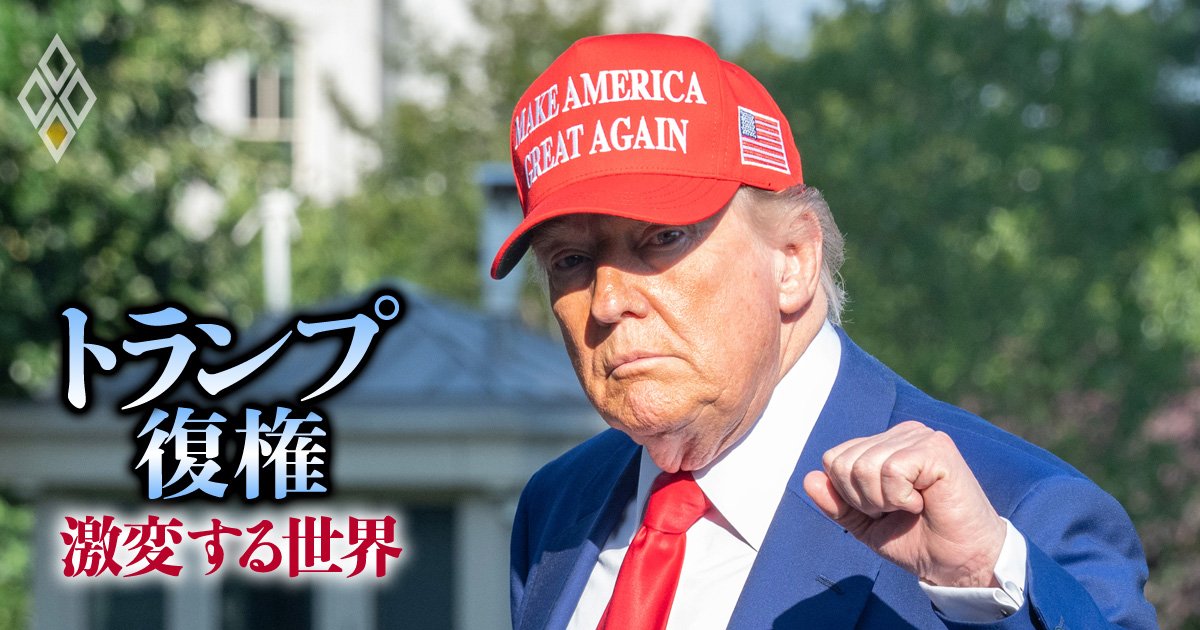 Photo:Bloomberg/gettyimages
Photo:Bloomberg/gettyimages
7回目関税見直し交渉も合意できず
米国は相互関税一時停止の延長を示唆
トランプ関税を巡る日米の関税見直し交渉は長期化の様相だ。
日本政府は、6月のカナダでの主要7カ国首脳会議(G7サミット)に合わせて日米関税交渉の大枠での合意を目指すシナリオを描いてきたが、6月16日、サミットの際に行われた石破茂首相とトランプ米大統領の首脳会談は不首尾に終わった。
26日には赤沢経済再生相が7回目の協議のため訪米、ラトニック米商務長官と交渉を行ったが、合意の目途はたたないまま、7月3日からは日本は参院選に突入した。
一方で米国側からは、相互関税の上乗せ分の一時停止期間を7月9日から延長する可能性が示唆され、ベッセント財務長官は、具体的な国などには言及しないものの、最終的には「レーバーデー」の9月1日までに交渉を完了させる考えを語っている。
トランプ大統領は7月1日には、日本との交渉の難航について「合意できるのかは疑わしい」と語り、「30%から35%」の関税を見切り発車で課す可能性に言及するなど、日本との早期合意は遠のく情勢だ。
交渉がまとまらない背景には、日本側が最重要視する自動車25%関税の撤廃や、貿易不均衡を巡って米国IT企業などが稼ぐ「デジタル黒字」をどう評価するかなどで、日米の主張になお隔たりがあるからだ。
現状では関税引き上げに対して多くの日本企業が当初対応策として挙げていた米国での販売価格の引き上げはそれほど行われておらず、日本企業が関税負担分は日本企業がかぶっている状況だ。
だが交渉長期化となれば、日本企業の「値上げ回避」の戦略も限界になるだろう。価格転嫁が始まれば米経済もインフレが再加速する懸念がある。一方で、価格転嫁を回避し続ければ、国内の下請け企業などに徐々にそのしわ寄せが及んでくることになるだろう。
見直し交渉が長期化すればするほど、日米双方にとって難しい局面になる。