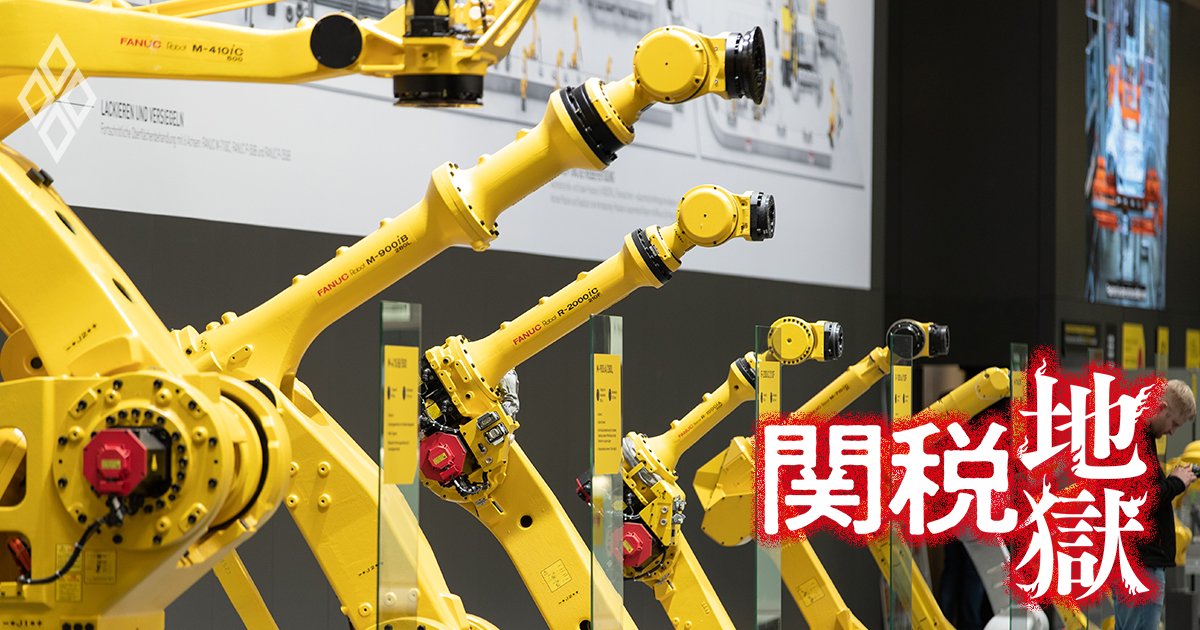1990年代から2000年代にかけての本格的なグローバル化、2000年代からのIT化、その後現在に至るまでの急速なデジタル化という変化の大波の中で、日本企業の多くは辛酸をなめてきた。一方、デジタル化によってサイバー(データ)とフィジカル(モノ)の世界が結び付く「インダストリー4.0」が動き出し、製造業は大変革の局面を迎えている。その先駆者としてDXに挑んできた小松製作所や東芝の事例をひも解きながら、日本の「製造業DX」のあり方、組織変革や人材育成について議論する。
※当コンテンツは、2022年3月3日に開催されたダイヤモンドクォータリー創刊5周年フォーラム第2弾「日本型『製造業DX』 人間とAI・デジタル技術の共進化」のパネルディスカッション内容を採録したものです。
3つの事例が示す
コマツのDXの進化プロセス
 <モデレーター>
<モデレーター>東京大学大学院 経済学研究科 教授 経営教育研究センター長
新宅純二郎
JUNJIRO SHINTAKU東京大学経済学部卒業後、1993年東京大学経済学博士取得。藤本隆宏氏とともに「東京大学ものづくり経営研究所センター」「東京大学経営教育研究センター」などを立ち上げると同時に、数々の共同研究に取り組んできた。著書に、『日本企業の競争戦略』(有斐閣、1994年)、『中国製造業のアーキテクチャ分析』(共著、東洋経済新報社、2005年)、『ものづくりの反撃』(ちくま新書、2016年)など。
新宅:本日、皆さんに議論していただきたいのは「インダストリー4.0」といわれる潮流の中で、デジタル化によってサイバー(データ)とフィジカル(モノ)の世界をどう連結させて、日本製造業の競争力につなげていくかということです。今回は、3人の論客をお招きしております。最初に、1990年代からコマツのデジタル化を率いてきた野路國夫さんに、事例をご紹介いただきます。
野路:今日は3つの事例を取り上げます。最初にご紹介するのは、2001年に当社製建設機械への標準搭載を開始した「KOMTRAX」(Komatsu Machine Tracking System:コムトラックス)です。当社の建設機械にGPSやセンサーを付け、どこでどのような状態で稼働しているかを把握するもので、おかげさまで日本におけるIoTの先駆けともいわれています。これは経営企画室の若手社員がある論文から着想したアイデアをもとに始まった新規事業で、社長の命を受けて当時CIOだった私が開発を率いました。そもそもIoTという言葉すらない時代でしたから、自前での開発に相当苦労しました。もちろん最初からビジネスモデルのグランドデザインができていたわけではありません。盗難防止、部品・サービスの生産性向上に加え、新興国での代金回収といった予期せぬ成果も含めて、さまざまな価値が後付けで生まれていきました。最初からリターンを求めていたら、KOMTRAXはここまで成長できなかったことでしょう。若い人のアイデアを取り上げてチャレンジさせること、その際、1〜2億程度の研究開発投資を惜しんではならないこと。新規事業における教訓をここで学びました。
 <パネリスト>
<パネリスト>小松製作所 特別顧問
野路國夫
KUNIO NOJI1969年大阪大学基礎工学部機械工学科卒業、小松製作所入社。建機事業本部技術本部生産管理部長などを経て、1997年に取締役となり、生産本部長、建機マーケティング本部長など、製造・販売それぞれのトップを歴任。2007年に代表取締役社長(兼)CEO就任。その後、2013年に代表取締役会長、2016年に取締役会長。2019年6月に取締役を退任し、現職。
次にご紹介するのは、私が社長時代の2008年から導入を始めた、鉱山プラットフォーム「AHS」(Autonomous Haulage System)です。鉱山全体にアンテナを立て、集中コントロール室から鉱山内で働いている無人車両をコントロールする仕組みで、いわば鉱山の交通管制システムです。フリートマネジメント(車両管理)システムを開発したアメリカ・アリゾナ大学発ベンチャーを買収し、そこに当社が長年開発を進めてきた無人ダンプトラックの技術を組み合わせることで実現しました。無人ダンプトラックというハードベースの開発ではトラック自体にさまざまな機能を搭載させねばならず、システムが複雑になってしまうことが最大の課題でしたが、この車両管理ソフトがすべての車両を制御することでハード側の技術的課題を一気にブレイクスルーすることができたのです。
最後にご紹介するのは、2015年から開始したスマートコンストラクション、つまり土木建設現場のDXを目指すオープンプラットフォームです。ここではお客様の生産性向上のためのエコシステムづくりを進めており、パートナー企業とともに試行錯誤を続けている真っ最中です。現場で刻々と変化する地形データをプラットフォームに取り込んでいくことが不可欠となるわけですが、データはどこからか自然と湧いてくわけではありません。よってカギとなるのは、正確なデータを取り出す計測技術です。そこで画像半導体メーカーのNVIDIA(エヌビディア)との協業の下、ドローンによるリアルタイムの3次元測量を開発しています。また、このスマートコンストラクションは、“オープンな”プラットフォームであることもポイントです。プラットフォーム上にあるデータを公開し、アプリ開発企業などさまざまなパートナーにデータ利活用のソリューションを開発してもらうことで、スマートコンストラクションのエコシステムを形成しています。
新宅:この3つの事例は、まさにコマツのDXの進化プロセスを示しているように感じます。まず、KOMTRAXでハードにデータを装備したIoTを実装しました。次に、AHSで鉱山という空間の中でクローズドなプラットフォームを完成させました。そして、ERTHBRAINではさまざまな現場に対応するためのオープンなプラットフォームと、その運用に不可欠なエコシステムをつくり上げました。デジタル化とプラットフォームの進化形がここに読み取れます。