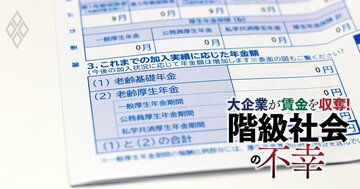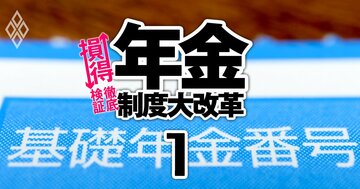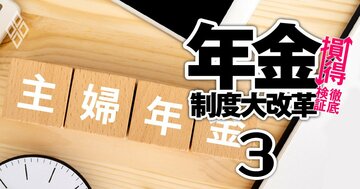Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
政府は2024年度年金財政検証を基に年金制度改革法案を国会に提出する予定だ。被用者保険の適用拡大などが盛り込まれているが、いずれも制度の根幹に踏み込む抜本的改革には至っていない。少子高齢化の進行が続く中、支給開始年齢や給付水準、さらには制度の財源構造そのものを再設計する必要性が高まっている。(昭和女子大学特命教授 八代尚宏)
形式的な制度改正にとどまる
年金制度改革案
政府は2024年度年金財政検証を踏まえた年金制度改革法案を近く国会に提出する予定である。その主な内容は、被用者保険(厚生年金・共済年金)の適用拡大、在職老齢年金の支給停止となる金額の引き上げ、遺族年金の見直しなどである。
しかし、いずれも年金制度の技術的な内容にとどまっており、今後の少子高齢化の急速な進展の下で、年金制度の安定性を確保するための抜本的な改革には程遠いものだ。
公的年金制度は福祉ではなく、「保険」である。政府が運営していても、民間保険と同様な収支の均等原則を維持しなければならない。
公的年金保険の最大のリスクは加入者の長寿化である。今後45年までの20年間で、平均寿命は男女平均で2.4歳も延びることが見込まれる。人々が長生きすることによる年金給付の自然増加分をどう賄うかが、本来の年金制度改革の基本となる。
増加分を賄う方法としては、まず年金保険料の引き上げが挙げられる。しかし、それは縮小する勤労世代人口へのさらなる負担増となり、経済社会への悪影響が大きいため、保険料引き上げの上限が04年度の制度改正で設定された。そのため、保険料引き上げに頼ることはできない。
では、収支均衡を図るためにはどうすればいいのか。次ページで今回の法案に含まれていない方策を含めて検証する。