「私」「私たち」「世界」
3つのシステムの関わりを考える
井上英之(以下、井上) インタビューの中での福谷さんとピーターのやりとりは、これまで二人が構築された、深い信頼関係に基づいたもので、明らかにピーターが安心して話していることが声の響きでもわかりました。あのインタビューの場そのものが、「ソーシャル・フィールド」のお手本のようですね。
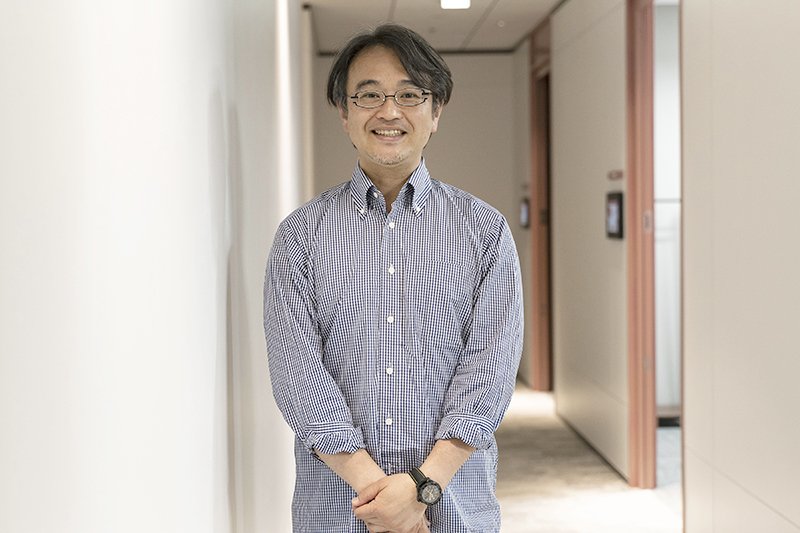 井上英之(いのうえ・ひでゆき)
井上英之(いのうえ・ひでゆき)慶應義塾大学卒業後、ジョージワシントン大学大学院に進学。外資系コンサルティング会社を経て、NPO法人ETIC.に参画。若い社会起業家の育成・輩出に取り組む。2003年、社会起業向け投資団体「ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京」を設立。2005年より、慶應義塾大学SFCにて、社会起業に関わる実務と理論を合わせた授業群を開発。2009年、世界経済フォーラム「Young Global Leader」に選出。近年は、マインドフルネスとソーシャルイノベーションを組み合わせたリーダーシップ開発に取り組む。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」共同発起人。Photo by Teppei Hori
ピーターが、冒頭から「場」、「ソーシャル・フィールド」や「リレーショナル・フィールド」に言及していることが印象的でした。「場」を考えるのに、まずは「自分が本当は何を意図しているのか」を知ること、そして「自分がどのような未来を欲しているのか」を描くこと、この2つが必要です。
そして、その「私」があり、次に「私たち」(つまりは場)があり、もっと「大きな世界」、自然界というものが、常に同時並行で存在している。その関わりを考えることが起点になるんですね。
ブータンで、ピーターと一緒に「今の自分は何を感じているか」を話す、「チェックイン」というセッションをしたときのことです。ピーターは、一人ひとりの参加者のことを、とてもよく覚えているんです。
それもそのはずで、チェックインする個々の話を聞きながら、熱心にメモを取っているんです。しかも、移動中のバスで(彼は、みんなを先に乗せてから、自分は最後に補助席に座っていました)、そのメモを丁寧に、大切そうに見返しているんですね。
参加者のバックグラウンドに深く興味を持ち、その人に敬意を払いながら、そこに会社や社会の代表性を見いだそうとしているのかもしれません。たとえば、「こういう人がいるのなら、その会社の背景にはきっとこういうことがあるのではないか」「ある働く女性がこういう訴えをしているなら、同じような人がきっといる。だからその人の言っていることは、必ず何かの意味があるのだ」といったふうに、全身で注意を向けているんです。
一人一人もそうですし、もっと言えば、自然界にあるものに脇役なんて何ひとつありません。動物、植物、バクテリアまで、すべての循環と関係性に好奇心を持っているからこそ、ピーターは深いところでいろいろな人と対話ができる。人と人とが理解をすすめる場をつくり、そういう場があることで、世界に対して深い変革を生み出せる。彼はそういうことを数多く経験してきています。
今回のインタビューでも、「場」について、「私」、「私たち」、そしてそれらを含む「大きな世界」という、3つのレベルとの関わり合いの重要性が強調されていたように思います。
人間同士の「自然なリズム」を意識し
テクノロジーの使い方をデザインしていく
小田理一郎(以下、小田) そうですね。「グラウンディング」(地に足がついて、心と体が整っている状態)している、それぞれの個性やペースがある、その人が自然にいられる仲間や会話がある、など、「一人一人がその人なりのありかたをしている」ということを大切にすれば、精神的に健康な時間を過ごせる。
 小田理一郎(おだ・りいちろう)
小田理一郎(おだ・りいちろう)チェンジ・エージェント代表。オレゴン大学経営学修士(MBA)修了。米国企業で10 年間、製品責任者・経営企画室長として、組織横断での業務改革・組織変革に取り組む。2005年チェンジ・エージェント社を設立。日本において、「システム思考」や「学習する組織」など、変化のための方法論の普及・実践の推進に務める。サステナビリティ、社会課題解決分野における、能力開発とプロセスデザインに関連するサービスを提供する。共訳にピーター・センゲ著『学習する組織』、著書に『「学習する組織」入門』(共に英治出版)など多数。Photo by Teppei Hori
逆に、プレッシャーやストレス、ディストラクションがあると、大脳辺縁系から反応して、戦う、逃げる、凍結するというモードになる。長期的視点で考えられなくなる。このことをピーターは伝えているのだと思います。
人間の脳の働きが解明されるに従い、その人が自然でいられるために、どういう場を用意すればいいかということが、ますます重要になってくるが、テクノロジーはその解決に役立っているのか? テクノロジーは本当に良いものばかりなのか? ということを、ピーターは問いとして突きつけています。
テクノロジー、つまり、ITC、インターネットやSNSなどは便利で良い面もあるが、それは本当に人間に役に立つものなのかどうかをよく考えなくてはならない。「テクノロジー」は抽象的な言葉だが、抽象化することで、無批判に「良いもの」という前提になってしまいがちだ。だから具体化して考えたほうがいい、と。
日本人はこれまで、テクノロジーを上手に使ってきました。ただ、「テクノロジー」は、はさみや包丁、ペンなどローテクなものであって、昔は自分でどう機能するのかを学べるもの、身の丈に合うものでした。
それが、インターネットの発達に伴い、どんどんグローバル化、巨大化して、知らないところでつながり、良い面、悪い面が見えなくなってきました。画面と画面でつながっている部分は見えても、その裏にあるテクノロジーのブラックボックスは見えないし、コミュニティの外にあるものも見えなくなってきています。
一人一人のそのキャパシティという意味でも、社会、組織、国はそのテクノロジーの制御をどう行うべきなのか。ピーターは、現代は1日600〜700通のメッセージやチャットが手元に届くという例を挙げていましたね。
テクノロジーは、明らかにわれわれの想像を超える形で発展して、広がっていっている。その中で、広める側の人は「良い面」ばかり強調するが、ピーターは、テクノロジーはこのままではディストラクションをもたらすと、言い切っています。
私たちのウェルビーイングやメンタルヘルスへの影響は、子どもたちを見ていても言える。この10年で、10代の自殺率が2倍になった。これは異常な状況で、子どもたちは大人よりも正直だから、社会の変化をすごく敏感に感じ取っているのだと。教育の現場でも多くの課題が浮き彫りになってきていると。
井上さんが、先ほど生態系の話にも触れてくださいましたが、現代は何かというと「スピード、スピード」と言うけれど、人と対面で会話できているときのように、人にとっての「自然なリズム」は厳然としてあると、ピーターはこう言っているんですね。
現代のテクノロジーは、スピードがより高速化し、スキルが高度化し、ネットワークが膨大になっている。うまく使える人はいいが、キャパシティが伴わないと、むしろ一人一人にはマイナスの影響の方が大きい。テクノロジーはもろ刃の剣である。その剣の本質をしっかりと目を背けずに見なくてはいけないと、指摘しています。
ただし、コロナ禍では、家や会社の中からでも世界中とつながることに、テクノロジーは寄与している。反射的・反応的ではなく、ゆっくりとじっくりと考えられる、人間同士の「自然なリズム」で社会的な関係をつくることにプラスの形で使えるならば、テクノロジーは何かを可能にしてくれるもの(=エネーブラー)である。
「制約」をしっかりと意識しながら、どのようにメリットを活かすのかというバランスを考えて、テクノロジーの使い方をデザインしていくべきだという提言は、重要でした。
 Photo by Teppei Hori
Photo by Teppei Hori
福谷 ソーシャルリレーション、つまり、社会的なつながりを育むのに良い方法があるならば、テクノロジーで多くのことが成し遂げられる。これが今の時点の結論だと、ピーターは指摘していました。今、おふたりはそのことに触れて、お話を深めてくださいました。
日本人は「コンテキスト」(文脈)を大切にするカルチャーを持っていると彼は言っていて、「それを活かすのに何から始めればいいか」と聞くと、「ホームから始めなさい」「『学習する組織』の最小単位はいつもチームである」と言っている。
今日の「チーム」の特徴として、組織の中のチームだけでなく、組織をまたいだチームがあり、その両方から始めていくのが大切だとも、話されていました。この話を受けて、おふたりはどのようにお感じになられましたか?






