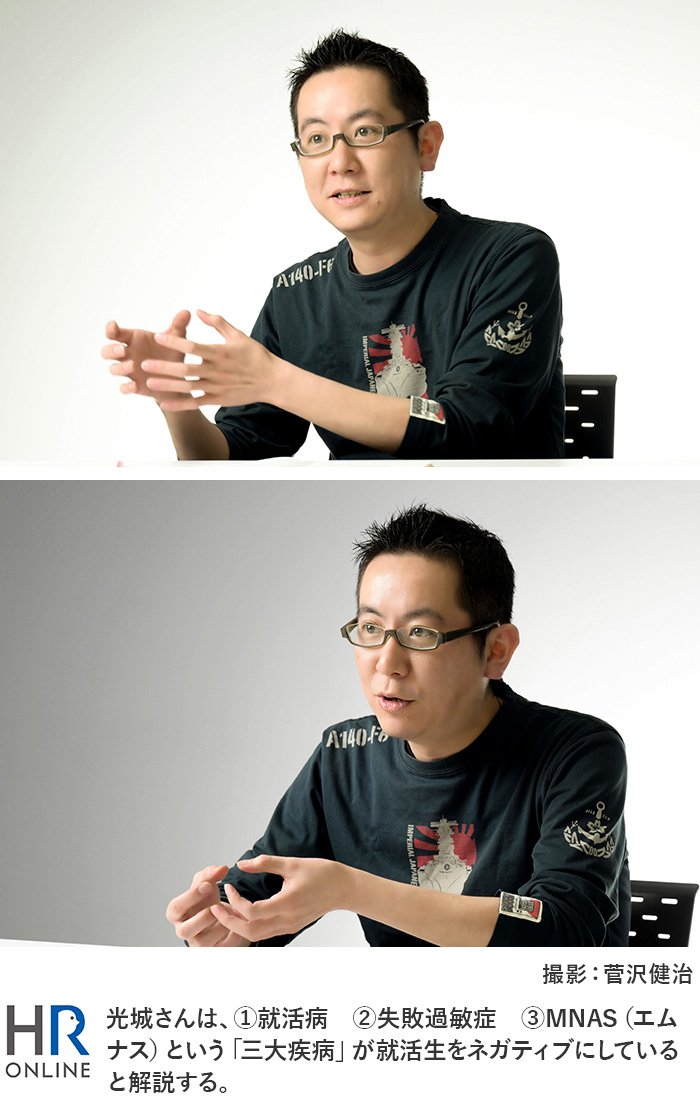「就活病・失敗過敏症・MNAS」という重い疾病
光城さんは、自著『内定メンタル』の中で、学生をネガティブにする「三大疾病」を憂い、その対処法を説いている。そのひとつ「就活病」は、過去の常識にとらわれてしまう病(やまい)だという。
光城 既存のやり方、周りの常識に疑問を持つことなく、「そういうものだから」と合わせることが普通。それでいて成功確率も楽しさややりがいもそれほど高くない。学生も企業も騙し合って疲弊してしまう……そんな「就活病」の弊害について、ずっと言い続けています。学生だけでなく、企業も「就活はこうあるべき」という固定観念に縛られすぎていませんか、と改めて考えてみてほしいです。就活ではスーツにワイシャツ、髪の毛までも色が指定されて、お辞儀の角度にノックの回数も正確に守らなければいけない――僕に言わせれば、「そんな社会人、どこにおんねん!?」と。
企業の採用活動でも、エントリーシートからガクチカ、志望動機に強みや弱みを聞くのが「常識」になっているわけです。そんな就活の常識やルールをもとに商売している大人たちもいて……そうした人が実際の採用活動をどこまで知っているかというと、それも怪しいですよね。
就職活動における常識とルール――たしかに、企業・団体の採用活動の姿勢や「就活ビジネス」を行う業者が、学生にそれを強いているように見える。
光城 もちろん、常識やルールを重んじる企業もあれば、それとは違う尺度を持っている企業もあります。それを「就活ビジネス」の人たちが、むしろ複雑にしている現状があります。だから、「就活の常識にとらわれないでいい」という企業側の考えは、残念ながら学生にうまく伝わらないことが多いですね。「学生と、もっと本音で話をしたい」という採用担当者の思いがあったとしても、常識やルールが壁を作ってしまう。就活病を減らすには、「いわゆる“就活っぽい就活”はしなくていい」といった企業の積極的な発信で、学生自身も意識を変えていくことが必要です。
それこそ、採用において「コミュニケーションスキル」を重視している企業であるとしたら、不安だらけで着飾っている学生たちの「常識の壁」や「心の壁」を取り除いてあげるコミュニケーションを大事にしてほしいのです。
「失敗過敏症」についてはどうだろう?
光城 就活病で「型や正解に合わせる」ことを前提としている学生たちにとって、そこから外れることは大きなストレスになります。同時に、閉じたSNSや実体験の少なさの影響もあるのか、「自分が触れた正解」以外のものに対して過敏に失敗を恐れてしまう部分もあると思います。どこかに行くにもスマホで正しい行程を探せるし、食事でも評価サイトが評判の良いお店を教えてくれて、失敗に出遭う機会は減っています。ただ、社会では、どんなに実績を残したトップクラスの社員でも、一度も失敗をせずにその位置にたどりつくなんてことはないはずです。むしろ、失敗をしたから学べることのほうが多いはずです。
だからこそ、採用活動でも、挫折経験を聞くという「常識」があるのも理解できつつ、本当にそれが就活病の学生たちにとって本音で話せる投げかけ方なのかと考えると、彼らにとって「挫折」という言葉は大きすぎる。個人的にはズレが生じるのは当然だな、と思います。
三つ目の病(やまい)――「MNAS(エムナス)」は、多くの学生が「もらい慣れ過ぎて、与えることを知らない」ことを指している。
光城 「MNAS」の症状を減らすだけで、社会人からの評価がガラリと変わるはずなのに、学生はなかなか気づいてくれないですね。僕自身も、どう伝えたら本質的に理解してもらえるのか、考え続けている段階です。というのも、若いうちは誰でも、社会に出る前はさまざまなものを受け取ります。学校で教育を受けたり、保護者に学費を払ってもらったり、道路が整備されていたりゴミを収集してくれるのも、そう。あらゆるものをもらえるのは、やがて「社会に価値を生み出す人」になるためです。
しかし実際は、もらうことに慣れて、返すことに意識が向かない学生って、むちゃくちゃ多いんです。頭では理解してくれても、返す方法がわからないこともあります。たとえばセミナーでも、その後のLINEのやりとりで、「今日は勉強になりました」という1行で終わる学生もいれば、「□□のところが○○でした」「これまで○○だったんですけど、今日のセミナーで□□だと思いました」という学生もいます。僕としては、後者の言葉だけで「返してもらった」と思える。一方で、いきなり「セミナー資料を送ってください!」「自己PRの添削をお願いします!」という学生もいて、ちょっと困ってしまうこともあります……。
ただ、おそらく彼らにとってはセミナーも資料も、アドバイスや添削なども、何かしらの「答え」をもらえるのが当たり前の社会で過ごしてきているんですよね。スマホで検索すれば出てくるし、求めれば返ってくることに慣れている。いまの学生にとっては、どこかで答えを拾えるのは普通のことなんです。