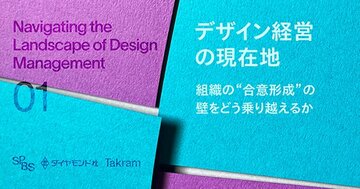「製品愛」を原動力に、感動価値を生み出していく

──だとしても、その好循環はどこから生まれたのでしょう。サイクルを回すにも初動のエネルギーが要るのでは。
ああ、そういう意味では初動は何だろう……。あまり考えたことがなかったけど、言われてみると「ありがとう」が顕在化するまでに5年ぐらいはかかっています。デザイナーはめちゃくちゃ現場を観察するでしょう。すると課題がわんさと出てきます。それを小手先の改善で終わらせず、「その先」をデザインで見せることができたとき、ニッチから新しいサービスやビジネスが生まれる。事業部の人がそのプロセスを目撃すると、「デザインの力はすごい」と気付くし、別の事業部に移っても必ず「一緒に考えてほしい」と声が掛かる。こうして、デザインの目撃者が社内にじわじわと増えていきました。
これって「デザイン思考」といえばそうかもしれませんが、僕はそう呼ぶことに違和感があるんです。そういう一般論じゃないんですよ。富士フイルムって「サイエンスの会社」で、みんなが色んなことを試します。試しながらこれがどういう価値になるのかを追求していく。そこにすごく時間をかける。それは富士フイルム全体に共通する風土です。
──では、試しながら価値を追求することが重要だということは分かっていても、実際に時間をかけられる会社は多くありません。その風土はどうやって生まれたんでしょうか。
根本に、立場を超えて共有している「製品愛」があります。デザイナーなら誰しも「いいものを作りたい」という「デザイン愛」を持っています。これが「製品で人が喜んでくれた」という現実を目の当たりにすると、「製品愛」に進化する。僕もチェキを大喜びで使う女子高生を見て、製品愛が爆発して、開発をやめられなくなった。製品の根幹の価値を追求する原動力はこれかな。会長に「デザインセンターは『機能のデザイン』を超えて、デザインで機能を生み出しているね」と言われたことがありますが、これは刺さりましたね。
振り返れば「デザインを分かってもらいたい」という精神も強かった。デザインセンターの活動を報告する「デザイン月報」というレポートがあるんですが、そこに社長や会長からコメントが付くと、すかさず「説明させてください!」と、若手を連れてプレゼンテーションに行く。質問が付きやすいように、わざと難しく書いたりして、デザインの力を伝える機会を常にうかがっていました。あるときには、社長から「この考え方は早過ぎる。日の目を見るときは来るから、活動は継続しながら、ちゃんと引き出しにしまっとけ」なんて言われたことがありました。
──「しまっとけ」とまでは言えても、「継続しろ」とはなかなか言えません。それが今、まさに日の目を見ているわけですね。
技術畑出身の社長でしたから、デザインに「技術ごころ」を見いだして共感してくれたのかもしれません。デザインって成果を数値化しにくいものですが、「人に感動を与える価値を生み出す」というデザインの本質には、人それぞれに共感できるポイントがある。そうやって色んな立場の人に、デザインについて何かしらの思いを持ってもらうことは重要だと思います。
──社会が「モノからコトへ」と必死にシフトしようとしている中、富士フイルムでは、もともと両者は不可分であるという考えが根付いているようにも思えます。
そう感じてもらえるのはうれしいですね。「コトの時代」なんていいますが、モノがないコトなんてないでしょう。あったとしても、寂しいじゃないですか。いいモノの周りにはストーリーがあるし、大切なモノがあるからこそコトも輝く。それを切り離して考えたことはないですね。
それは、もしかしたら、富士フイルムの原点が「写真フィルム」だからかもしれません。写真って、モノである以上に体験ですから。現在の多様な事業領域が全てそこから生まれたように、デザイナーに覚醒をもたらした本当の初動も、やはりそこにあるのかもしれないですね。
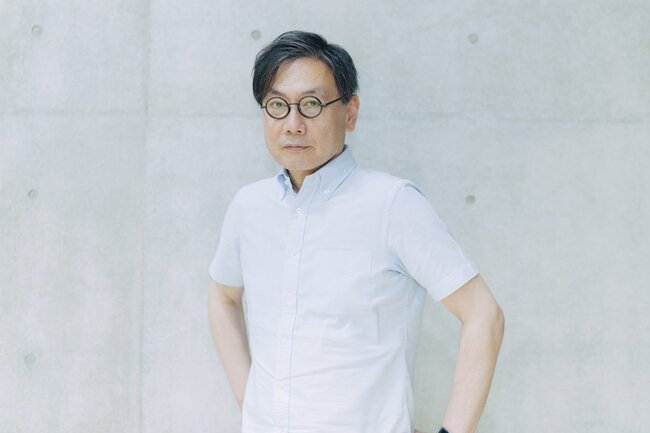 Kazuhisa Horikiri
Kazuhisa Horikiri富士フイルムホールディングス 執行役員 デザイン戦略室長 ブランドマネジメント管掌 兼 富士フイルム 執行役員 デザインセンター長
1985年、プロダクトデザイナーとして富士写真フイルム(当時)に入社。代表作の初代チェキのデザインで発明賞を受賞。2014年、デザインセンター長に就任し、「富士フイルムをデザインする」を掲げ、2017年、CLAYスタジオを西麻布に開設。2018年にデザイナーとして初めて執行役員に就任。2022年に富士フイルムホールディングスにデザイン戦略室を開設し、グループ全体のデザインとブランドを担う