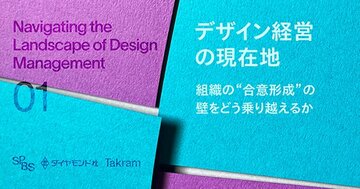純度の高いクリエイティブ環境を丸ごとデザイン

──今年(23年)5月に、デザインとITの開発を統合したクリエイティブ拠点が誕生しています。総工費がおよそ35億円とのことで、かなり思い切った投資提案だと思いますが、社内からの反対などはなかったのでしょうか。
逆に、経営層からも強い後押しを受けました。といっても、ゼロからいきなり提案したわけではなく、もちろん前段はあります。ご存じのように、富士フイルムの祖業は写真フィルムです。しかし、2000年のデジタルショックで需要が激減して以降、自社の技術を全て棚卸しして、新たに組み合わせ直すことで新領域を広げてきました。カメラ、化粧品、医療機器、機能性材料……。デザインセンターが扱う領域もそれに伴って拡張されていきました。
そこで、僕がデザインセンター長に就任した14年、経営層に「新しくなった富士フイルムを丸ごとデザインさせてください」と訴えました。デザインの力というと、よく「可視化力」が挙げられますが、実は、向かうべき方向が全然見えない中で「こっちに行った方がいいんじゃない?」みたいにかぎ分ける力もある。この力を経営に生かしたいと思ったんです。
──10年近く前から「デザイン経営」が始まっていたのですね。
そのためには、デザイナーの発想がジャンプする場が必要だ──。そう考えて17年に「CLAY(クレイ)」と名付けた独立型のデザインスタジオを東京・西麻布に立ち上げました。独立といっても、分社化したわけじゃないから親のスネをかじりながらの1人暮らしです。でも、実家と違って、1人暮らしの部屋って人が集まりますよね。CLAYの狙いもそこにあって、本社にいたときには付き合いの薄かった研究所や事業部からの相談が増え、ブランディングや仕組みのデザインが広がりました。他社のデザイナーや、外部のアーティストとの交流も加速。デザイン賞の受賞数も激増しました。純度の高いクリエイティブな環境を得て、デザイナーたちが覚醒したんです。
──こうした布石があったからこそ、型破りなデザイン拠点が実現した、と。
今回オープンした南青山の新拠点には、デザインセンターが入った新しいCLAY棟の隣に、エンジニアが結集するIT棟が並んでいます。デザインにITを掛け合わせてイノベーションを加速させようという狙いです。新CLAYのデザインには、デザイナー80人が全員参加しました。外観や内装だけじゃなく、デスク、館内サイン、手すりやマンホールまで。しかも、これで終わりじゃない。「完成しないデザインスタジオ」をコンセプトに、使いながらどんどん変えていくつもりです。未完成だからこそ、進化が続くんです。
──とはいえ、おびただしいデザインの成果は「場の力」だけでは説明できないように思います。
その質問は非常によく頂くので、自分たちでも改めて振り返ってみました。それで分かったのは、「ありがとう→いいね→たのむ」の好循環が回っていることです。社内の経営会議には、デザインセンターと組んだ事業部長の「デザインセンターのおかげで価値が生まれた」という感謝の声が集まってくる。社外からはデザイン賞などを通じて評価の声が集まってくる。社内外からの「ありがとう」と「いいね」が蓄積すると、頼られる場面が増え、さらなる「ありがとう」や「いいね」が生まれていく。特に変わったことをしてきたわけではありません。