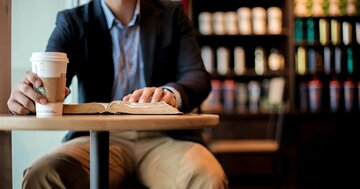情報を得られる人と、得られない人とで
中国人の間に分断が生じている
今回の騒動で、筆者が特に気になっている点が二つある。一つは、ネットの発達により、情報の伝え方がとても重要に、難しくなっているということだ。真実であれフェイクニュースであれ、情報の使い方や統制の仕方次第で、真実は容易に隠されてしまう。まさに「情報戦」である。
もう一つは、中国に住む人々の情報格差の大きさだ。中国の場合、一般の人々(圧倒的多数)が情報を取得するソースは国内のメディアやSNSに限られている。ゆえに、今回放出された処理水は汚染物質が除去されていて、トリチウムが微量で環境にほぼ影響がないこと、そして、自国を含む世界の原発が処理水を海洋に放出している事実を知らない人がほとんどだ。その一方で、外国語ができる人、特にVPN(仮想プライベートネットワーク)を使ってYouTubeやX(Twitter)を利用している人々は、中国国内の報道にとらわれず、世界のニュースやさまざまな言論に触れることができる“情報強者”である。前者と後者では、今回の件について見解が完全に分かれており、分断が生じている。
ネットでの声がほとんど日本への批判であることについて、中国にいるシンクタンクの研究員の知人は次のように話す。
「ネット世論は批判一辺倒だ。まるですべての中国人が日本の処理水の海洋放出に反対し、日本を叩いているように見えるが、その人たちのどれぐらいが、理解して発言しているのか疑問だ。多くの人は単に“流量”が欲しくて(=PVが欲しくて、注目を集めたくて)、激しい言葉を発したら注目されると思っているだけだろう。また、これまでも(中国は)日本を含め、国際社会との衝突が度々起こったが、毎回時間がたつにつれ、忘れ去られていく。今回のことも、多分そうだろう。3カ月もたてば、日本へ旅行に行って、海鮮を楽しむんじゃないかと予想してるよ(笑)。
それよりも、僕が懸念しているのは、『海鮮を不買運動した結果、ブーメランのようにならないか?』ということ。海はつながっている。日本の水産品をボイコットした結果、我が国自身の漁業への打撃になりはしないだろうか?」
確かに、すでに中国のネットでは、漁業を営む人が「400万元(約8000万円)のローンで買ったばかりの漁船をどうしたらいいんだ、泣きたくなる」と投稿して話題になったり、ライブ配信で販売する魚屋さんが、中継中に売った魚を返品され、ののしられて大声を出して泣いた、といった動画も出回ったりしている。
さらには、不安のあまりガイガーカウンターを購入して、身の回りの放射線を測ることがブームになりつつある。その結果、家の中にある大理石の近くで放射線を検出して数値の高さに驚いたり、日常生活の中でも被曝することを知ったり、海よりも都市部のほうが数値が高いことに気付いて混乱したりする人々も現れ始めた。