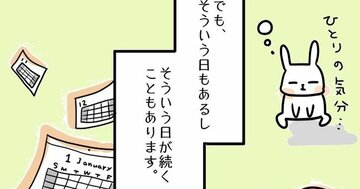人と話した後、
モヤモヤして疲れてしまう…
【 実際の相談事例 】
とにかく人間関係で疲れてしまいます。何か意見を求められても、相手が何を求めているのか? 何を言ったら喜ぶのか? 相手が言ってほしい答えは何か? について考える思考が染みついていて……。
自分の意見を言えたとしても、相手が不満そうだと「ああ、言わなきゃよかったな」と思いますし、かといって言わないままだと、「本当はこう思っていたのにな」とモヤモヤします。
どちらにしても後悔するので、どうしたらいいのか分からなくなってしまいました。
この相談者Iさんの場合、相手を喜ばせることが最優先事項となっていることが、人間関係で疲弊する一番の原因でした。
自分が言いたいことよりも相手が言ってほしいことを選び、自分の機嫌よりも相手の機嫌を優先し、自分が楽しむことよりも相手が楽しむことを大切にするのが、当たり前になっていました。
相手を優先することがダメだ、と言いたいのではありません。相手を優先することに不満やストレスを感じていないのなら、それはそれでいいのです。
相手を楽しませ喜ばせることで、あなたが心から楽しみ喜ぶことができるのなら、まったく問題ありません。
ですが、Iさんは自分の意見が言えない状況に、次第にストレスを感じるようになっていました。
このように、今の状況がストレスになっている場合には、なぜ楽しませなければいけないと思ってしまうのかについて知る必要があります。
「人を楽しませなきゃ」
その思い込みはいつから?
Iさんの場合、人を楽しませなければいけないという思い込みは、子どもの頃につくられていました。
子どもの頃は、大好きなお母さんを喜ばせるために、勉強やお手伝いを頑張っていたIさん。
自分の意見を言うとお母さんが悲しんだり、「誰のおかげで生活できていると思っているの!?」と怒ったりした経験から、自分の意見を言うのは良くないことだと思い込むようになったのだといいます。
母親に合わせ、母親の望む言葉を言うことで、母親を喜ばせようと努力を重ねてきました。
人は、子どもの頃に親との関係を通して、「〇〇をすると、何が起こるのか」を学びます。
しかし、この時期に学ぶ事柄は親の価値観に大きく影響されたものなので、すべてが正しいとは限りません。
カウンセラーとしての経験上、生きるうえで弊害になるような事柄を植え付けられてしまうことのほうが圧倒的に多いのです。
Iさんの場合は、「自分の意見を言うと、怒られる」「自分の意見を言うと、悲しませる」ということを学んでいました。
その結果、自分の意見を言うのは良くないことだという、強い思い込みに苦しめられてしまうようになったのです。