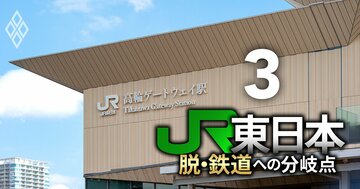また、特別利益として、貨物列車の運行に必要な設備投資や青函トンネル修繕費として助成金75億円が交付されており、これらの手厚い支援によって成り立った黒字であることが分かる。
もっとも、このまま補助金漬けで延命させようという話ではなく、支援の期限である2030年度までに、鉄道事業の合理化と不動産をはじめとする関連事業を拡大することで、なんとか自立に持って行きたいという計画だ。
しかし、今期のセグメント別営業損益は、運輸が約218億円の赤字に対し、不動産が約26億円、ホテルが約11億円の黒字と、残念ながら全くの力不足だ。「切り札」とされる北海道新幹線札幌延伸と札幌駅周辺再開発は、工事の遅れで2030年度の開業が困難との報道もあり、先行きは厳しい。
JR四国が置かれている状況も同様だ。同社は連結営業収益約254億円に対して約48億円の営業赤字だが、基金運用益を含む営業外利益が約74億円計上され、経常利益は約24億円、約20億円の最終黒字となった。
ただ超閑散路線を多く抱えるJR北海道に対し、JR四国は収支こそ赤字だが鉄道でなければ運べない輸送密度の路線が多いのが特徴で、4県にまたがる特急ネットワークで高速道路網に対抗するなど経営努力を進めてきた。
今期のセグメント別営業収益は、運輸こそ2019年同期比86%だが、建設、ホテル、駅ビル・不動産、ビジネスサービスはコロナ前を上回り、全体でも2019年度と同水準だ。運輸の営業損失約59億円を埋めるには程遠いが、札幌という大都市を抱える北海道とは異なり、四国の人口規模ではやみくもに事業拡大しても大きな利益は期待できない。
本州3社が合計5000億円近い営業利益を計上し、コロナ前に戻りつつある中、JR北海道とJR四国の営業損失は合計約222億円。仮に国の支援がなく経営安定基金運用益を利回り2~3%で運用したとすれば、経常損失は半期で計約100億円だ。
JR東日本、西日本もローカル線の見直しに乗り出す中、北海道と四国の赤字路線を野放図に補助しろとは言わないが、不合理を感じてしまうのは筆者だけではないだろう。