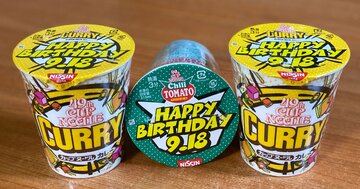化学調味料と殺虫剤という組み合わせの悪さと70年代の空気
ご存じの方も多いだろうが、味の素は戦後、調味料を販売するかたわらで殺虫剤の「DDT」の製造販売をしていた。同社ホームページの社史にもこうある。
現在ならば、食品メーカーが「殺虫剤」を売るというのはイメージ的な問題があるので、別会社、別ブランドをたてるのが常だが、当時はおおらかな時代だ。「味の素のDDT」という商品名で広告や宣伝がなされていく。「読売新聞」だけでも、1949年から1962年まで「味の素のDDT」や「味の素のネオDDT」、さらに後継品である「味の素の強力殺虫剤ノックダウン」などの広告が大量に掲載されている。
そんな風に世に「味の素=強力殺虫剤」というイメージを定着させた10年後、これまで繰り返し述べている「中華料理症候群」問題がやってくる。70年代の日本人からすれば、味の素というのは「毒」「化学薬品」「殺虫剤」などのネガイメージと直結しやすいものだったのだ。
ちなみに、なぜ読売新聞で「味の素のDDT」の広告が1962年で終わっているのかというと、実はこの年、海洋生物学者レイチェル・カーソンが「沈黙の春」を発表して、DDTをはじめとする化学物質の危険性に警鐘を鳴らしたからだ。
「沈黙の春」は世界的ベストセラーになり、各国でDDT論争を巻き起こして、それがその後の「中華料理症候群」などアンチ化学物質のムーブメントにもつながっていった。
つまり、「沈黙の春」に衝撃を受けた、70年代のアンチ化学物質の人たちからすれば、「味の素」は、化学調味料と殺虫剤という人類を破滅に追いやるツートップを扱う「死の商人」という位置付けなのだ。
そのネガティブイメージが令和の現在も引きずられている可能性は高い。
「沈黙の春」や「中華料理症候群」が一世を風靡した60〜70年代に若者だった人は今や70〜80代だが、高齢化社会の日本ではバリバリの現役で、さまざま世界で「大御所」として影響力を有している。「美味しんぼ」の原作者の雁屋哲氏などまさしくこの世代だ。
しかも、この世代は社会で活躍している40〜50代の親世代だ。言い換えれば、我が子を幼い頃から「いいか、味の素ってのは毒みたいなもんで体に悪いんだぞ」としつけることができた世代ということでもある。
このように「呪い」のような刷り込みこそが、「ファクト」を無力化する「味の素=毒」説の正体ではないか。
そう聞くと、「いやいや、いくらそうやって刷り込まれたとしても普通は大人になって、自分でいろいろな情報にアクセスできるんだから、デマだと気づくだろ」と思うかもしれない。
そう、普通に考えれば確かにそうなるのだが、そうならないのは3の《アメリカで今も続く「MSGヘイト」への崇拝》が関係している。