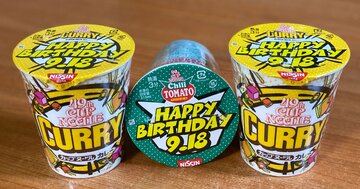「毒」というイメージが払拭できない3つの原因
それは次のようなものだ。
1.100年前の「毒」イメージの世代間伝承
2.10年以上続いた「DDT(殺虫剤)」広告のネガティブイメージの後遺症
3.アメリカで今も続く「MSGヘイト」への崇拝 ※MSG=グルタミン酸ナトリウム
まず、1に関しては、リュウジ氏を批判するアンチの人々の言説を見ていると「味の素が毒というのは昔から有名」「親からそう教えられた」などの表現がよく出る。つまり、「祖母から孫へ」「母から子へ」という感じで、「味の素ってのは体に悪いんだよ」というネガティブイメージが伝承されてきたのだ。
実際、「味の素」が怪しい原料でつくられているというデマは、100年前、大正時代からあった。それがうかがえるのが、1922年5月13日、「東京朝日新聞」に、味の素の前身・鈴木商店名義で出した、「誓て天下に声明す、味の素は断じて蛇を原料とせず」という意見広告だ。
しかし、このような「蛇が原料説」を払拭しようと躍起になっているまさにその時、半世紀にわたって「毒」イメージが定着してしまう「公害問題」が起きた。
この「毒液問題」は漁民だけではなく、多摩川沿の六郷村(現在の東京都大田区六郷地区)の耕作地にも被害をもたらしたことで、農民たちまで押しかけ、漁民とともに味の素に損害賠償を求めた、と報道されている。
…と聞くと、「おいおい、いくらなんでも100年前の公害問題の悪いイメージをそんなに引っ張らないだろ」と嘲笑するだろうが、この「毒液問題」に地元民は半世紀にわたって悩まされていた。それが再び「炎上」したのが、1973年のことだ。
川崎市公害局が調査したところ、味の素工場を含む3つの工場が長期間にわたって、東京湾に流し続けた水銀はかなり高濃度だと判明したと大きな社会問題となった。
さて、そこでこの時代の東京都民、川崎市民の心境になっていただきたい。大正時代から「毒液」を流して近隣住民とトラブルになっていた大企業が、半世紀を経て今度は水銀を流し続けていたという。「ああ、じいちゃん、ばあちゃんがよく言っていたように、味の素ってヤバいんだな」とネガティブイメージがより刷り込まれていくのではないか。
しかも、この「毒液問題」の対応に追われている時というのは、先ほどの「中華料理症候群」がアメリカで社会問題となって炎上している時と重なった。つまり、1970年代というのは、「味の素=毒」というイメージが急速に社会に定着していく時代でもあったのだ。
さらに、この状況を後押ししたのが、2の《10年以上続いた「DDT」広告のネガティブイメージの後遺症》ということではないかと考えている。