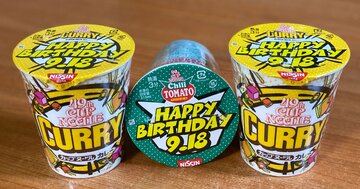グルタミン酸ナトリウムを「毒」扱いするアメリカに対する“信頼”
実は、国際的機関が「中華料理症候群」とグルタミン酸ナトリウムは関係がないと結論づけてからも、アメリカの消費者の間では、ネガティブイメージが続いている。
現地のスーパーなどに行った人はわかるだろうが、食品のパッケージには「no-MSG」と大きく書かれているものもある。
なぜこうなるのか。ひとつは、アメリカ社会は、食品を過剰に摂取して肥満になるなど健康を害する人が多いということがある。そのため、カフェイン、トランス脂肪酸など日本では適量なら問題ないとされているものでも、国が「安全性が認められない」として規制されることが多い。MSGは規制されているわけではないが、このような風潮もあって、「体に悪い」と信じる消費者が多い。
舶来コンプレックス(国内製品より外国製品をやたらにありがたがること)の強い日本人は、海外の情報に過剰に反応してしまう。「賃金が低い」とか「幸福度が低い」といった都合の悪い話は無視する一方で、自分たちの都合のいい情報は「ほらみろ、アメリカでは」と錦の御旗とする。
つまり、「味の素=毒」説が「ファクト」を突きつけられてもなかなか消えないのは、100年前から定着していた「毒」「薬」のイメージがあまりにも強いところに、アメリカのアンチ化学物質という心強い「援護射撃」があるからではないか、と個人的には考えている。
もちろん、「味の素」も、指を加えて見ているだけではない。科学ジャーナリストの松永和紀氏が2018年10月2日に以下のようにレポートしているように、アメリカで「風評対策」を始めている。
《フェイクニュースと闘う味の素 ニューヨークから世界へ情報発信 「中華料理店シンドローム」信じている人、まだいませんか?》
この記事の中で興味深いのは、アメリカ人の研究者が、「アメリカ人のno-MSGという意識の裏側にはレイシズム(人種差別)があるのでは?」と指摘をしたということだ。「アジアから来たわけのわからない調味料なんて、食べてもろくなことにならないに決まっている」という偏見こそがこの問題の根っこだというのだ。
これは日本の「毒派」のみなさんにも当てはまるのではないか。