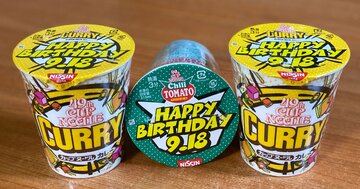漫画「美味しんぼ」が広めた誤解?ファクトがあっても進まぬ理解
「私が正しい」と「私が正しい」が衝突して両者一歩も引かなければあとは「戦争」しかない、というのは、イスラエルとハマス、ロシアとウクライナでも証明されている人間社会の宿痾(しゅくあ)だ。
しかも、リュウジ氏が「反ワクチン」に言及したことで、この「戦争」は泥沼化しつつある。SNSではリュウジ氏が「反ワクチン叩き」を始めた背景には、23年11月に、味の素グループが米・遺伝子治薬の医薬品開発製造受託機関であるForge Bologicsを買収したことがある、などと「陰謀論」が唱えられているからだ。
そんな風にカオスな様相を呈してきた「味の素=毒」論争の行方も気になるところだが、企業危機管理を生業としている立場としてはちょっと違うポイントに注目している。
一般的なリスクコミュニケーションの考え方では、しっかりとしたファクトを世に示せば、デマや風評というのは自然に収束していく、ということになっているが、「味の素=毒」説にはまったく当てはまらない。これはなぜなのか。
通説では「味の素=毒」を世に広めたのは、人気グルメ漫画「美味しんぼ」だとされる。では、その「元ネタ」は何かというと、1970年代のアメリカで注目された「中華料理症候群」だ。これは、うま味調味料の主成分であるグルタミン酸ナトリウムを多く含む中華料理を食べると、脱力感や動悸などの症状につながるというものだ。
ただ、それからさまざまな国際的な機関が調査をして、両者は関係ないと結論づけている。詳しくは、非営利組織「日本ファクトチェックセンター」の《「味の素は神経毒」は誤り。うま味調味料の安全性は確認されている》を参照されるといい。
こういう「ファクト」はずいぶん昔から社会に提示されている。にもかかわらず、「毒派」はそのような情報こそが「デマ」だと言わんばかりに、今日も「味の素を好きだった母が苦しんで死にました」というような「被害」を主張している。
つまり、「ファクト」くらいでは払拭できないほど、味の素に「毒」というイメージが、骨の髄まで染み付いてしまっていることではないのか。個人的にはこれには3つの原因があるのではないかと見ている。