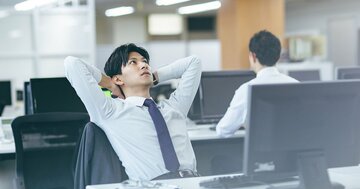現在の認識と異なる仏教の「差別」
区別に対する執着から次第に変容
 同書より転載
同書より転載
仏教では「差別」は「しゃべつ」と読み、区別することを意味します。それぞれのものが異なる姿をしていて、さまざまなものとして存在している様子を表す言葉で、今でいう「差別」みたいな、いわれのないランク付けのような意味ではありません。
世の中に存在するすべてのものが平等であるとした上で、その価値を認め、個々を独自のものとして認識する意味合いで「差別」が使われていました。
例えば、人間は皆等しく赤い血が流れ、命の尊さも同じで平等です。その上で、体格差や性格や肌の色など、それぞれに違いがある。これが仏教でいう「差別」です。
物事に対し「これは〇〇だ!」と差をつけて扱うのは、私たちがそういう見方をしているからです。本来はものごとというのは、ただのものごとであるにすぎません。区別することに対する執着から、現代で言うような「差別」が生まれたのです。
ちなみに、仏教でも差別に対する語は「平等」です。大乗仏教では差別と平等は切り離せないものだとしています。
平等だと言うとき、その裏には必ず差別があります。差別だと言えるのは、その裏に平等があるからです。どちらか一方では存在しえないものなのです。双方に裏付けされた差別であり平等であってこそ、真の差別であり真の平等なのです。