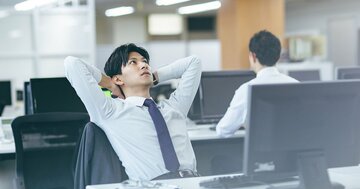写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
普段の生活でもよく耳にする「自由・煩悩・大丈夫・歓喜・覚悟」。いずれも仏教とは深い縁があり、梵語に由来する言葉もあるという。広く世の中に浸透する意味とは真逆の解釈から学べる智慧や真理を今後に生かそう。※本稿は、Jam著・枡野俊明監修『仏にゃんのふわもこやさしい仏教の教え』(笠間書院)の一部を抜粋・編集したものです。
「私を神格化してはいけない」
釈迦が遺言に込めた教えとは
 同書より転載
同書より転載
「自由」も実は仏教語です。梵語の「スヴァヤン」の訳語で、「他に依存せず、それ自体で存在すること」を意味します。
仏教による「自由」とは「自らに由る」ことで、自分以外のものの影響を受けず、自らを拠りどころにし、自分の本心に沿って生きることです。
お釈迦様が亡くなる間際に「自灯明・法灯明」という言葉を弟子に伝えました。「自灯明(じみょうとう)」は他の誰かの言葉や教えなど、そういった外のものをよりどころにするのではなく、自分と向き合い、自分自身をよりどころにしなさいという意味です。「法灯明(ほうみょうとう)」は真理、つまり、本当に正しい教えをよりどころにして生きなさいという意味です。
お釈迦様は亡くなるときに「私を神格化してはいけない、教えを怠ってはいけない」と言いました。
お釈迦様も「他の誰か」の一人なのでしょう。だから仏法(仏の教え)は自分自身の灯りで、ここでいう正しい教えは、経典や僧侶の法話そのものではなく、これまで自分が積み重ねて会得してきた生き方など、もっと広い意味での解釈も含むのだと思います。
今では「自由」は思いのまま好き勝手に生きられるような意味に使われますが、本当の自由って何にも依存することなく、心を自在にコントロールできる生き方なのかもしれません。