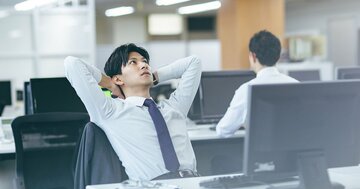Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
「お盆・お彼岸・喪中・四十九日」など葬儀に関する言葉だけでなく、「大人・頂く・意識・挨拶」なども仏教語だとされる。現代と異なることもあるという本来の意味も知ることで、気持ちが楽になる仏教語を紹介する。本稿は、Jam著・枡野俊明監修『仏にゃんのふわもこやさしい仏教の教え』(笠間書院)の一部を抜粋・編集したものです。
実は意外と使われている「仏教語」
本来の意味を知れば気が楽になる
現代の日本において、昔ほど宗教は身近な存在ではないと思います。かくいう私も無宗教です。
子供の頃から年末にはクリスマスを祝い、年始には神社に初詣に行き、夏にはお盆でお墓参りに行く。それぞれがキリスト教、神道、仏教に関連がある行事だと知ったのは、少し大きくなってからです。
私がはじめて「儀式」として宗教に触れた記憶があるのが「仏教」でした。いわゆる、お葬式です。
まだ幼い頃に父方の祖父が亡くなりました。和風の大きな広い畳の部屋があるお屋敷(お寺)に行って、たくさん親戚が居て、むにゃむにゃ言ってる(お経を読んでいる)坊主の人がいて。ご馳走(精進落とし)を食べて。「行事」として参加したのは夏祭りの「盆踊り」でしょうか。
「なんで『ぼん』なの?」と思いましたが、深く考えることなく、「お盆とお彼岸はお墓参り」「喪中のときは年賀状は出さない」など、仏教行事や習慣は当たり前に日常生活に溶け込んでいました。私と同じくらいの感覚で仏教に接してきた人は、結構多いのではないでしょうか?
これはあくまで私見なのですが、「仏教」って難しそうな印象がありませんか?お経は読み方がよくわからないし、漢字ばかりだし、本を読むと細かい字がびっしりだし。
ところが…私たちは普段から、その言葉を使わずに生活する方が難しいくらい仏教語を使っているのです。覚える前からもう使っていると思うと、少し敷居が低くなりませんか?
ちなみに、私が「仏教語」をはじめて意識して調べたのは、水族館に行ったのがきっかけでした。確かアジの水槽の前だったと思います。
「命をいただくから、いただきます」という看板があって、「え、そうなの?」と気になって調べたのですが、「頂く」が仏教語だったのです。