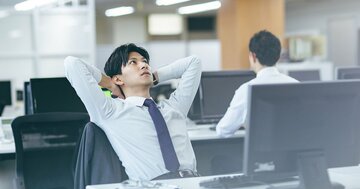写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
現代社会で頻繁に使われる「機嫌・精進・出世・差別・世間」は、もともと仏教の世界から派生した言葉だ。お釈迦様が説いた教えなどが由来とされ、ビジネス現場や暮らしでの悩みを解決するヒントとして活用しよう。※本稿は、Jam著・枡野俊明監修『仏にゃんのふわもこやさしい仏教の教え』(笠間書院)の一部を抜粋・編集したものです。
「機嫌」は古く「譏嫌」と書いた戒律
立派な人間で居続けるための定め
 同書より転載
同書より転載
「機嫌」は今では気分や体調を表す言葉ですが、古くは「譏嫌」と書き、戒律のことでした。
「譏」は「そしる」で非難すること、「嫌」には「疑う」という意味があります。正しくは「息世譏嫌戒」と言い、世間からお坊さんが譏嫌悪く思われるのを息(や)めさせるための戒律のことでした。
お釈迦様の時代は、お坊さんは修行に専念する必要があったので働くことは禁止で、生活はすべてお布施に頼らねばなりませんでした。
今の時代でもそうですが、もし、働かずに人に養われている人が悪事を働いたり誤解を招く行いをすれば、あっという間に世間から非難されてしまいます。
だから罪を犯さないのはもちろんのこと、飲酒や飲食、行動や言葉の慎みなど、人が不愉快に思うことをしないようにと戒律を定めたのです。
そうでなくては人々から尊敬されたり、祈りを捧げてもらうことはできません。修行を続ける為には立派な人間で居続けることが大事だったのです。
日常でも、人の嫌がることをせず相手の気心を察し、自己管理をして、つつましく生きている人は好かれるし、尊敬されると思います。もし、誰かの機嫌を悪くさせてしまったと感じたときは、本来の意味を思い出してみてください。まずは相手の信用を得るために、自分の今を見直すことが大切かもしれません。