高齢者はタンパク質をしっかりと摂取することが重要だ。働き盛りの世代は動脈硬化を抑えるためのメニューを考えるのが望ましい。
「あとは睡眠もしっかりとる。一般に6時間以上の睡眠がヒトには必要です。短時間睡眠の体への負荷は想像以上に大きいですし、また、脳科学的にも睡眠は記憶の固定にとって重要な役割を果たしています。
さらに脳の中の老廃物は寝ることで洗い流されるので、短時間睡眠は将来の認知症リスクを高めます。そして、夜の睡眠をしっかりとれるようにするためには、日中の活動量を上げることが肝要です。しっかり寝るためには昼間に陽の光を浴びて、体を動かす。結局は『運動』がすべての基本になってくるわけですね」
さらにもう一つ、脳の老化予防にとって大事なのは「会話によるコミュニケーション」である。
脳を健康に保つには
「主観的幸福感」が重要
人との会話は常に相手の声の抑揚や仕草、表情などを総合的に判断しながら、自分がどんな言葉を発するかを判断する行為だ。言語能力や社会性、共感性といった脳のさまざまな領域を駆使するのが「会話によるコミュニケーション」であり、それは結果的に脳への良い刺激になる。
「一方で社会的孤立は認知機能低下のリスクを上げることが分かっています。できれば文字情報だけのSNSではなく、対面で相手の仕草や表情を見ながら話すことが望ましい。人が孤独感を抱くのは、何か楽しいことがあってもそれを伝える相手がいないときです。
逆に私たちが幸せを感じるのは、何か楽しいことがあったときに、それに共感してくれる家族や友達がいることでしょう。自分の気持ちを理解してもらえたと幸せを感じるからです。自分の気持ちを理解してくれる人の存在は脳の老化を予防するわけですね。
脳を若々しく保つためには、井戸端会議でも何でもいいので、ご近所の方や友人、ご家族と会話をするのがいい。運動や趣味活動でいろんな人と会話をして主観的幸福感を高める。それが脳を健康に保つことに必要なわけです」
こう語る瀧教授が最後に挙げるのが、「主観的幸福感」というキーワードだ。
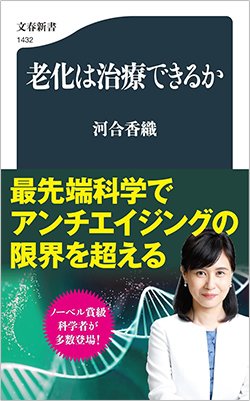 『老化は治療できるか』(文春新書)
『老化は治療できるか』(文春新書)河合香織 著
経済学では「幸福のパラドックス」と呼ばれる概念があり、所得の増加と幸福度は正比例しないとされているが、老化の予防においても、客観的な幸福よりも自分が幸せだと感じることが重要だという。人は日々、些細(ささい)なことであっても「幸せ」を感じるとストレスが和らぎ、生活習慣病による動脈硬化のリスクが下がるからである。
「主観的幸福感が高いとストレスレベルが下がる。そうすると生活習慣病のリスクが下がる。さらに、寿命が延びるだけではなく将来の認知症リスクも下がる。ほんのちょっとでもいいので、幸せだなと思えることは老化の予防のために何より大切なのです」







